
 新金谷駅に停車中のC10型「SL急行かわね路号」。
新金谷駅に停車中のC10型「SL急行かわね路号」。
 新金谷駅に停車中のC10型「SL急行かわね路号」。
新金谷駅に停車中のC10型「SL急行かわね路号」。

1930年に製造されたタンク機関車で、都市近郊旅客列車用蒸気機関車として開発されました。大井川鐡道の8号機は、同年に川崎車輌で製造、大宮機関区に新製配置されました。主に東北本線や高崎線で活躍し、それから1932年には高崎機関庫に転属し、新小岩機関区や田端機関区、水戸機関区にも貸し出されました。1941年仙台機関区に転属し、1949年には盛岡機関区に所属となり、山田線の旅客用列車に使われました。1961年には会津若松機関区会津線管理所の所属となり、会津線の旅客用・貨物用に使われる事になります。1962年廃車となってからは岩手県宮古市のラサ工業に譲渡され、1987年には「SLしおかぜ号」として走っていましたが、実際堤防沿いを走るので、海がほとんど望めず、1990年に運転を終了、休車となりました。その後宮古市は譲渡先を探していましたが、適当なタンク式蒸気機関車が必要だった大井川鐡道と意見が一致し、1994年に大井川鐡道に入線しました。

「SL急行かわね路号」は、寝台特急等のヘッドマークを付けて走る事もあります。
 「ドラえもん」に出てくる天の川鉄道にそっくりな車内。因みにマンガ版では、天の川鉄道はロングシートとなっているそうです。
「ドラえもん」に出てくる天の川鉄道にそっくりな車内。因みにマンガ版では、天の川鉄道はロングシートとなっているそうです。
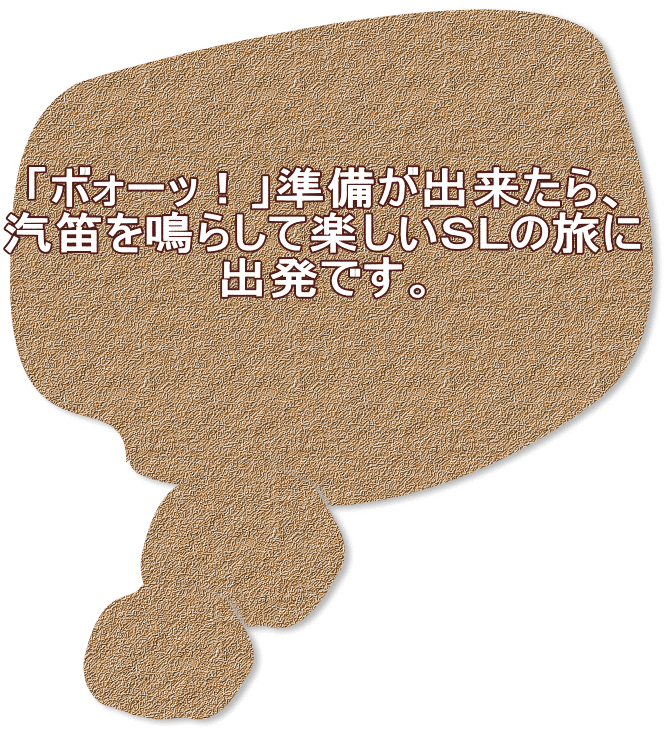

 茶畑が見えます。さすがお茶で有名な静岡県!
茶畑が見えます。さすがお茶で有名な静岡県!



 大井川と思われる川を渡り・・・・・・・・。
大井川と思われる川を渡り・・・・・・・・。

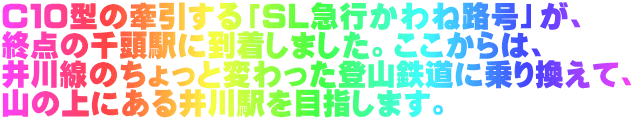
千頭駅の構内

 千頭駅にあった、海外の登山鉄道の模型。大井川鐡道井川線も、この鉄道と同じラック式鉄道(アプト式鉄道)なのです。
千頭駅にあった、海外の登山鉄道の模型。大井川鐡道井川線も、この鉄道と同じラック式鉄道(アプト式鉄道)なのです。

①マーシュ式
アメリカの技師マーシュによって考案された、ラック式鉄道としては初めての方式。L字型をした2本の鋼材(アングル材といいます)に、断面が丸型のピンを渡した、梯子型ラックレールを使う。
②リッゲンバッハ式
スイスの技師、ニクラウス・リッゲンバッハによって考案された。構造としてはマーシュ式に似たところがあるが、浅いコの字型をした鋼材(チャンネル式)と断面が台形のピンを使用している為、機関車のピニオンとの嚙み合わせも良くなっている。ラックレールの中ではアプト式に次ぐ普及率。
③アプト式
位相をずらした通常2~3枚のラックレールを使う。常に複数枚の歯車と歯軌条が噛み合っている。その為、重量級の車両にも適しており、3列式は幹線の鉄道にも使われている。スイスの技師、カール・ローマン・アプトによって考案された。ラック式鉄道では一番多い形式で、大井川鐡道井川線はここに含まれる。インドのニルギリ山岳鉄道、オーストリアのシャーフベルク鉄道もアプト式鉄道。
④ロヒャー式
ロッハー式とも表記する。ラックの歯は上下では無く側面にある。それを車体側のピニオン2つで挟む形になる。ピニオンの下には車輪にあるフランジに似た円盤があり、ラックから浮き上がらないようになっている。その為、あらゆるラック式鉄道の中で、最も急勾配に対応出来るのだが、構造上トングレールを用いる分岐器は使えない。なので、「ロータリースイッチ」と呼ばれる特殊な分岐器またはトラバーサーを用いて進路を切り替える。これを採用しているスイスのピラトゥス鉄道は、ケーブルカー等を除いた鉄道では、最も急勾配を登っていく(ピラトゥス鉄道の勾配480‰{※})。スイスの技師、エデュアルト・ロヒャー考案。
⑤シュトループ式
スイスのエミール・シュトループが考案した方式。頭の大きなレールの形をした鋼材に歯を付けてラックにする。普及率はアプト式、リッゲンバッハ式の次に多い。
⑥フォン・ロール
スイスのフォン・ロール社によって開発された。幅の広い単一のラックを使っている。分岐器まで含めて構造が簡単になっているので、リッゲンバッハ式やシュトループ式の置き換え用、又は比較的新しいラック式鉄道に見られる。
⑦フェル式(ラック式鉄道では無い)
フェル式は、厳密に言うとラック式鉄道には入れない。中央に設置された通常のレールを水平の2枚の車輪が挟み込んでいる。スウェーデンの技師ウィドマークが最初に発案したが、後にイギリスの技師ジョン・フェルによって完成された為、「フェル式」という。
※パーミル。鉄道は道路に比べ勾配が緩いのが一般的な為、%(パーセント)では表さない。大井川鐡道井川線の場合、1000m進む間に90m登るので、大井川鐡道井川線は「90‰」となる。
 千頭駅に止まって待っていた、大井川鐡道井川線の列車。井川線はトロッコ列車です。
千頭駅に止まって待っていた、大井川鐡道井川線の列車。井川線はトロッコ列車です。
 列車を牽引するのは、DD20というディーゼル機関車です。
列車を牽引するのは、DD20というディーゼル機関車です。

 列車内で見つけたこのハンドル、一体何に使うものなんでしょうか?
列車内で見つけたこのハンドル、一体何に使うものなんでしょうか?


井川線で使われていたものとみられる貨車。何を運んでいたのでしょう?

 井川から千頭方面に向かう列車とすれ違います。
井川から千頭方面に向かう列車とすれ違います。



