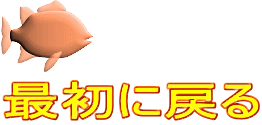近くにいた虫を捕まえました。この感じだと、恐らくカワゲラか何かだと思います。
近くにいた虫を捕まえました。この感じだと、恐らくカワゲラか何かだと思います。





 西行庵まで行き着きました。近くの水が流れ出ている辺りで、水筒に水を補給します。
西行庵まで行き着きました。近くの水が流れ出ている辺りで、水筒に水を補給します。


 ムネアカオオアリは、クロオオアリに似ていますが、名前の通り胸部から腹部の根元にかけてが赤っぽいのが特徴です。
ムネアカオオアリは、クロオオアリに似ていますが、名前の通り胸部から腹部の根元にかけてが赤っぽいのが特徴です。

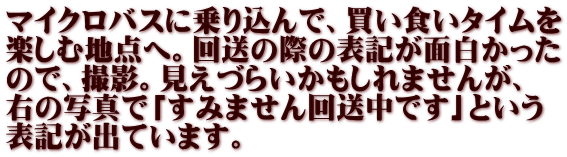
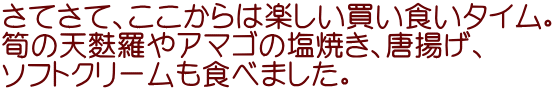
 お店にあったキツツキのおもちゃ。ヒモを引っ張るとキツツキが木をつつきます。遊び方を見たい方は下のリンクをクリックして下さい。
お店にあったキツツキのおもちゃ。ヒモを引っ張るとキツツキが木をつつきます。遊び方を見たい方は下のリンクをクリックして下さい。PICT0196.AVI へのリンク
 またカメムシを見つけました。こちらは家の近所でもよく見かける部類に入るクサギカメムシだと思われます。
またカメムシを見つけました。こちらは家の近所でもよく見かける部類に入るクサギカメムシだと思われます。
魚が沢山泳ぐ水槽。アマゴの塩焼きを買った辺りにあったと思います。



ニホンオオカミ
オオカミは正式には「ハイイロオオカミ」とか「タイリクオオカミ」と呼ばれ、シベリアオオカミやメキシコオオカミ、シンリンオオカミ等の亜種に分けられていて、ユーラシアや北アメリカ等、北半球に幅広く分布するイヌ科の動物です。でも、オオカミが日本にもいたと言ったら、皆さんは信じますか?実は、絶滅してしまいましたが、かつては日本にもオオカミが暮らしていたのです。ニホンオオカミというオオカミの亜種で、東北地方から九州まで幅広く分布していました。体長は95~114cm。尾長(尻尾の長さ)は30cm、肩高55cm、体重は推定15kg程度と、他の地域のオオカミに比べると少し小さ目でした。同体格の中型日本犬に比べると足は長く、脚力も発達していたようです。遠吠えをする習性があり、近くだと障子が震える事があったといわれています。絶滅の原因としては、狂犬病やジステンパー等のイヌの病気や家畜等を襲う害獣としての駆除、開発による獲物の減少や生息地の分断等によって絶滅したのではないかといわれています。最後のニホンオオカミは奈良県吉野郡小川村鷲家口(現・吉野村鷲家口)で捕獲された若いオスで、アメリカの鳥獣標本採集家マルコム・プレイフェア・アンダーソンと同行していた金井清及び猟師の石黒平次郎が、地元の猟師2名から8円50銭(この頃は10円あれば大人一人が1ケ月生活出来る時代だった)の値段で買い取ったものです。日付は1905(明治38)年1月23日でしたが、標本作製の際金井が「腹が腐敗しかけているところからみて、数日前に獲れたものらしい」との言及をしている為、捕獲されたのはそれより数日前だったと考えられます。剝製の作製は宿泊していた「芳月楼(現・皆花楼)」という旅館で行われました。吉野郡東吉野村には、「最後のニホンオオカミ像」が建てられています。日本にはもう一種、「エゾオオカミ」というオオカミがいましたが、これも1900(明治33)年頃絶滅したのではないかと考えられています。

ロープウェイがありましたが、この時は動いていませんでした。

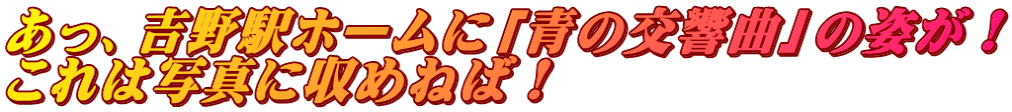



 「さくらライナー」もやって来ました。
「さくらライナー」もやって来ました。 僕達は、こちらの急行電車で帰る事に。行きに特急列車を使った以上、帰りは安い費用で済ませねばなりません。
僕達は、こちらの急行電車で帰る事に。行きに特急列車を使った以上、帰りは安い費用で済ませねばなりません。