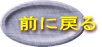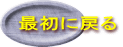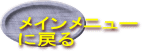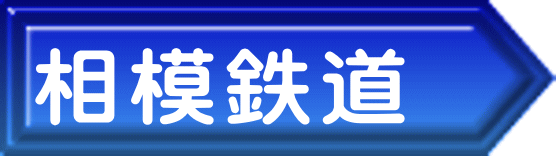
相鉄とも呼ばれる、神奈川県を基盤とした私鉄会社。開業したのは茅ヶ崎~橋本間(現・JR相模線)で、現在の相鉄線にあたる横浜~海老名間を開業させたのは、相模鉄道の元祖・神中鉄道という鉄道会社でした。1943年に神中鉄道は相模鉄道と合併し、八王子までの直通列車を走らせた時期もありました。特急の運転を行っていませんでしたが、2014年のダイヤ改正で導入されました。

2018年から走り始めている20000系をベースにして、8両編成にした電車です。東急目黒線との直通用で、20000系とよく似たデザインですが、車椅子・ベビーカースペースの変更、非常用ドアコック配置位置等、いくつかの点で違っています。2021年に営業運転を開始した電車で、相鉄新横浜線も通っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:相模鉄道
走っている路線:本線、いずみ野線、相鉄新横浜線

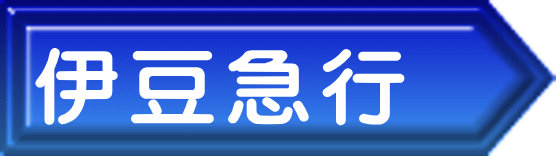
静岡県の伊東~伊豆急下田間を結ぶ、伊豆急行線の運転を主に行っています。複線区間は無く、全線単線です。海岸沿いを走る区間もあり、海が綺麗に見えるのも特徴です。伊豆半島は温泉地が多い為、建設当時、地盤に温泉が染み込んで落盤事故が起こる事が何度もあり、多くの建設員が犠牲になりましたが、1961年に開業を迎えました。また、JR東日本から「踊り子」「サフィール踊り子」といった特急列車が乗り入れています。

2005年に運転を開始した電車で、元東急の車両です。在籍両数は45両となっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:伊豆急行
走っている路線:伊豆急行線、JR伊東線
ヒミツ情報:伊豆急行の電車は、これまでに走っていた国鉄等の電車よりも、色を明るくする等工夫をした。

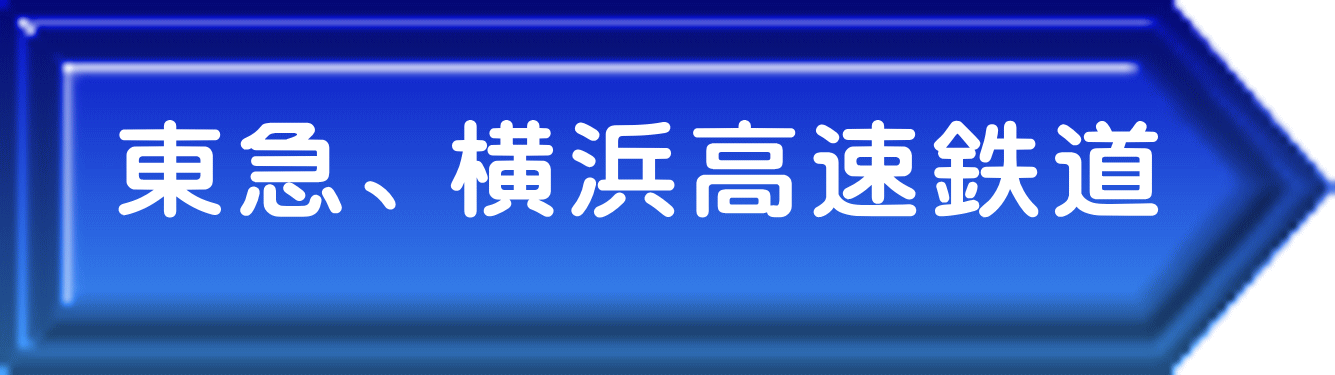
東急は鉄道と町づくりの両立で首都圏の人々の暮らしを支えてきた私鉄です。渋谷をターミナルとして横浜方面へ向かう東横線と、中央林間へ向かう田園都市線の二大幹線の他にも、住宅街を走る大井町線、目黒線、池上線、東急多摩川線、路面電車の世田谷線といった路線があります。横浜高速鉄道は1989年、みなとみらい線の事業主体として設立。2004年にみなとみらい線は開業しましたが、それより早い1999年、こどもの国線でY000系の運転が開始されました。その翌年である2000年には、こどもの国線通勤化も成されました。東急が第二種鉄道事業者(自らが敷設した以外の線路を利用して、旅客や貨物の輸送を行う鉄道会社)として旅客運送を、横浜高速鉄道は第三種鉄道事業者として線路を保有しています。

2019年にデビューした目黒線の新型車両です。大井町線の6020系、田園都市線の2020系同様に、「sustina」の車体を採用。「sustina」とは、オールステンレス車両のブランド名。山手線のE235系や京王ライナーも、sustinaを採用しています。目黒線ではワンマン運転を行う為、3020系には6020系や2020系と違い「強制ワンマン」のスイッチがあります。このスイッチをオンにすると、本来なら車掌さんが車掌室で行う作業を運転席で出来るようになるんだそう。先頭が丸っこく糊代も小さいので、もしかしたら木工用ボンドを使うのがオススメかもしれません。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東急
走っている路線:目黒線、東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道線、都営三田線
ヒミツ情報:相鉄と直通運転をするようになると6両が8両になる見込みである。


カッコいいボディが目を引く5050系は、東急の代表的な車両として、コマーシャルやポスターにも度々登場しています。東横線を中心に走っていて、当初より横浜高速鉄道みなとみらい線乗り入れに対応している他、増備車及び改造後には、東京メトロ有楽町線と副都心線、東武東上線、西武池袋線、相鉄本線、いずみ野線、そして相鉄新横浜線乗り入れにも対応するようになりました。なお、相鉄線に直通するのは4000番台のみで、4000番台は10両編成だそうです。同じグループの車両には、田園都市線用の5000系や、目黒線用の5080系もあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東急
走っている路線:東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線、東京メトロ副都心線、東武東上線、西武池袋線、相鉄本線、相鉄いずみ野線、相鉄新横浜線
ヒミツ情報:4000番台は区分公表前に「4000系」と称された事例もあった。
 写真左の電車は、4000番台の10編成目に渋谷ヒカリエ開業1周年記念として、2013年から走り始めた特別列車「Shibuya Hikarie号」。
写真左の電車は、4000番台の10編成目に渋谷ヒカリエ開業1周年記念として、2013年から走り始めた特別列車「Shibuya Hikarie号」。
緑色のカラフルな車体が特徴的なこの電車は、池上線や東急多摩川線用に、短い編成で造られています。ワンマン運転用の設備も兼ね備えていて、客室の一部にボックスシートを備えています。車体は5000系の系列と共通化してオールステンレス製となっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東急
走っている路線:池上線、東急多摩川線


1987年から1991年にかけて、初代7000系を改造して誕生した電車です。写真左側の車両は、「歌舞伎色」と呼ばれているそうですよ。確かに、言われてみれば歌舞伎役者にも見えてきますね。2018年に残念ながら引退してしまいましたが、今でも養老鉄道で元気に走っていますよ。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東急
走っている路線:大井町線、東急多摩川線、池上線


これは初代の5000系電車で、その車体色と正面形状から、「青ガエル」と呼ばれ親しまれてきた電車です。東急では最後となる普通鋼製で、この電車以降、東急の新車は全てステンレス製へと移行する事になります。西鉄313形で採用されたモノコック構造、高抗張力鋼を取り入れる事で軽量化を実現しました。1954年から1959年にかけて105両が製造され、東横線や田園都市線、大井町線等で1986年に引退するまで現役で活躍してきました。親しみを感じさせる外観から観光施設等で保存されている車両もあり、また、地方私鉄に譲渡されたものもあります。地方私鉄に譲渡されたものは大半が運用を終了しましたが、熊本電気鉄道で1両が動態保存されています。この写真には、もう一つ別の列車が写っています。何だか分かりますか?答えはこのページの一番下に記載しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東急
走っている路線:東横線、田園都市線、大井町線、目蒲線
ヒミツ情報:全長が18.5mであった為、東急池上線へは入線出来なかった。


長津田とこどもの国を結ぶ、こどもの国線用の通勤型電車です。車両は横浜高速鉄道が所有していますが、検査・整備は東急が行っています。その為、ほぼ同時期に製造された東急3000系がベースになっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:横浜高速鉄道(検査・整備は東急)
走っている路線:こどもの国線
ヒミツ情報:東急の乗務員には俗に「Y系」と呼ばれている。

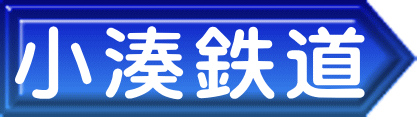
千葉県を走るローカル線で、五井から上総中野までをつないで走ります。ワンマン運転では無く車掌さんが切符を拝見する昔ながらの路線で、国鉄時代を思わせる車両が山里を走っているので、テレビドラマやコマーシャルにもよく出てくる路線です。ローカル線とはいえ東京に近い所を走るし、学校も多いから、大勢の人が利用するのかと思いますが、昼間はローカル線らしく、少ないお客さんを乗せてのんびり走っていますよ。

1961年から1977年にかけて、国鉄のキハ20形をモデルに設計された気動車です。製造当初は冷房設備がありませんでしたが、1990年~1993年にかけてキハ209、キハ210を除く12両が冷房化されました。作品はデビュー当初の仕様で、2022年以降は前面に車番号を追加し、雨樋を赤にした新塗装へのリニューアルが進められています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:小湊鉄道
走っている路線:小湊鉄道線
ヒミツ情報:1963年から1964年の夏季に運転された千葉~養老渓谷間の直通列車では、国鉄キハ20形をベースとしたその設計が役立ち、国鉄形気動車と連結して内房線(千葉~五井間。なお当時は内房線では無く房総西線だった)を走った実績がある。

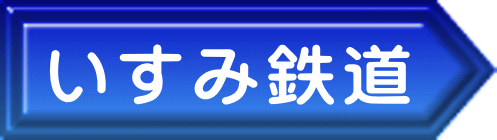
いすみ鉄道も千葉県を走るローカル線で、大原と上総中野との間で走っています。車両の長さが他の電車よりも短い事から、「レールバス」と呼ばれる気動車が走っています。

国鉄世代の気動車に似せて造られ、2013年より運転を開始しました。2015年には、イベント等に対応すべくトイレ付・クロスシートで、国鉄標準色となったキハ20 1303が導入されました。この為、キハ20形はいすみ350型に分類されます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:いすみ鉄道
ヒミツ情報:351と352では、前照灯のケースに差異が見られる。

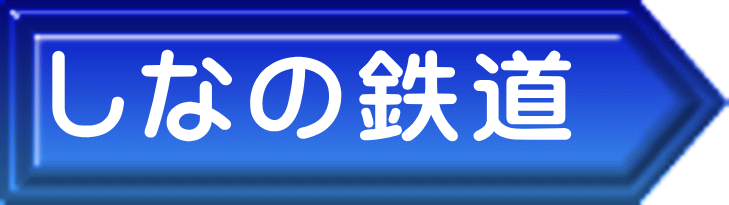
長野県を走るローカル線で、軽井沢と篠ノ井とを結ぶしなの鉄道線と、JR特急「ワイドビューしなの」の終点でもある長野駅から妙高高原まで走っている北しなの線の2つの路線を運営しています。昔JR線で走っていた115系が、通勤列車として走っています。

JR線からしなの鉄道に移ってきた車両で、写真のようなしなの鉄道オリジナルのの新塗装で走る車両もありますがJRと同じ色合いのものもあるようです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:しなの鉄道
ヒミツ情報:ドアは手動だが、発車時刻になると自動で閉まる。

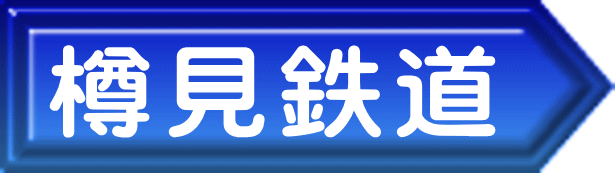
樽見鉄道は、岐阜県の大垣と福井県・樽見を結ぶローカル線です。冬になると雪が多く降る為、列車は雪をかき分けながら走って行きます。運転時間も1時間につき1~2本程度で、あまり多くはありませんが、地域の人々の足として活躍しています。
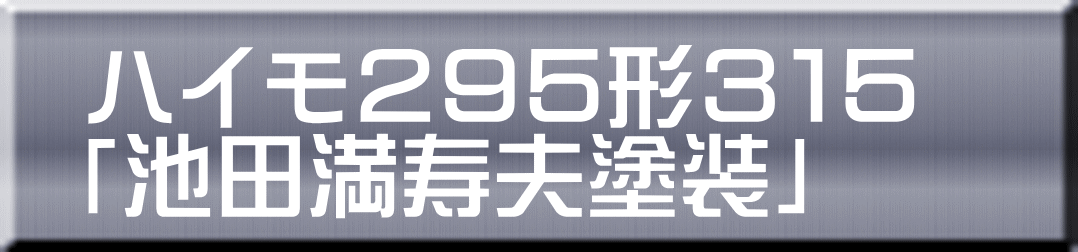
樽見鉄道の気動車にある「ハイモ」という記号は、「ハイスピードモーターカー」の略で、全ての車両についています。形式名の「295」は馬力表示の機関出力を意味しています。全長は16.5m。塗装は、ハイモ230-312に続いて池田満寿夫がデザインしたものでしたが、2020年3月からはプラレールのラッピングデザインに変更され、同年8月からは車内の壁面にプラレールキャラクターの「てっちゃん」が描かれた他、床面にはレールが描かれ、遮光カーテンも踏切やトンネルが描かれたものになりました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:樽見鉄道


名鉄こと名古屋鉄道は、大手私鉄の中では、近畿日本鉄道、東武鉄道に続いて、3番目に長いネットワークを持つ鉄道会社。ステンレス車体の電車がおおくなっていますが、大抵どこかにシンボルカラーの赤(名鉄スカーレットレッド)を入れています。名鉄スカーレットレッドはパノラマカーで初めて取り入れられたのですが、パノラマカーが大人気になると、他の電車にもスカーレットレッドが入るようになったんですね。名鉄名古屋駅が中心となる駅ですが、珍しい事に終着駅ではなく、通り抜けとなっています。

栄町と尾張瀬戸を結ぶ瀬戸線で走っている電車です。騒音や振動を抑える工夫をする等、沿線の環境に配慮した車両となっています。また、車椅子スペースがある等、車内もバリアフリーに対応しています。他の新型車両に比べると、デザインはやや角ばった感じです。瀬戸線用車両では初めてのステンレス車両でもあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:名古屋鉄道
走っている路線:瀬戸線


名鉄の最新型通勤車両です。名古屋鉄道初の車内防犯カメラや、無料でインターネットに接続出来る「MEITETSU FREE Wi-Fi」を搭載しています。ライトにはLEDを採用し、前面にも名鉄のイメージカラー、名鉄スカーレットレッドを強く打ち出しました。なお、9500系は4両編成の電車、同じ形状で2両編成の9100系もあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:名古屋鉄道
走っている路線:名古屋本線、犬山線、常滑線


名鉄で初めての本格的な通勤車両です。ラッシュ時に列車が遅れるの防ぐ為に、片側3か所の扉を本格的に採用しています。1977年に鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞した車両ですが、通勤型車両がブルーリボン賞を受賞するのはこの車両が初となります。一部6500系と同じデザインのものもあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:名古屋鉄道
走っている路線:名古屋本線、犬山線、常滑線、三河線、空港線
ヒミツ情報:空港線は中部国際空港連絡鉄道が第三種鉄道事業者として施設の建設や保有を行い、名鉄はこれを借り受けて「第二種鉄道事業者」として列車を走らせている。


1979年に登場した電車で、名古屋市営地下鉄鶴舞線との相互直通乗り入れを目的として開発されました。名鉄が製造した車両としては初の20m級4扉のロングシート車両です。1980年には鉄道友の会ローレル賞受賞車両にも選出されています。なお200系はベースは同じですが走行用システムの変更がされています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:名古屋鉄道
走っている路線:豊田線、犬山線、名古屋市営地下鉄鶴舞線

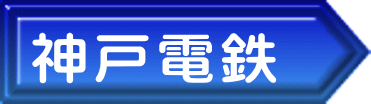
兵庫県南東部で神戸市の湊川駅を起点に、有馬温泉、三田、粟生を結んでいます。創業時は「神戸有馬電気鉄道」と呼ばれていて、その略称で「神電」とも呼ばれます。
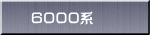
2008年に登場した神戸電鉄の通勤型電車です。1994年の5000系以来の新型車両で、ワンマン運転に当初より対応しています。親会社である阪急電鉄の9000系と共通する特徴が多く見られます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:神戸電鉄
ヒミツ情報:種別・行き先表示にフルカラーLEDを採用している。

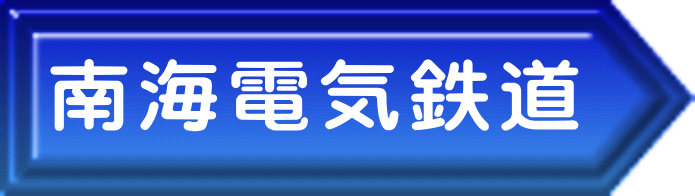
南海電気鉄道の南海本線は、大阪の難波と和歌山県・和歌山市を結んでいます。1000系、2000系、7100系、8000系、9000系等の電車が、南海本線の普通や急行、準急として走っています。堺や岸和田、新今宮等の大阪の大きな町を通る為、通勤に利用する人が多いようです。多くの通勤列車は、灰色か銀色の車体に、青とオレンジのラインが入っています。南海電気鉄道は、現存する日本最古の私鉄会社。1885年に前身となる阪堺鉄道が営業開始しました。

1992年に登場した電車で、9000系電車の後継系列として運転を開始しました。2000系に導入された新技術を取り入れつつ、1994年の関西国際空港開港を見据え、南海グループ全体の新CI戦略に伴い、新しいデザインを盛り込みました。南海本線・高野線の双方で共通運用可能なハイグレードな次世代汎用通勤型電車として設計され、新造の度に機会を捉えて様々な改良が加えられ続けており、1次車、2~5次車、6次車(50番代)の3つのグループに分けられます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:南海電気鉄道
走っている路線:南海本線、空港線、高野線、泉北高速鉄道線
ヒミツ情報:難波の次の駅は今宮戎だが、その今宮戎に停車するのは高野線各駅停車のみ。南海本線普通電車は今宮戎には停車しないのだ。


6300系へ改造された6100系とデザインや性能はほぼ同じですが、この電車は南海本線用で鋼鉄製の車体です。。1969年から1973年にかけ、近畿車輛と東急車輛製造において152両が製造されており、これは2009年まで南海車両史上最多の両数でした。2015年に7000系が引退した為、本線を走る通勤車両は本系列を含めて全て両開きになりました。10000系と連結して特急「サザン」の自由席車としても走ります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:南海電気鉄道
走っている路線:南海本線、空港線、加太線


南海高野線橋本駅~極楽橋駅間の山岳区間への直通運転の為に開発された「ズームカー」の1形式です。途中での仕様変更が多く、製造年によりパンタグラフの取り付け位置や車体外板のビード数、内装、座席配置等に違いがみられます。基本的に車体はステンレス製で、VVVFインバーター制御も採用しました。写真にあるうち赤い方の電車は「真田赤備え列車」で、2015年から2019年の間走っていました。基本的に車内はロングシートですが、一部クロスシートとなっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:南海電気鉄道
走っている路線:南海本線、空港線、高野線
ヒミツ情報:本線で走る場合は2扉車扱いとなる。その時は種別表示の下に写真にあるように「2扉車」のステッカーを掲示する。


中央・総武緩行線や東海道線等で走っているE231系電車の設計を一部に取り入れています。9000系や1000系、8300系と連結して走る他、12000系「サザン・プレミアム」と連結して走る事もあります。なお、「サザン・プレミアム」と連結して走る際には8000系は自由席車両となります。前面及び側面の種別・行先表示器には南海初となるフルカラーLED、白色LEDが採用されました。定員着席保護の為のスタンションポール等、車内には大型の手摺が多数設置されています。貫通路幅を775mmに拡張する事、床面の高さを1000系の1170mmから1150mmに低くする事により、駅ホームとの段差を縮小する等のバリアフリー化が図られています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:南海電気鉄道
走っている路線:南海本線、空港線
ヒミツ情報:2015年12月以降は9000系、2020年12月以降は8300系も「サザン」自由席車両としての運用に入っている為、日によっては本形式が入らない事もある。


南海本線系統で初めて、オールステンレス製となった電車がこの9000系です。高野線用の8200系(現・6200系)と一部の設計は同じになっています。2018年度よりリニューアル工事が行われており、2021年度までに4両編成が全てリニューアルされ、残る6両編成2本に関しても随時更新対象となる予定です。「サザン」の12000系とはブレーキ方式等がほぼ共通しており、実際に併結運転が可能となっています。2015年12月10日に12000系と連結して以降、「サザン」の自由席車両にも使用されています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:南海電気鉄道
走っている路線:南海本線、空港線
ヒミツ情報:側面の車両番号は南海伝統の欧風書体なのだが、この電車が最後の採用となっている。

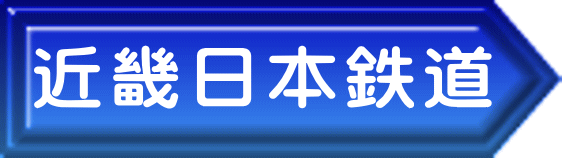
京都、大阪、奈良、三重と、幅広い範囲に路線を持っています。全ての路線の営業距離を合わせると、500kmに及ぶ、日本の私鉄では一番長い距離を誇る鉄道会社です。

L/Cカーだなんて不思議な名前の電車ですが、この不思議な名前は、この電車がロングシートとクロスシートを切り替えられる事から来ています。屋根に取り付ける部品の中に、細かいのがありますので気をつけてください。Webページ「近鉄電車ペーパークラフト」収録作品。
所有している鉄道会社:近畿日本鉄道
走っている路線:大阪線、奈良線、名古屋線、阪神本線

<写真に写っている他の列車の答え>
(東急5000系・初代)787系「つばめ」→「JR特急」参照