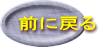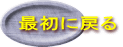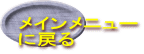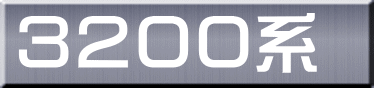
京都市営地下鉄烏丸線乗り入れ用としてデビューした、近鉄では初の量産型VVVFインバーター制御車両です。8000系にはアルミ車体試作車がありましたが、この編成で試験採用されたアルミニウム合金車体を本格的に採用しています。前面は非対称のデザインで、左曲面ガラスを備えて車体上部を若干傾斜させた「く」の字型の断面となっています。地下鉄線を走行する車両なだけあって、前面の貫通扉は中心部より左側に寄せられた非常扉になっています。塗装は近鉄の一般車両では初めてのマルーンとシルキーホワイトとなり、後に在来の一般車両も本系列に合わせて塗装を変更しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:近畿日本鉄道
走っている路線:難波線、奈良線、京都線、橿原線、天理線、京都市営地下鉄烏丸線
ヒミツ情報:地下鉄対応車両としては珍しく、山岳トンネル(奈良線・新生駒トンネル、新向谷トンネル)を走行する。1988年の地下鉄相互直通開始時には記念装飾が施されていた。


3220系は、「シリーズ21」と呼ばれる次世代の一般型車両の最初の形式です。2000年にデビューしました。こちらも3200系同様、京都市営地下鉄烏丸線に乗り入れる電車。「シリーズ21」は、「人に優しい、地球に優しい」「コストダウン」をコンセプトに開発されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:近畿日本鉄道
走っている路線:難波線、大阪線、奈良線、京都線、橿原線、天理線、京都市営地下鉄烏丸線
ヒミツ情報:地下鉄対応車両としては珍しく、山岳トンネル(奈良線・新生駒トンネル、新向谷トンネル)を走行する。


1988年に登場した、大阪線、名古屋線の急行用電車です。快適さを追求して、自動転換クロスシートを採用しています。正面の窓は曲面ガラスで、客室からの眺めを良くする為に、貫通扉の窓は縦長になっています。本形式の改良型として、1991年に登場した5209系、1993年に登場した5211系があります。1988年にグッドデザイン商品にも選定されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:近畿日本鉄道
走っている路線:大阪線、名古屋線


先程の3220系と一見よく似ていますが、こちらは5800系と同じく「L/Cカー」と呼ばれる車両です。やはり混雑する朝夕がロングシート、昼間の時間帯がクロスシートという風に、ロングシートとクロスシートを切り替える事が可能な車両です。5800系同様、阪神電車への乗り入れも行っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:近畿日本鉄道
走っている路線:大阪線、奈良線、京都線、阪神本線

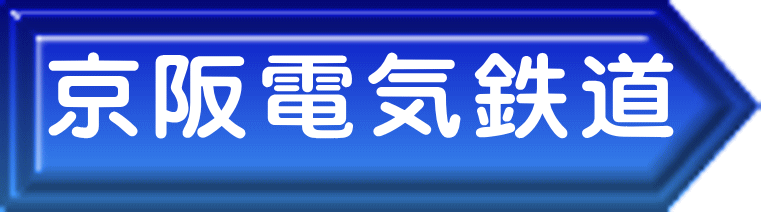
京都、大阪、そして滋賀県に路線を持っています。京街道に沿って走っていて、カーブが多いのも特徴です。日本初の技術を沢山生み出している、技術のトップランナーです。通勤列車は主に緑と白に黄緑のライン。石山坂本線の電車には、見ているだけでも楽しいラッピング電車も走っています。

石山坂本線の電車で、石山坂本線は滋賀県の石山寺と、同じ滋賀県の坂本比叡山口とを結んで走っています。電車は2両編成です。石山坂本線の浜大津駅、別所駅、皇子山駅、そして坂本駅は、それぞれびわ湖浜大津、大津市役所前、京阪大津京、坂本比叡山口に名称を変更しました。写真の作品では、車両の後部に切れ目を入れ、その切れ目に紙切れで作ったジョイントを差し込んで2両編成にしました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京阪電気鉄道
走っている路線:石山坂本線


600形と同様、石山坂本線の電車です。型紙は1両分しかないので、2両編成にしたい方は、2枚印刷して幌1つで完成した2つの車体を組み合わせて下さい。Webページ「CUBY TRAM AND BUS’sPAPER MODELS」収録作品。
所有している鉄道会社:京阪電気鉄道
走っている路線:石山坂本線


宇治線に投入された新型車両で、京阪本線や中之島線等でも見られます。安全性を高め、消費電力を大幅に抑えました。また、座席の下に脚や機器類の無い「片持ち式」の座席も、京阪電車では初めて導入されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京阪電気鉄道
走っている路線:京阪本線(鴨東線の区間含む)、中之島線、宇治線、交野線
ヒミツ情報:普通新型車両のパンタグラフはシングルアーム型だが、13000系のパンタグラフは、昔の車両のパンタグラフを使っている為下枠交差型。


10000系は2002年に登場しました。老朽化した1900系や2600系0番代の置き換え用、そして将来の支線である宇治線や交野線のワンマン運転実施を目的として製造されました。後継車種は本形式をベースに新3000系の意匠を取り込んだ13000系に移行しており、6000系から続いた大型非常扉を採用した最後の車両です。デビュー当時はターコイズグリーンでしたが、2009年から2010年にリニューアルが進行し、写真のような塗装になっています。一部は7200系や9000系から改造された車両を組み込んで7両編成とし、京阪本線で使われるようになりました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京阪電気鉄道
走っている路線:京阪本線、宇治線、交野線


名前通り、大阪と兵庫県の神戸を結ぶ私鉄です。プロ野球球団・阪神タイガースの親会社でもあり、本線の駅にも甲子園駅というのがあります。また、神戸高速鉄道の区間で阪急電鉄や山陽電車と相互乗り入れを行っています。

快速急行や特急、直通特急のような優等列車に使われる車両です。2009年に阪神なんば線の西九条~大阪難波間の延伸に伴う、阪神と近鉄の相互直通運転に先駆けて、2006年より製造が開始され、2007年から営業運転に入っています。なお、快速急行は、2009年に運転を開始しました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:阪神電鉄
走っている路線:本線、阪神なんば線、近鉄奈良線、山陽電鉄本線
ヒミツ情報:急行系の「赤胴車」と呼ばれる車両ではあるが、阪神なんば線、近鉄難波線・奈良線では普通電車でも運用されている。

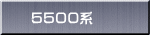
高加速・高減速の「ジェット・カー」と呼ばれる車両の1つです。愛称は「従来の車両をプロペラ機に例えるならこの車両はジェット機に匹敵する位の加速・減速の良さである」という比喩からつけられました。青銅車とも呼ばれ、「ジェット・カー」は主に普通電車で走っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:阪神電鉄
走っている路線:本線、武庫川線
ヒミツ情報:高加速・高減速の車両には、「ジェット・カー」の他、京阪「スーパーカー」、近鉄「ラビット・カー」等があったが、高加速・高減速運用を排除された為、「ジェット・カー」のみが現在残っている高加速・高減速の車両。


これも5500系と同じく、「ジェット・カー」の1種です。2015年にデビューした新型のジェット・カーで、「ジェット・シルバー5700」という愛称でも呼ばれています。2016年には鉄道友の会ブルーリボン賞も受賞しています。ジェット・カーとしては13形式目の車両です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:阪神電鉄
走っている路線:本線
ヒミツ情報:過去にはテレビ番組の企画でTOKIOメンバー5人と50m×5人で250mのリレー対決を行った事も。

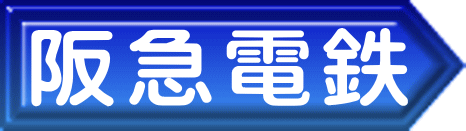
大阪の梅田を起点に、京都や宝塚、神戸を結んでいます。全身マルーン・カラーと呼ばれる茶色い車体の電車が、各駅停車、快速、特急、急行、準急、快速急行、通勤特急、通勤急行等で走っています。また、団員が全て女性の劇団「宝塚歌劇団」を運営している事でも知られています。色々な形式がありますが、系列名は、神戸・宝塚線用は100の位が0~2、京都線用は100の位が3で、それぞれ別の電車なのですが、1000の位が同じならばタイプとしては基本同じ電車という事になります。

2013年にデビューした電車です。新世代の神戸・宝塚線用で、音の小さいモーターを備える等、最新技術を取り入れた、静かな電車となりました。その翌年の2014年には、京都線用の最新型車両で兄弟車の、1300系もデビューしています。静かさの他にも省エネルギー性能、バリアフリーにもこだわっています。電装品等は先程紹介した、阪神電鉄の新型ジェット・カー、5700系にも取り入れられています。客室照明や前照灯、標識灯等、全ての照明装置にLEDを取り入れました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:阪急電鉄
走っている路線:神戸本線、宝塚線

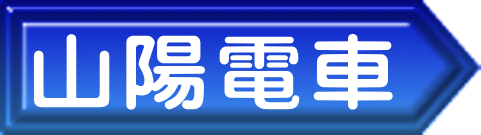
本線は西代から山陽姫路までを、網干線は本線の飾磨駅から山陽網干駅を結んでいます。一部、JRの線路と並行して走る区間があります。

1964年から導入された電車です。神戸高速鉄道の開業と阪神・阪急との相互乗り入れを踏まえて登場しました。初期車はオールアルミ合金製という技術が評価され、1965年に鉄道友の会ローレル賞を受賞しています。かつては特急から普通まで幅広く活躍していましたが、2001年のダイヤ改正以降は普通(3両、4両)を主体にS特急に使われる事もあります。但し、特急運用終了後も車両トラブル等の場合は車両交換の上で直通特急として走る事もあります。また、4両編成が付随車1両を外し3両編成で走る場合もあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:山陽電車
走っている路線:本線、網干線、神戸高速線

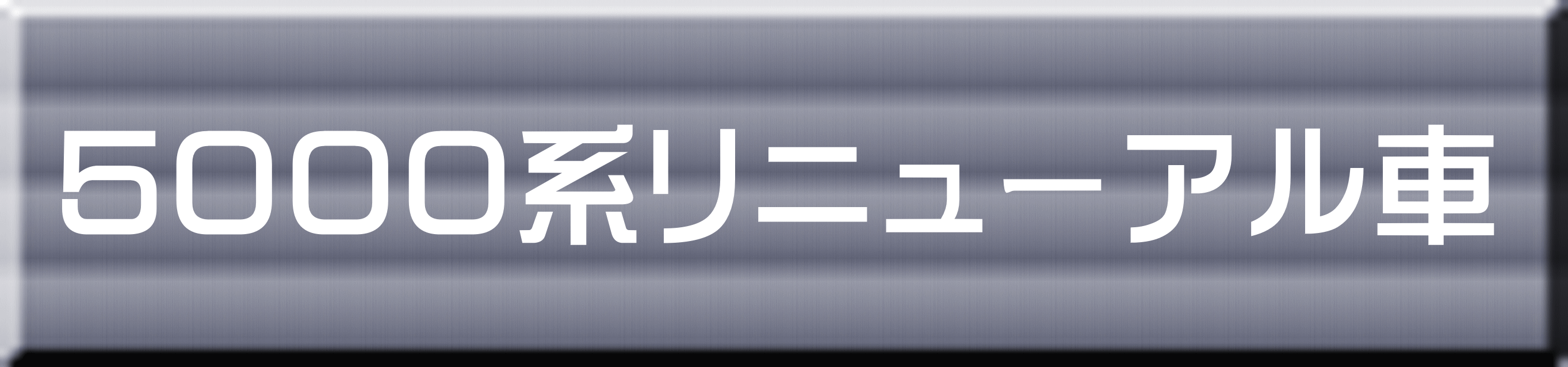
3扉セミクロスシートの電車で、特急での運用が主体である為、特急型電車に分類される事があります。吊り掛け駆動方式を採用する旧性能車の置き換え用として製造され、普通列車運用に充当されていましたが、その後の増備、増結になり特急運用にも充当されるようになり、現在では直通特急を主体とした優等列車に使われています。2018年よりリニューアルが行われ、前面及び側面表示器もフルカラーLEDのものに取り替えられ、各車の車両番号が側面下部だけでなく連結面寄りの上部にも表示されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:山陽電車
走っている路線:本線

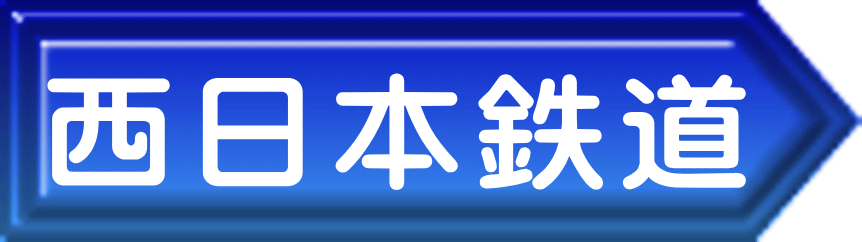
「西鉄」とも呼ばれ、西鉄福岡(天神)と大牟田を結ぶ天神大牟田線、西鉄新宮と貝塚を結ぶ貝塚線、天神大牟田線の西鉄二日市から学問の神様・菅原道真(菅家)が左遷された太宰府まで走る太宰府線、そして基山から甘木まで走る甘木線の、計4つの路線があります。九州では唯一の大手私鉄です。

天神大牟田線の急行や特急に使われる車両で、2007年に鉄道友の会ローレル賞を受賞しました。ローレル賞というのは、通勤列車を選定対象とした、技術面で優秀な車両を評価する賞のことです。なお、ローレル賞のローレルは月桂樹という木のことで、記念プレートに描かれる月桂冠は栄誉を意味します。先端部は少し曲げる感じで完全に折ってしまわない方が、見栄えが良くなります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西日本鉄道
走っている路線:天神大牟田線、太宰府線
ヒミツ情報:太宰府観光列車「旅人」や柳川観光列車「水都」に改造された編成もある.


1975年に登場した電車で、輸送力を増やす為に136両も造られました。4両編成が終日普通列車に充当されており、平日日中は6両編成も数本急行で走っています。「系(けい)」「形(がた)」という呼び方は、鉄道会社それぞれで決めていますが、西鉄は「形」と書いて「けい」と読むんだそうです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西日本鉄道
走っている路線:天神大牟田線
ヒミツ情報:天神大牟田線の端間~宮の陣までは長い直線区間が続くので、普通電車でも時速90km、最高で時速100kmの走行をする。


2017年に、5000形の代替として製造された電車で、天神大牟田線の最新型電車です。3000形をベースに安全・サービス・省エネルギーの性能を向上させています。制御装置にSiC素子を適用したVVVFインバーター制御を採用した事により、前照灯、尾灯、車内の照明と、全ての照明をLED化しました。車体はステンレス製で、5000形と同じく、片側3扉のロングシートとなっています。デザインは前に進む力強さと次世代型車両としての新しさを表現しつつ、車体側面には歴代車両でも多く採用された赤帯を配置しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西日本鉄道
走っている路線:天神大牟田線


貝塚線は西鉄新宮から貝塚までを結ぶ路線。西鉄のどの路線ともつながっていませんが、博多方面へ向かう地下鉄と乗り換えが出来るので、通勤には便利な路線です。過去には西鉄新宮より先もあり、津屋崎まで路線があって、路線名も「宮地岳線」だったそうです。600形は1962年に登場した電車で、元は天神大牟田線を走っていました。天神大牟田線時代は先に紹介した5000形と同じような色合いでしたが、現在は写真のような黄色に赤のラインです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西日本鉄道
走っている路線:貝塚線


1952年に製造された電車で、1977年からは宮地岳線(現在の貝塚線)で運転されました。普通鋼ながら日本で初めてモノコック構造を採用した電車で、2015年まで50年以上も現役で走り続けました。貝塚線時代は先程の600形と同じような色合いでしたが、最後に残った1編成は引退の1年前の2014年に、写真のような大牟田線(現在の天神大牟田線)時代の色に戻されました。因みにモノコック構造とは、車体や機体の骨組み(フレーム)の代わりに、外板に必要最小限の加工を施して強度剛性を持たせる設計の事。後に新幹線にも採用されたんだそうです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西日本鉄道
引退時に走っていた路線:貝塚線