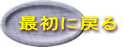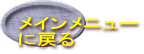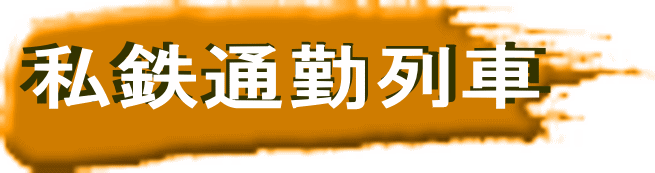
私鉄には、長い編成の電車から1両で運転されるレールバスまで、色々な種類の通勤列車が走っています。通勤するお客さんが快適に利用出来る様に、鉄道会社それぞれが工夫を凝らしています。走っている路線については、明確なもののみ記しておきます。
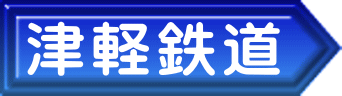
青森県の津軽地方を走るローカル線で、冬の時期には車内にダルマストーブがある「ストーブ列車」が運行される事で有名です。路線距離は僅か20.7km位ですが、春の桜は綺麗ですよ。
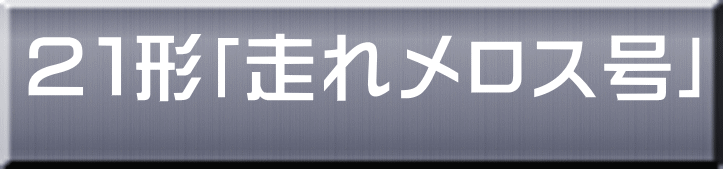
新潟トランシス製の18m級気動車で、津軽鉄道沿線が出身の作家・太宰治の有名な作品「走れメロス」に因み、車両の愛称も「走れメロス号」となっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:津軽鉄道
走っている路線:津軽鉄道線

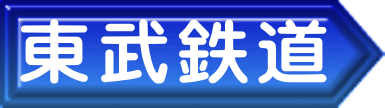
東京、埼玉、千葉、栃木、群馬と、広い範囲に路線を持っています。少し古い車両から新型車両まで、通勤列車の種類も様々で、色々な色があります。

東武鉄道の通勤車両として初めてアルミ合金製の車体を採用した、オレンジ色と銀色の通勤列車。ダブルスキン大型材の適用により車内の遮音性向上及び車体軽量化、それに伴った消費電力軽減、更に各部のアルミ材質を統一し、リサイクル性能を向上させる等、車両構造の大幅な見直しを行い環境負荷の軽減を図っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東武鉄道
走っている路線:50000系は、基本的に形式別による運用区別はあまり見られない。東武東上線の他、東京メトロ有楽町線・副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線でも運用


東武アーバンパークラインこと野田線の新型車両で、2013年より営業運転を開始しています。「人と環境に優しい車両」をコンセプトに設計されており、VVVFインバータ制御やLED照明を採用しました。また、車体にアルミ合金を使い軽量化した事で、省エネ化を図っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東武鉄道
走っている路線:アーバンパークライン


急勾配等の対策として、特殊なブレーキや砂撒き装置等を兼ね備えた、高性能な通勤型電車。長距離移動も考えてトイレも設置しています。東武鉄道と会津鉄道では2022年に引退。現在では野岩鉄道で少ないながらも頑張っていますWebページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:東武鉄道
走っている路線:日光線、鬼怒川線、会津鉄道会津線、野岩鉄道会津鬼怒川線
ヒミツ情報:違う行き先の電車をつないで走る事もあった為、車内にも行き先表示器が付いている。

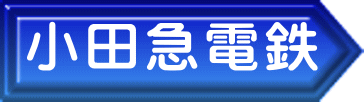
小田急電鉄は、東京と神奈川に路線を持っています。特急列車のロマンスカーだけでなく、通勤列車にも色々種類があります。小田急は正式名称を「小田原急行電鉄」といいますが、「東京行進曲」の歌詞に「小田急」とあった為、「小田急」の略称が広まりました。これに当初小田急電鉄側は反対していましたが、その後は会社の宣伝になると認めたそうです。

JR東日本のE233系をベースに、改良を加えた電車です。東京メトロ千代田線との直通運転に対応した仕様で、JR常磐緩行線にも直通しています。車体の90%が、リサイクル出来るようになっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:小田急電鉄
走っている路線:小田原線、江ノ島線、多摩線、東京メトロ千代田線、JR常磐緩行線


1995年から運転を開始している車両で、グッドデザイン賞も受賞しています。前面・側面ともに種別・行先表示はLEDを採用し、騒音や振動の少ない「環境にやさしい車両」、快適に乗車出来る「お客様にやさしい車両」、旅客の案内や安全確保に専念出来る様に、付随的な作業を自動化した「乗務員・駅員にやさしい車両」、そして熟練を要する機器の排除やモニター監視を可能とした「保守にやさしい車両」をテーマに登場した電車です。8両編成だけで、各駅停車に使用されています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:小田急電鉄
走っている路線:小田原線、多摩線
ヒミツ情報:2009年から、前面・側面の種別・行先案内表示がフルカラーLEDに交換された。


3000形は、今小田急で走っている通勤車両の中で、一番多く造られた電車です。2001年から2006年もの間に、何と合計312両が製造されたんですよ。車体構造等についても大幅な見直しを図り、一層のコスト削減と環境負荷の低減を図る車両として登場しました。増備の過程で「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」が制定された為、これを受けて車体の基本構造に変更が加えられている為、製造年次によって細部仕様に違いが見られます。この作品は1次車です。快速急行から各駅停車まで幅広く使われる、小田急電鉄の主力車両です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:小田急電鉄
走っている路線:小田原線、江ノ島線、多摩線


1983年にデビューした車両です。同じ小田急線を走る他の電車と比べると、少し古い車両ではありますが、大きな曲面ガラスを採用した先頭車両は、それまでの通勤列車の常識を覆したといいますから、本当にスゴイ車両です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:小田急電鉄
走っている路線:小田原線、江ノ島線、多摩線


東京と千葉県に路線を持つ鉄道会社。多くの電車は、赤と青の2色のライン。関東を代表する私鉄の1つで、成田空港にも乗り入れています。

3000形は、京成電鉄で最も数の多い電車で、各駅停車から特急まで、幅広く使われています。都営地下鉄浅草線や京急電鉄の路線にも乗り入れています。2003年にデビューした車両で、この後紹介する3050形は、成田スカイアクセス線が開業した時に、3000形に改良を加えて誕生した電車です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、北総線、都営地下鉄浅草線、京急本線、京急空港線


京成電鉄の主力車両で、デビューしたのは1991年。124両も製造されました。成田空港ターミナルへの乗り入れと北総鉄道2基線開通を機に導入された車両で、シルバーメタリックの塗装が施されています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、北総線、都営地下鉄浅草線、京急本線、京急空港線
ヒミツ情報:3400形と車体構造は同一。その為意外と外見だけで区別出来なかったりする。


京成スカイアクセス線のアクセス特急用車両として開発されました。京成には、赤と青のラインが多いのですが、こちらは飛行機をモチーフにしたデザインとなっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、北総線、都営地下鉄浅草線、京急本線、京急空港線
ヒミツ情報:3100形の登場後は、他の車両と同じ色になった編成も見受けられる。


僕も図鑑でこの電車の写真を初めて見た時、「えっ、これ京成?」と驚かされたものです。2019年から走り始めている新型の車両で、京成電鉄だけでなく、新京成電鉄等、京成電鉄に関係の深い会社が同じ電車を使えるように、よく考えて設計されています。成田空港へのアクセス特急にも使われる為、大きな荷物置き場もあります。車体のあちこちに飛行機が描かれている他、沿線の名所も描かれているので、見ているだけでも楽しそうですね。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、成田スカイアクセス線、都営地下鉄浅草線、京急本線、京急空港線


1968年にデビューし、2015年に引退するまで現役で走っていた電車です。今まで見てきた電車に比べると、角が丸いデザインで、このデザインから愛されてきた名車でもあります。3000系「赤電」シリーズの最終形式で、モーンアイボリーにファイアーオレンジ、銀縁のミスティラベンダー帯というツートンカラーの赤電塗装で落成した、最後の形式となりました。因みに初代の赤電は、日本の私鉄の電車で初の、地下鉄(都営1号線・現在の都営浅草線)との相互直通運転を開始したすごい電車なんですよ。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄

 ←赤電復刻色
←赤電復刻色
1982年登場の、軽量オールステンレス製車両です。3000形や3100形、3700形に比べると少々古い車両ではありますが、まだまだ現役で頑張っています。但し、3000形や3100形に置き換わって引退も進んでいるようです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、金町線
ヒミツ情報:4両編成の電車には、全車両先頭車両で運転台が付いている編成があり、「ターボ君」と呼ばれている。


1972年から1982年の間に、24編成96両が製造されました。京成電鉄の通勤電車としては初めて冷房が搭載され、車体の外側の板はステンレス、骨組みは鋼鉄製です。この電車は、先程紹介した通り形成初の冷房車なんですが、それだけでは無く、京成初のステンレス車体でもあります。東成田と芝山千代田の2駅をつなぐ日本一短い鉄道会社の芝山鉄道も、この車両を借り受けて運転しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京成電鉄
走っている路線:京成本線、千葉線、金町線
ヒミツ情報:芝山鉄道には、京成電鉄の車両も乗り入れてくるが、ICカード「PASMO」等は使えないので要注意!

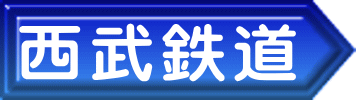
西武鉄道は、東京都と埼玉県を主に走っています。黄色い車体のイメージが強いかもしれませんが、実際色々な色の電車が走っています。路線の数もとても多く、新都市交通システム(新交通システム)のレオライナーこと山口線を入れても12の路線があり、大都市から地方の町まで、様々な区域で走っています。近江鉄道も、「西武グループ」に入っている為か、ラインの色がここでは紹介していませんが4000系と似ています。

2000系は混雑緩和の為4扉車として製造されましたが、これに戸袋を追加する等、様々な変更を加えたのがこの新2000系です。2021年3月現在、366両もある、西武鉄道では一番数の多い電車です。Webページ「ペーパークラフト|西武鉄道キッズ」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:池袋線、新宿線、拝島線、国分寺線、西武園線、狭山線
ヒミツ情報:更新車は行先表示がLED方式。


「人に優しく、みんなの笑顔を作り出す車両」をコンセプトに、2008年より営業運転に入っている通勤型電車です。「スマイルトレイン」という愛称で親しまれています。Webページ「ペーパークラフト|西武鉄道キッズ」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:池袋線、新宿線、拝島線
ヒミツ情報:車体にはアルミを使用しており、軽くて強い構造。


古くなった101系を取り替える為に、2000年に登場した電車です。カッコいい車体は「アルミダブルスキン」で、軽くて強度が高くなっています。また、騒音を小さくする様々な工夫が施されています。設計コンセプトは「シンプル&クリーン」。前照灯は丸型のシールドビームで、LED式の後部標識灯と共に、同一ケース内に収めたものを、前面腰部に左右1ヶ所ずつ配置したスタイルを取っています。西武鉄道で初めて、ワンハンドルマスコン、LEDによる車外表示も採用しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:池袋線、新宿線、拝島線


101系のモーターや台車等の機械類を再利用して、片側のドアが4ヶ所の車体を新しく造って組み合わせ、1993年にデビューしました。2003年~2007年にかけてVVVFインバーター制御への改造が施され、より環境に優しい電車へと生まれ変わりました。西武鉄道最後の「黄色い電車」です。10両固定編成時代は池袋線や新宿線でも活躍していたみたいですが、現在は4両編成に短縮され、ワンマン化改造も行われました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:多摩湖線
ヒミツ情報:京急とのコラボで生まれた「RED LUCKY TRAIN」や埼玉西武ライオンズ応援の「L-TRAIN」といった特別塗装もあった。


西武池袋線と営団(現・東京メトロ)有楽町線の相互直通乗り入れ用の電車として、1992年に運転を開始した通勤型電車です。ステンレス製の車両とアルミニウム製の車両があり、微妙に違いが見受けられます。西武らしい「黄色い電車」のイメージから大きく離れ、新たな西武電車の標準を確立しました。Webページ「ペーパークラフト|西武鉄道キッズ」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:池袋線、新宿線、拝島線、西武有楽町線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線
ヒミツ情報:西武鉄道で初めて、前面に左右非対称の構造を採用している。


2017年に「S-TRAIN」用に開発された電車です。同年にグッドデザイン賞も受賞しました。座席をロングシートとクロスシートの切り替えが可能な0番代と、固定ロングシートの50番代があり、「S-TRAIN」には前者が使用され、「拝島ライナー」にも使われています。固定ロングシートの50番代は、急行や各駅停車に使われています。10号車には、ベビーカーや車椅子でも安心して過ごせる「パートナースペース」があります。Webページ「ペーパークラフト|西武鉄道キッズ」収録作品。
所有している鉄道会社:西武鉄道
走っている路線:池袋線、西武秩父線、新宿線、拝島線、東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線
ヒミツ情報:僕もたまに電気機関車に引っ張られてJR線を走行していくのを見た事がある。

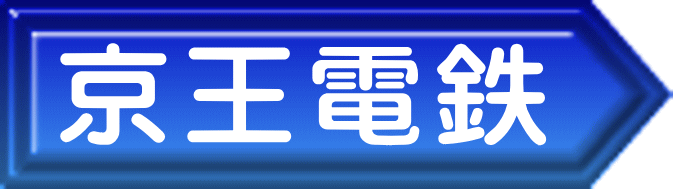
京王電鉄は、東京都南西部から神奈川県北部にかけて路線を持っています。東京と八王子に由来して、会社名も「京王」となっています。1998年、会社設立50年を機に、「京王帝都電鉄」から名称を改めました。そんな京王を知るキーワードは「地味にスゴイ」。地味だけど本当にスゴイ技術で、首都圏の人々の暮らしを支えています。

1992年から1999年にかけて製造された通勤型電車です。車体や車内のデザイン、走行用機械を一新したフルモデルチェンジ車両です。先頭車両の大きな窓が、目立ちますね。京王線用車両として初めて、VVVFインバータ制御を採用しました。京王電鉄線内の特急から各駅停車まで、色々な種別に使われます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京王電鉄
走っている路線:京王線、高尾線、相模原線


座席がロングシートとクロスシートの切り替え可能な優れものの5000系は、クロスシートの時には座席指定列車「京王ライナー」として走り、ロングシートの時には特急から各駅停車まで、通勤列車として走ります。また、照明に関しても朝の通勤時間帯には爽やかな色、夜の座席指定列車では落ち着いた暖色系の色に変える事が可能となっています。sustinaのカッコいいボディーが印象的。上手に丸みを付けて整えましょう。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京王電鉄
走っている路線:京王線、高尾線、相模原線
ヒミツ情報:「京王ライナー」の座席指定券を買えば、グリーティングカードがもらえる事もあるぞ。グリーティングカードのデザインは月ごとに異なるから、集めると楽しいかも!?

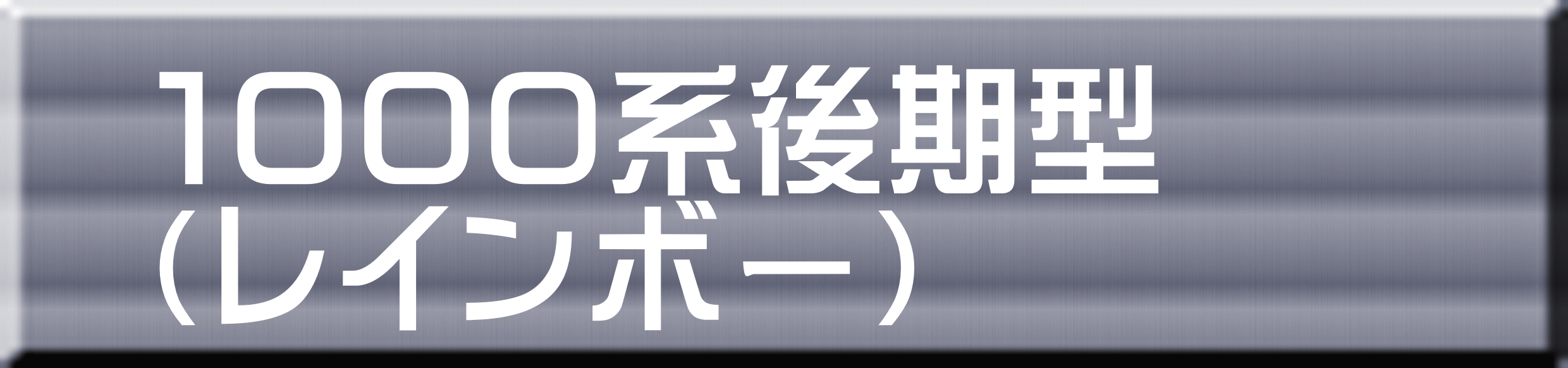
1996年に登場した井の頭線用の通勤型電車です。井の頭線では3000系以来、34年ぶりの新型車両で、井の頭線車両として初めて20m級車体とVVVFインバータ制御を採用しました。これは7色のラインが入った、特別な車両ですが、他にも7色の色の電車が走っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京王電鉄
走っている路線:井の頭線
ヒミツ情報:井の頭線で一番速い(停車駅が少ない)のは急行。


正式には、「京浜急行電鉄」といい、東京都港区から品川区、大田区、神奈川県川崎市や横浜市、更に三浦半島に路線を持っています。また、羽田空港から飛行機に乗るお客さんにとっては、大事な役割を果しています。

2002年に営業運転を開始し、1959年から走っていた1000形と同時に走っていた時期があり、区別する為、「新1000形」と呼ばれました。色々なバリエーションがあり、製造されたロッド毎に「20次車」」等と呼ばれます。これは恐らく最初に造られたグループの1~5次車かなと思います。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
所有している鉄道会社:京急電鉄
ヒミツ情報:2018年に営業運転を開始した17次車は、ステンレス車体。