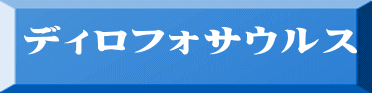
頭に薄い2枚のトサカを持っていました。トサカの役割には、メスへのアピール、仲間を見分けるなど諸説ありますが、空気をためる袋があり、膨らませることができたそうです。(僕も初めて知りました)いきなり大きく膨らませれば、敵もビックリすることでしょう。魚やトカゲなどの小動物を食べていました。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品。前足が長いので、しっかりと2本足で立つようにしてください。「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。
名前の意味:2つのトサカを持つトカゲ
大きさ:5~7m
食性:肉食
生息年代:ジュラ紀前期


前足が後ろ足よりも長く、首も長い恐竜で、首を持ち上げると高さだけでも16mに達しました。頭がコブのように盛り上がっていて、以前はここに鼻の穴があり、水中で暮らしていたとされていましたが、現在は陸上で暮らしていたと考えられています。また、頭の盛り上がりも、ただ単にそういう形だったということでしょう。化石はアメリカで見つかっていますが、アフリカのタンザニアでも見つかったことがありました。ところが、生息地がアメリカとアフリカで離れているため、アフリカで見つかった種は「ギラファティタン」という別の恐竜となったのです。
名前の意味:腕トカゲ
大きさ:25m
食性:植物食
生息年代:ジュラ紀後期

「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。魚の基本形から簡単に折れます。

「おりがみ恐竜博」収録作品。少し自立しにくいので、その辺調整してください。

Webページ「高井くんのおりがみ教室」収録作品。この後紹介するアパトサウルスに似ています。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。15cmで問題なく折れますが、首と前足辺りを綺麗に折るのが難しいかもしれません。

「チャレンジ力がつく 男の子のおりがみ」収録作品。簡単なブラキオサウルスで、15cm×15cmの折り紙でも作れます。足と背中はハサミで切って作ります。

三畳紀に生きていた恐竜のなかで、最初に発見されたのがこのテコドントサウルスです。発見後暫くは、別の爬虫類の化石だと思われていました。化石はイギリスで見つかりました。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ2」収録作品。
名前の意味:歯槽から生えた歯を持つトカゲ
大きさ:1~2.5m
食性:植物食
生息年代:三畳紀後期

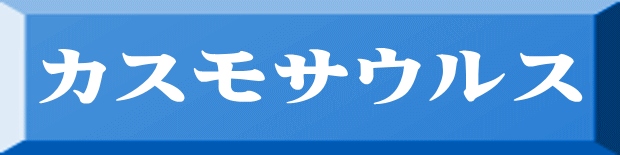
トリケラトプスと同じ角竜類で、大きなフリルを持っていました。フリルを上下左右に振るだけでも、正面からくる相手を脅すことができたのでしょう。軽量化のため、フリルに穴が開いていましたが、皮膚で覆われていました。先ほど紹介したトリケラトプスの途中から折ります。完成したら、フリルに模様を描いても、楽しい仕上がりになると思います。「新・おりがみランド 恐竜のおりがみ1」収録作品。
名前の意味:穴の開いているトカゲ
大きさ:6m
食性:植物食
生息年代:白亜紀後期

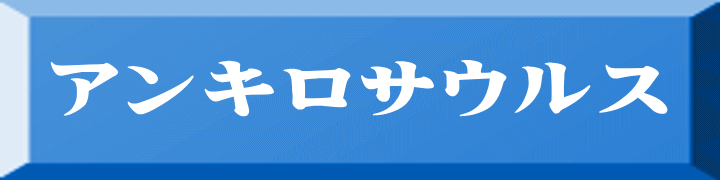
体中を鎧で覆った、鎧竜と呼ばれる恐竜の最大種です。尾の先にはハンマーがあり、これを襲ってきた肉食恐竜の足にぶつけたでしょう。まるで重戦車といった感じでした。骨盤が腸骨と坐骨からなることなど、鎧以外にも特殊性が見られます。
名前の意味:連結したトカゲ
大きさ:11m
食性:植物食
生息年代:白亜紀後期

「おりがみ恐竜博」収録作品。かなり難しい作品です。根気よく折っていってください。

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。沢山の折り筋をつけますので、しっかりと折り筋をつけましょう。同じ大きさの紙を2枚使います。つまり、「複合作品」です。

「2枚の紙でおろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。前の2つと比べ、割合簡単です。
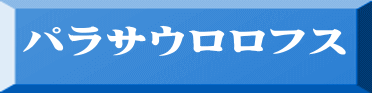
「カモノハシ恐竜」と呼ばれる鳥脚類の植物食恐竜。頭に角のようなトサカがありました。トサカの長さは1m近くになりますが、どんな風に使われていたかは諸説あり、中は空洞になっていて、鼻の穴とつながっていました。
名前の意味:サウロロフス(カモノハシ恐竜の1種)に似たトカゲ
大きさ:11m
食性:植物食
生息年代:白亜紀後期

「恐竜と古生物の折り紙」収録作品。パラサウロロフスは2本足でも4本足でも歩けたようなので、どっちで立たせても構いません。

「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。尻尾を写真のように曲げて自立するようにしてください。

「おりがみ恐竜博」収録作品。トサカはかぶせ折りで整えます。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。途中の折り方からは基準点が無いので本を見て折り進めましょう。

パラサウロロフスと同じカモノハシ恐竜の仲間ですが、体は一回り大きく、トサカの形もタバコのパイプって感じです。カモノハシ恐竜のトサカは、オスにもメスにもありましたが、オスのトサカの方が立派でした。カナダの古生物学者、ローリンス・モリス・ランベ氏が名前の由来で、ランベ氏はティラノサウルス科の肉食恐竜ゴルゴサウルス、鎧竜エウオプロケファルス、石頭の恐竜ステゴケラスなども命名しています。
名前の意味:ランベ(人名)のトカゲ
食性:植物食
大きさ:15m
生息年代:白亜紀後期

「1枚のかみでおる おりがみどきどき恐竜」収録作品。先ほどのパラサウロロフスの途中から折りますが、トサカ以外にも微妙に折り方が違う箇所があります。

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。これもパラサウロロフスの途中から折ります。

フタバスズキリュウは恐竜ではなく、首長竜という海の爬虫類で、化石は1968年に福島県の地層から高校生によって発見されました。近くからサメの歯が大量に出土していますが、サメに襲われたのか、死骸をサメがかじったのか、真相は迷宮入り。「映画ドラえもん のび太の恐竜」で「ピー助」として登場したのは、このフタバスズキリュウ。正式名称は、「フタバサウルス・スズキイ」といいます。「2枚のかみで折ろう 恐竜おりがみ教室」収録作品。
名前の意味:双葉層(福島県の地層)のトカゲ
大きさ:7m
食性:肉食(魚・イカ)
生息年代:白亜紀後期


中国で見つかった、首の長い大型の植物食恐竜です。最初見つかった時には、竜骨、つまり薬になる竜の骨と思われていたそうです。竜が天に帰ろうとしたら天国の門が開かず、そのまま山で死んでしまったという言い伝えがあるのも、中国でマメンチサウルスをはじめとした恐竜の化石が見つかっているからでしょう。首の骨は19個もあり、その1個1個も長いつくりになっていたようです。
名前の意味:馬門渓(中国の地名)のトカゲ
大きさ:22m
食性:植物食
生息年代:ジュラ紀後期

「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。体に丸みをつけると、迫力のある造形になります。

「あそべる たのしい 男の子のおりがみ」収録作品。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。
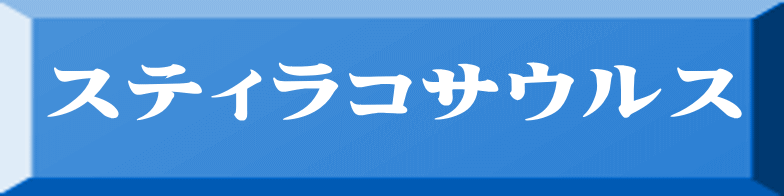
トリケラトプスよりも小柄な角竜類ですが、鼻の上の角は長く、フリルの6本の角も長く伸びていました。この角は、敵を威嚇するのに役立ったようです。
名前の意味:とげトカゲ
大きさ:5.5m
食性:植物食
生息年代:白亜紀後期

「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」収録作品。フリルの先端をつまみ折りすると、6本角に見えるので、挑戦してみてください。僕オススメの仕上げです。

「あそべる たのしい 男の子のおりがみ」収録作品。意外と複雑な折り方があるかもしれません。諦めずに何回も挑みかかっていってください。

「新世代 至高のおりがみ」収録作品。かなり難易度の高い作品です。大きな折り紙を使って折ってください。かなり重厚感のあるスティラコサウルスが出来上がります。
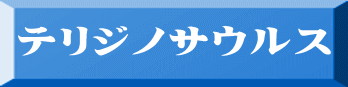
モンゴルやカザフスタンで発見されている、植物食の獣脚類です。前足と肩の骨しか見つかっておらず、謎の多い恐竜で、2.5mの前足に90cmもの長いカギ爪を持つ変わり者。ですが、このカギ爪が何の役に立つのかは、未だに分かっていませんが、「植物の枝を手繰り寄せるのに使った」とか、「蟻塚を壊してアリを食べるのに使った」等、色々と考えられます。また、タルのような大きな胴体に、大きな消化管を収めていました。正方形の折り紙を半分に切って作ります。「おりがみランド+ 恐竜のおりがみ」収録作品。
名前の意味:大鎌トカゲ
大きさ:8~11m
食性:植物食
生息年代:白亜紀後期



