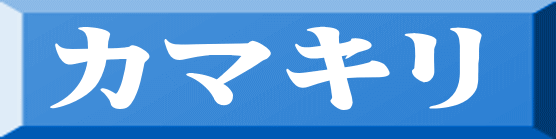
三角形の頭部に大きく前を向いた複眼、そして何といっても特徴的な鎌状の前肢を持つ、肉食性の昆虫です。草むらや枯れ葉等に身を潜め、近くにやって来た虫を鎌で捕まえ、発達した鋭い顎でかじって食べます。花に集まる虫や草むらに棲む虫の他にも、カエルやトカゲすらも襲って食べる事もあります。交尾中にメスがオスを食べる事も知られていますが、それは自分より小さくて動くものに飛びつくという習性からきているとされているものの、詳しくはまだ分かっていません。海外には花にそっくりなハナカマキリ、枯れ葉そっくりなカレハカマキリの仲間、枝になりすますオオカレエダカマキリといった、色々な色や形状で擬態する種が多くいます。

「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。鎌の前肢はかなり厚ぼったくなります。同じ大きさの折り紙を2枚使う複合作品です。前半分の糊付けする箇所はかなり小さいので、しっかりと接着しましょう。

「おりがみランド 虫のおりがみ」収録作品。顔は胴体の半分くらいの紙で折るといいでしょう。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。こんな風に翅に丸みを持たせて立体感を出すと、なかなかいい感じに仕上がります。

「「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。半分に折る際破れないように気をつけてください。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。1枚の折り紙を切り分けて作るので、作りやすいカマキリになっています。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。同じ大きさの紙を2枚使う複合作品です。パーツは2枚とも鶴の基本形を使って折ります。必要に応じて糊付けをするといいでしょう。顔の部分に紙の裏側が出るので、裏表同じ色の紙で折るのもいいでしょう。

「チャレンジ力がつく 男の子のおりがみ」収録作品。鎌と肢はハサミを使って切り分けます。

腹部の先端に尾角が変化したハサミを持ち、獲物を捕らえたり敵と戦うのに使います。動物の死骸や腐った植物、それらに集まる小さな虫を食べます。ハサミの形状は、種類により違いますが、同じ種類でも形状が違う事があります。メスが幼虫の世話をし、最終的には幼虫に自らの体を食べさせる種類もいます。ハサミムシ(ハマベハサミムシ)やオオハサミムシのような、世界共通種もいます。背面は半分に少し折って立体的にします。肢は背面の前の方にくっつけます。「甲虫の仲間」で紹介しているカブトムシ、クワガタ、コーカサスオオカブト、テントウムシにも言える事ですが、肢の部分はスティック糊で貼り付けて、仕上げに木工用ボンドで強化するといいかもしれません。「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。


体は平たい卵型で、隙間に入り込むのに適しています。頭部は前胸に隠れて、上からは見えなくなっています。クロゴキブリやチャバネゴキブリ、ワモンゴキブリ等、民家等に棲みつく害虫として嫌われていますが、多くは森で枯れ葉等を食べる分解者としての役割を担っています。恐竜が栄えていた時代よりもずっと古い、3億年前からいたといわれており、「生きた化石」と呼ばれています。体が油でテカテカ黒光りする為「アブラムシ」とも呼ばれますが、カメムシ目アブラムシ上科のアブラムシとはまた異なります。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。触角は折る向きに注意しましょう。割と折りやすいゴキブリです。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。お尻の辺りは展示に合わせて糊付けする方がいいかもしれません。

日本ではミンミンゼミやアブラゼミ、ニイニイゼミ、クマゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシ等、色々な種類が見られる、夏の昆虫の代表的なものの1つです。オスは腹部にある発音器官を使って鳴き、メスを誘います。ストローのような口を木の幹に刺して、木の汁を吸っています。卵は枯れ枝に産みつけられ、そこから孵った幼虫は地面に潜り、木の根の汁を吸って育ちます。幼虫期間は種類によって様々ですが、大体2~3年程度のものが多いです。因みにアメリカにいる17年ゼミは、幼虫期間が17年な為か、17年に1度の割合で大発生するそうです。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。僕は15cm角の折り紙で問題なく折れます。腹部の折りが細かいと思うので、慣れないという方は少し大きめの折り紙を使うといいでしょう。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。広げて被せる折り方は、紙が破けないように注意しましょう。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。前の2つと比べると簡単なセミです。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。1枚の紙を2枚に切り分けると、肢も4本だけではありますが折り出す事が出来るんですね。

「決定版!日本のおりがみ12か月」収録作品。今までの作品と異なり、翅の部分にも色の面が出ています。厚ぼったくなりやすいので、しっかりと折りましょう。



