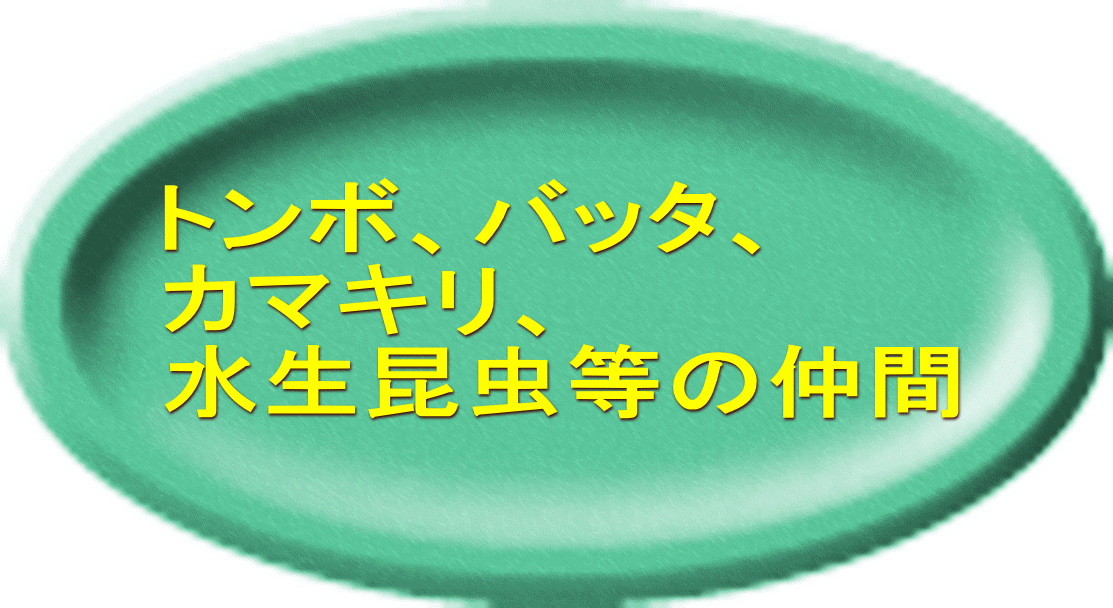
このエリアでは、トンボやバッタ、カマキリ、セミといった、蛹の時期が無い「不完全変態」の昆虫と、一生の殆どを水中で暮らす、いわゆる「水生昆虫」を紹介します。因みに甲虫やチョウやガ、ハチやアリやハエ、アブといった昆虫達は、蛹の時期がある「完全変態」の昆虫です。ゲンゴロウは甲虫の仲間なので完全変態なのですが、水生昆虫の一つなのでこのエリアで紹介します。

細長い胴体に大きな複眼、発達した長い翅を持つ飛行の得意な昆虫です。高速で飛ぶ事が出来る他、空中でその場に留まるホバリングにバックもお手の物。これ程に高い飛行技術があるのは、4枚の翅を別々に動かすことが出来るから。その巧みな飛行術を活かし、飛んでいる昆虫を捕らえると、鋭く発達した大顎でかじります。カワトンボやイトトンボ、アキアカネ、シオカラトンボ、オニヤンマにギンヤンマ等、色々な種類がいます。幼虫はヤゴで水中生活を行い、下唇を伸ばして水中の小動物を捕まえて食べます。ヤゴには鰓があり、水中で呼吸する事が可能です。ヤゴは種類により、田んぼやため池からきれいな川まで、棲んでいる水域が違います。ムカシヤンマのヤゴは湿ったコケの中に穴を掘り、半水生生活を行っているそうです。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。割と折りやすいトンボです。翅は実際は2枚なのですが、ちゃんと4枚に見えますね。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。やや半開きに思えますが、上から見てトンボらしく見えるようにしてください。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。1枚の紙を長方形に切って、胴体と翅を折ってから組み立てます。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。こちらは1つ前の作品と異なり、紙を三角形に切り分けて作ります。

アカトンボという種類のトンボはいませんが、一般にはアキアカネやナツアカネ等、トンボ目トンボ科アカネ属(アカトンボ属)のトンボをそう呼んでいます。但しそれ以外でもハッチョウトンボやショウジョウトンボ、ベニイトトンボのように体色が赤っぽいトンボをアカトンボといいます。なお、狭義に「アカトンボ」というとアキアカネの事を指します。1枚の折り紙を三角形に切り分けて作ります。基本的な折り方は途中まで同じですが、折り方を変えるだけで前半分と後ろ半分を作る事が出来ます。「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。


大きく飛び跳ねるのに適した、長くて力強い、発達した後ろ肢を持つ昆虫です。日本にはトノサマバッタやショウリョウバッタ、クルマバッタ等の種類が暮らしています。草むらで暮らし、主に原っぱや河原に生える草を食べています。イネ科の細長い葉の植物を好む種類が多いです。トノサマバッタは、食べ物の植物が減り生息密度が高くなったりすると、翅が大きくなり、長距離飛行に適した体つきになりますが、アフリカに暮らすサバクトビバッタは毎年のように大発生を繰り返し、農作物被害も報告されています。

「あそべる たのしい 男の子のおりがみ」収録作品。肢は胴体の半分の大きさの紙で折ります。例えば、胴体を15cm角で折った場合、肢は7.5cm角といった具合です。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。1枚で折るバッタです。厚ぼったくなるので、ずれないようにしっかり折りましょう。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。1枚の折り紙を2枚に切り分けて作るので、割とシンプルに出来上がります。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。「チョウ・ガの仲間」エリアで登場したチョウの途中の折り方を使って折ります。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。「甲虫の仲間」エリアに収録したテナガコガネの途中から折ります。僕は15cmの普通の折り紙で折りましたが、かなり難しい作品なので、大きな紙で折るのをオススメします。

日本でも身近に見られるショウリョウバッタ。とんがり帽子をかぶったような頭が、最大の特徴です。メスは日本のバッタの中でひときわ大きく、80mm~90mm位あります。オスは飛ぶときに「キチキチキチ」という音を立てる為、別名「キチキチバッタ」とも呼ばれる他、後ろ肢を揃えて持つとぺコンペコンと体を縦に振る事から、「コメツキバッタ」とも呼ばれます。最初は綺麗に折れないかもしれませんが、練習あるのみ。大きめの紙も使って、図をよく見て折りましょう。「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。

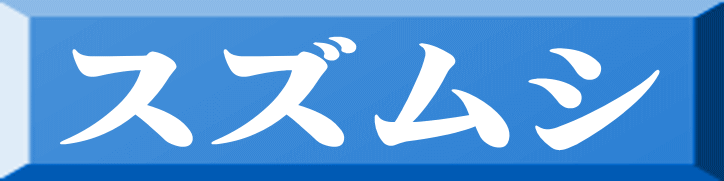
秋の鳴く虫としてもよく知られているスズムシ。オスは翅をこすり、リーン・リーンと、まるで鈴を転がすかのような美しい音色で鳴き、メスを誘います。森林縁またはススキ等の多く生える暗い茂みに潜んでいますが、自然の豊かな農村等では、田畑の脇の草むらで大きな石やコンクリート片等をひっくり返すと、多数の個体が潜んでいたりします。エンマコオロギのような、他の地表性コオロギ類に比べ肢は比較的長くて細い為、穴は掘らず物陰に隠れている事が多いようです。この作品は、鳴いているスズムシをイメージしています。上半身の中割り折り箇所は、下半身をくっつける所です。しっかりと糊付けしましょう。僕は実施していませんが、紙を細く切ったものや針金の曲げたもの等を触角として付けると、更に本物らしくなってきますよ。「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。



