
日本のクワガタムシで、クヌギやコナラの樹液に集まります。大型のオスは、水牛の角のように湾曲した大顎を持ち、中に細かな歯があり、鋸のようになっているのでこの名がついたのでしょう。昼間も活動していて、ミヤマクワガタ同様僕の近所でも最近見かけるようになったクワガタの1つです。

「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。大顎の仕上げが難しいです。折り図をよく見て折った方がいいかもしれません。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。1つ前のノコギリクワガタより難易度をぐっと下げています。慣れてきたら大顎を湾曲させたりして、本物らしくしてみましょう。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。1枚の折り紙を2枚に切り分けるので、折りやすくなります。最後の仕上げとして大顎を少しつまんでおくとカッコよくなりますよ。

日本を代表するクワガタムシですが、僕の近所では見かけません。体は黒くて平たく、木の隙間に入るのに適しています。大きな体ですが大変臆病な性格で、わずかな物音がしただけで隠れてしまう上、飛ぶ事も滅多にありません。ノコギリクワガタやミヤマクワガタと違い、成虫で越冬して2年以上生きる事もあります。

「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。大顎を整えてどっしりと重厚感あるクワガタを作りましょう。但し、大顎の根元が破れやすいので気をつけて下さい。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。1つ前のオオクワガタより難易度は下げています。
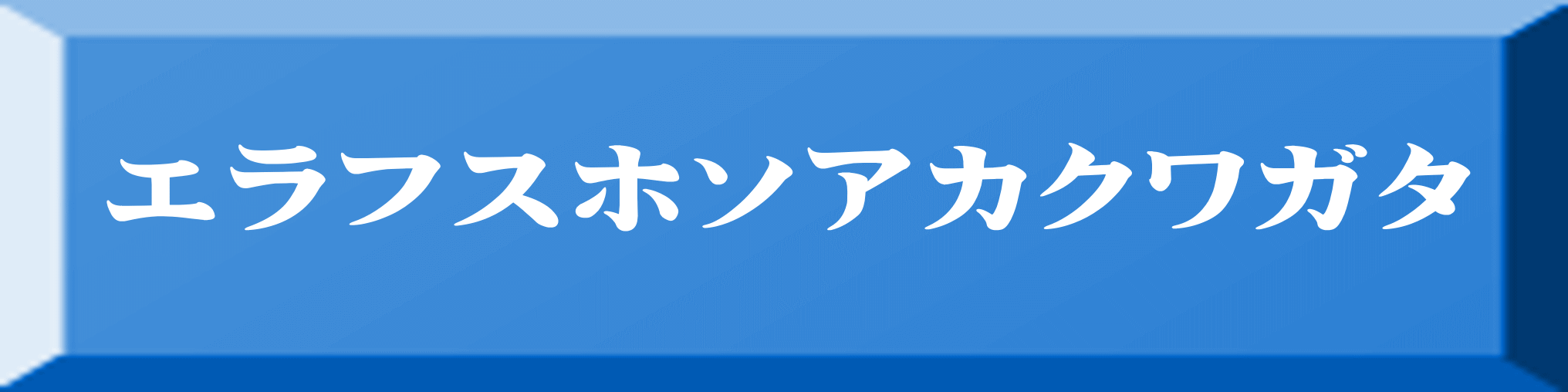
エラフスホソアカクワガタはホソアカクワガタの仲間。インドネシアのスマトラ島に生息し、オスは長くて立派な大顎を持っています。ホソアカクワガタの仲間には、体よりも長い大顎を持つ種類もいて、このエラフスホソアカはホソアカクワガタの最大種になります。基本的に体は青みを帯びた緑色で、大顎の根元にオレンジ色の斑紋がありますが、赤褐色の個体もいるようです。 大顎がシカの角の様に見える為、「シカ(若しくはシカの角)」を意味する「エラフス」と付けられました。大型のクワガタムシですが、意外と大人しい性格です。でも、ホソアカの挟む力を侮るなかれ。長い大顎の挟む力は意外と強く、指を挟まれたら出血する事もあるようです。大顎の根元が破れやすくなるので、気をつけて折りましょう。大顎を長く見せる為にも、工夫して下さいね。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。

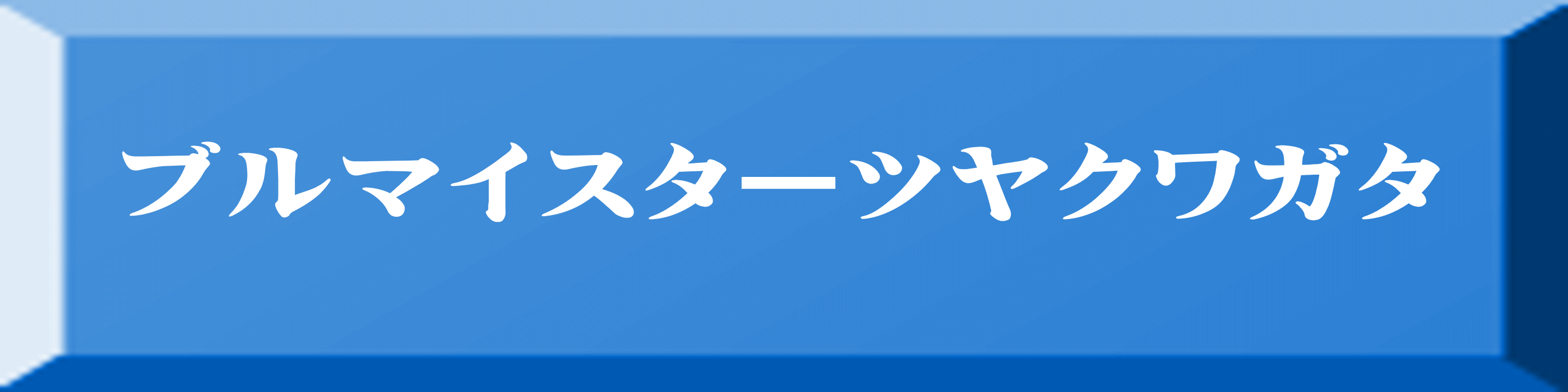
インド南部に生息するクワガタムシ。体長は最大で109mmに成長するものもいて、ツヤクワガタの仲間ではインターメディアツヤクワガタに並ぶ最大種で、色付きクワガタの最大種でもあります。野生における生態は詳しくは分かっていませんが、ツヤクワガタの仲間は、マルバネクワガタの仲間と近縁関係にあるとされています。厚ぼったく難解な作品です。ヘラクレスオオカブト同様、紙の裏面を表に出す「インサイドアウト」を使用しています。翅の模様は折り紙を貼って出していますが、金色折り紙を使うと折りやすいのではと僕は見ています。他のクワガタと違う折り方をしています。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。

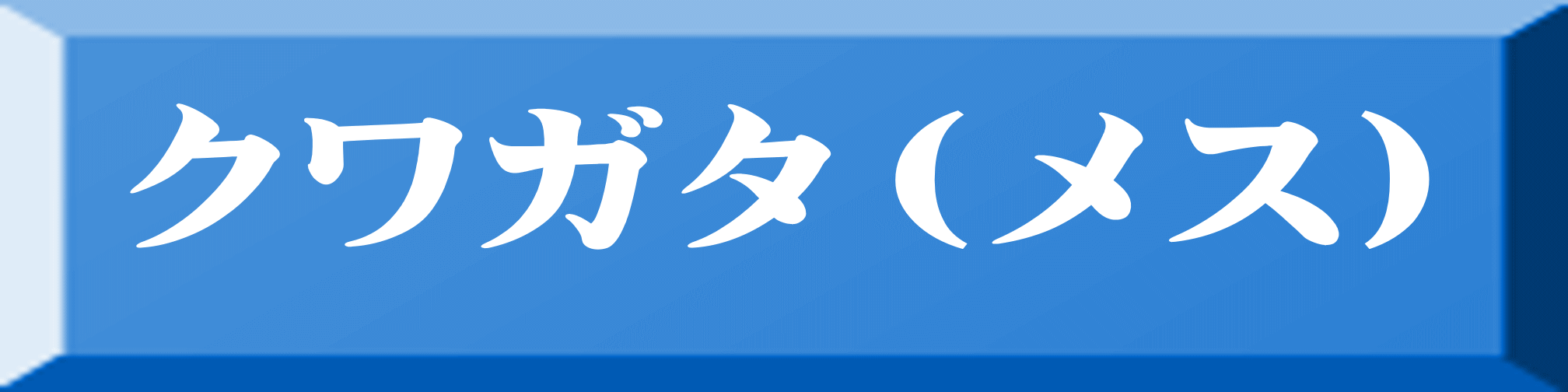
クワガタムシのメスは、多くの種類でオスに比べると体は小さく、大顎もあまり発達していません。ですが短い大顎でも強力で、「足切り」という別名通り、他の虫の足を嚙み切ってしまう事もある、油断のならない奴です。ミヤマクワガタの折り方を使って折ります。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。

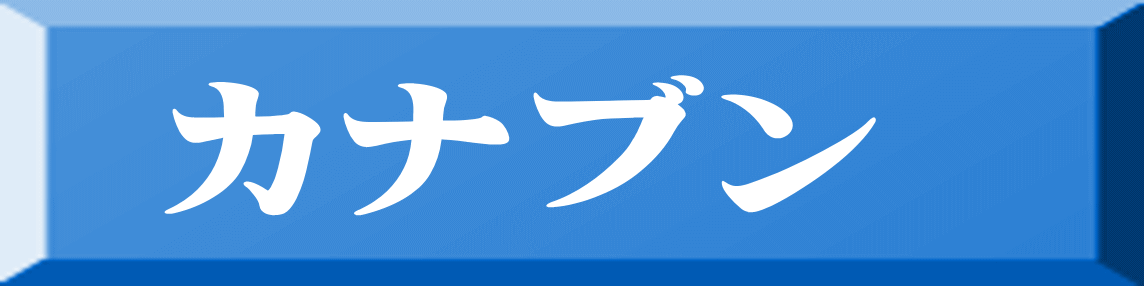
カナブンはハナムグリと呼ばれるコガネムシ科の昆虫の1種で、よく樹液に集まっているのが見られます。銅色のカナブンの他にも、緑色だったり黒っぽかったりするものもいたりしますが、それはカナブンの仲間のアオカナブンだったりクロカナブンだったりします。前翅を浮かせて、後翅だけを羽ばたかせてブンブン飛び回ります。折り鶴を組み合わせて作るカナブンです。頭部だけは半分のサイズの紙で作ります。なお、前に紹介したクワガタとミヤマクワガタ、カブトムシは、このカナブンと共通の折り方を使っています。「おりがみランド 虫のおりがみ」収録作品。

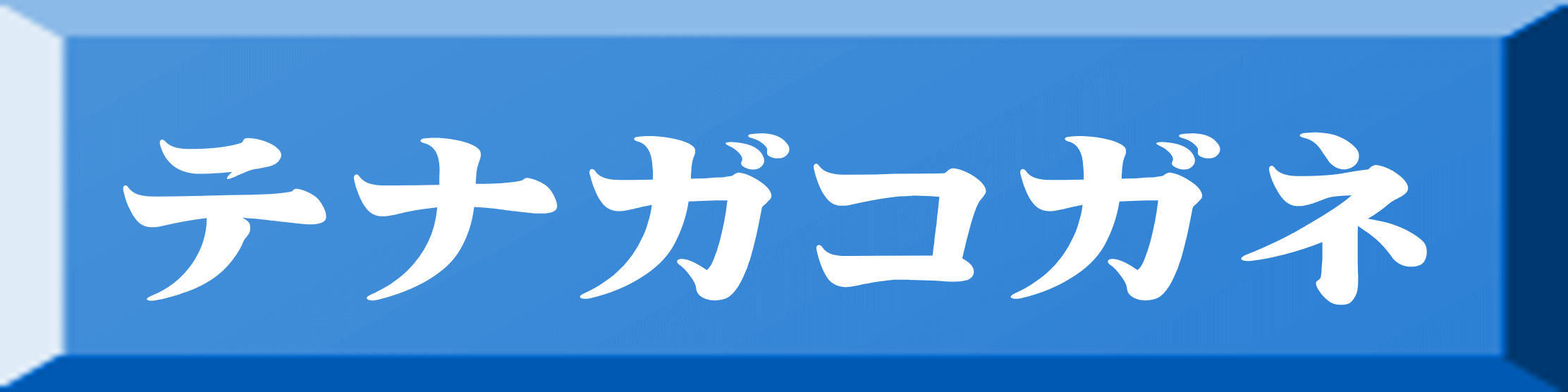
アジアの熱帯地域に暮らす大型コガネムシの仲間で、オスは名前の通り前肢が長く発達します。マレーテナガコガネやタイワンテナガコガネ等の種類がおり、日本には沖縄島にヤンバルテナガコガネが暮らしています。ヤンバルテナガコガネは日本最大の甲虫で、国指定の天然記念物に指定されています。ヤンバルテナガコガネに限らず、大体の種類が世界的に保護されています。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。僕が初めて折ったテナガコガネの折り方です。中肢はつまみ折りで細くします。綺麗に折れたら感激しますよ。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。この作品では15cm角のアルミホイル折り紙を使用しました。アルミホイル折り紙の他、細かい所があると思うので大きな紙で折るのもお勧めします。
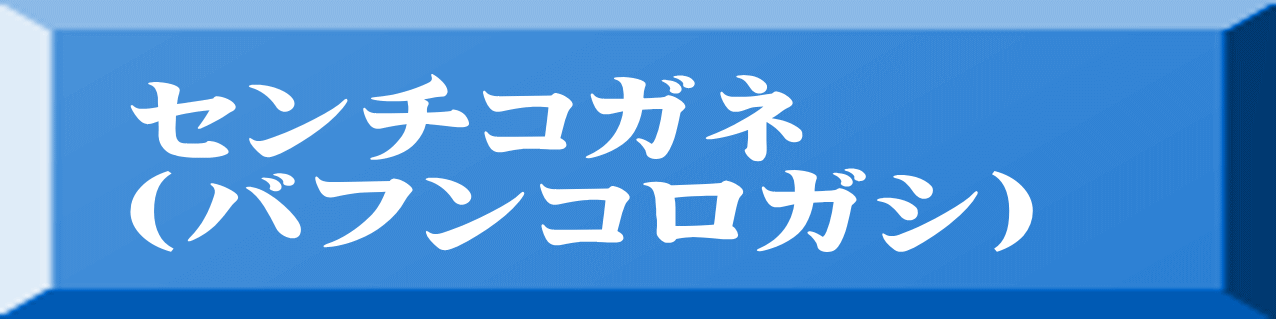
センチコガネはコガネムシの仲間ですが、幼虫も成虫も動物の糞を主食としています。そういったコガネムシの仲間は「糞虫」とよばれ、センチコガネの他にもダイコクコガネやスカラベことタマオシコガネの仲間等、かなり多くの種類がいます。フンボールは茶色の折り紙を丸めて、セロテープで貼り合わせて作りました。「おりがみランド 虫のおりがみ」収録作品。

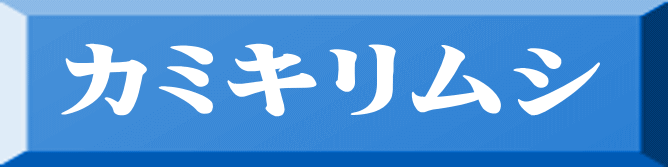
硬い前翅を持つ細長い体と長い触角を持つ甲虫で、鋭い大顎を持っています。幼虫は樹木や枯れ木の中に棲み、木の内部を食べて育ちます。成虫は生きた木の皮をかじるものもいますが、他に花の蜜に集まるものや葉っぱをかじるものもいます。大顎が鋭く髪の毛の束も簡単に切れてしまうので「髪切り虫」だとか、噛み切るので「噛み切り虫」だとか、いずれにしても大顎の鋭さが由来になっているようです。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。長い触角は、最終的に折りづらくなってくると思います。曲げてほどけないようにしましょう。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。1枚の折り紙を三角形に切り分けて作るので、至ってシンプルです。

丸っこい体をした甲虫の仲間です。背中にある模様は種類により数が異なり、それが名前の由来になっている種類が多くいます。餌はアブラムシやカイガラムシ等を食べる肉食性のもの、植物の葉っぱを食べるもの、菌を食べるものの3種類に分ける事が出来ます。背中の模様は図鑑をよく見てペンで描いてみましょう。

「本物みたいな虫のおりがみ図鑑」収録作品。2枚の紙で折る複合作品です。同じ大きさの紙でも問題なく作れますが、胴体と肢の紙の比率を4対5にして折ると肢の長さのバランスがいいです。

「決定版!日本のおりがみ12か月」収録作品。1枚で折るテントウムシです。これは15cm角の紙で折っていますが、少し小さ目の紙で折ったら可愛いかなと感じました。



