
アクティオンゾウカブトは、南米アマゾン川流域に多く見られるゾウカブトの仲間で、艶消しの漆黒ボディーに、ゾウの鼻のような頭角、前胸両横から伸びる太い角が特徴です。ペルー、ブラジル等南アメリカ大陸に分布するマルスゾウカブトと共に、体毛が無いゾウカブトの仲間では最大の体格を誇る種類で、オスは最大12cmにまでなります。アクティオンというのは、ギリシャ神話で鹿に変えられてしまった巨人の名に由来します。近年は分類が見直され、南アメリカ大陸東側の個体群は従来通りアクティオンゾウカブトとし、ペルーやエクアドル等西側の個体群は「レックスゾウカブト」として亜種扱いする事となりました。その重量感と巨体故、現地では、光につられて飛んできたアクティオンに体当たりされた電球や窓ガラスが割れる事故も相次いでいるようです。先程紹介したエレファス・ゾウカブトと、この後紹介するカブトムシの多くは、このカブトムシの折り方を使って折っていますので、まずはこのアクティオンゾウカブトの折り方をしっかりマスターしましょう。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。


アフリカには大型カブトムシはあまり多く見られませんが、ケンタウルスオオカブトはアフリカ最大のカブトムシの仲間です。アフリカではハナムグリの仲間がカブトムシに替わって繁栄しています。ヘクソドンの仲間等、アフリカにいるカブトムシは、ほとんどが小型の種類で角も目立たないものが多いですが、このケンタウルスオオカブトはアフリカ産カブトムシのなかでもカブトムシらしく立派な角を持っており、頭角の先端もフック状に曲がっているのが特徴です。このように立派な体格のケンタウルスオオカブトですが、組み合わせると戦う事はあるものの、あまり好戦的でケンカが得意というわけではなく、途中で戦意喪失する事もあるようです。折り筋をいっぱいつけ、その折り筋で沈め折りします。折り筋をしっかりつけましょう。肢は先に紹介したアクティオンゾウカブトと同じ折り方です。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。

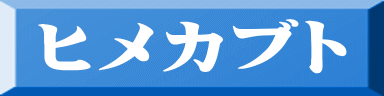
日本のカブトムシとほぼ分類学上近縁の中型カブトムシで、カブトムシの中でも極めて繁栄している種類です。ヒメカブトの分布域は東南アジアからオーストラリア、ニューギニアまでと幅広く、地域によって角の長さ等に差が見られ、特にニューギニアの東部の島々に生息するヒメカブトは胸角が長くなります。闘争心が強く、タイのチェンマイという都市では、ヒメカブトの相撲「メンクワン」が行われる程です。優勝者には賞金がある他、そのヒメカブトは高値で取引される為盛り上がるそうです。威嚇する時に「キューキュー」と威嚇音を発する事から、「鳴きカブト」という異名でも呼ばれています。ケンタウルスオオカブトと途中までは一緒で、肢はアクティオンゾウカブトと共通の折り方になります。頭角が破れないように気をつけましょう。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。


ゴホンヅノカブトは、頭部に1本の長い角、胸部に4本もの角という、合計5本の角を持つカブトムシです。竹林に生息し、タケの新芽の汁を吸って暮らしています。角が5本もあって、いかにも強そうな見た目ですが、性格は大人しく、好戦的では無いようです。主な分布はインドから中国にかけてで、パプアニューギニアには近縁種で「サンボンヅノカブト」というのがいます。生きている時の前翅は美しいクリーム色ですが、この色は死んでしまうと濃くなって褐色となってしまいます。昆虫図鑑に出ているゴホンヅノカブトの前翅が濃いオレンジがかった色をしているのはその為です。鞘羽の色はメスも同じで、竹やぶでの保護色になっていると考えられています。

「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。前翅に紙の裏面を出す「インサイドアウト」という技法を使います。紙を重ねて折る際は厚ぼったくなるので注意しましょう。他のカブトムシと少し違う折り方がいくつか出てきます。

「おりがみランド+ 昆虫のおりがみ」収録作品。肢の仕上げは先に紹介したネプチューンオオカブトと共通です。大きな紙で折る事をお勧めします。写真の作品は大きな和紙の折り紙で作りました。
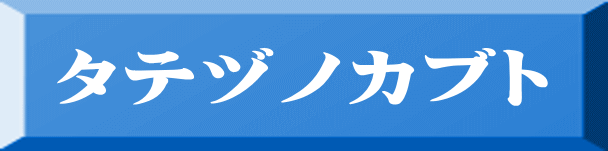
中南米に分布するカブトムシで、前肢が異様に長いのが特徴です。竹林に棲み、竹の樹液を吸って暮らしています。竹は足場が悪い為か、オス同士戦う時は長い前肢を振り回しますが、それでも勝負がつかないと角も使って相手のバランスを崩す事もあるようです。ノコギリタテヅノカブト(ゴロファ・ポルテリ)やクラビゲールタテヅノカブト(ゴロファ・クラビゲール)、ピサロタテヅノカブト等の種類がいます。普通の折り紙用紙だと紙が重なって破れやすいので、薄手の紙若しくは写真の作品のようにアルミホイル折り紙で折る方がいいかもしれません。肢先にもこだわって仕上げたいカブトムシです。「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。


カブトムシのメスはオスよりも小さく、角はありませんが、前肢のトゲがよく発達していて、腐葉土の中に潜り込むのに適しています。オスもメスも夜行性で、昼間は木の根元等で休んでいて、夜になると樹液を吸いに出てきます。因みに、カブトムシの仲間の中には、オスにも角が無いものや、サイカブトの仲間のようにメスも角を持つものもいます。

「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。途中、先に紹介したゴホンヅノカブトと同じような折り方が出てきます。最後に体を少し折って丸みをつけましょう。

「折り鶴から折る おりがみ昆虫館」収録作品。頭部の仕上げがややこしいと思います。折り図をよく見て仕上げましょう。

「2枚のかみで折ろう 昆虫おりがみ教室」収録作品。先ほどの2つの作品と違い、1枚の折り紙を2枚に切り分けて作るので、わりと作りやすいメスのカブトムシです。
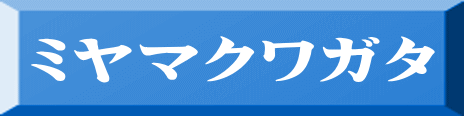
日本のクワガタムシで、オスは頭部の両側が出っ張っています。大型のオス程この出っ張りは目立ち、小型のオスではあまり目立ちません。ミヤマとは「深山」の事で、名前通り標高の高い山間部に多く見られます。挟む力はとても強く、大型の個体がカブトムシと戦えば体に穴を開けたり、人間でも猛烈に締め付けられると出血どころか爪部分を貫通してしまう事もあるといいます。台湾のタカサゴミヤマクワガタは、ミヤマクワガタの亜種の1つです。


「1枚のかみで折る おりがみ世界のカブトムシ・クワガタ」収録作品。この後紹介するノコギリクワガタやオオクワガタ等も、ミヤマクワガタと同じ折り方を使いますので、しっかり覚えておいて下さい。

「1枚のかみで折る おりがみむしむし昆虫園」収録作品。先程の作品より難易度は下げてますが、易しくはありません。大顎の形は、前掲書の写真等をよく見て整えましょう。前に紹介したクワガタの途中から折ります。

「おりがみランド 虫のおりがみ」収録作品。前に紹介したクワガタのパーツを使い、頭部の折り方を変えて折ります。胴体の仕上げ方も微妙に変えてます。



