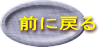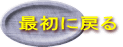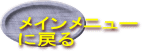水面をスケートするようにスイスイ滑るアメンボ。よく似た仲間がオオアメンボ、ヒメアメンボ等、10種類近くおり、見分けるのも至難の業。中肢と後肢が異常に長く、肢には細かい毛がビッシリ生えています。更に、肢からは水をはじく油が出ていて、この為にアメンボは水に沈まずに浮いていられるのです。水面を縦横無尽に滑りまわり、水に落ちて溺れている昆虫を襲い、体液を吸います。捕まえると、飴のような甘い匂いを出すので、「アメンボ」と名付けられました。作品を水色の画用紙の上に載せてみたら、水面に浮かぶアメンボらしくなりました。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:カメムシ目アメンボ科
体長:11~16mm
成虫が見られる時期:3~11月
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:多くの種類は飛ぶ事が出来る。


赤トンボの1種です。赤トンボというのは種名では無く、一般にアキアカネやこのミヤマアカネ等のアカネ属のトンボを指します。「ヤグルマトンボ」「カザグルマトンボ」とも呼ばれます。翅に褐色の太い帯があり、これで他の赤トンボと見分けられます。羽化後は羽化水域近くの、ススキやアシが群生したやや丈の高い草むらに移動し、体が成熟するまでそこで摂食活動を行っています。ヨーロッパから中国東北部に見られるヨーロッパミヤマアカネは、日本のミヤマアカネの原名亜種です。ヨーロッパミヤマアカネは、日本産ミヤマアカネに比べやや小型で、翅にある褐色帯も日本産に比べ幅が狭いです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:トンボ目トンボ科
体長:36mm前後
成虫が見られる時期:6~12月
分布:日本では北海道~九州、ヨーロッパ~中国東北部に原名亜種が分布。
ヒミツ情報:マユタテアカネとの種間雑種も報告されている。


黒い翅がお洒落なカワトンボの仲間。「ホソホソトンボ」とも呼ばれ、チョウのようにひらひらと舞っています。その際に、翅が「パタタタ・・・・・」と小さな音を立てます。幼虫は流れが緩やかな川に見られます。とまって翅を休める際も、翅を立てた状態で、4枚の翅を重ねていて、これもまたチョウにそっくりです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:トンボ目カワトンボ科
体長:60mm前後
成虫が見られる時期:5~10月
分布:東アジア(日本、朝鮮半島、中国)、ロシア、北米。日本では本州、四国、九州、種子島、屋久島で見られる。
ヒミツ情報:奄美大島、徳之島、沖縄本島にはよく似た「リュウキュウハグロトンボ」がいるが、リュウキュウハグロトンボは「タイワンハグロトンボ」という種類の亜種であり、属のレベルで異なる。


前に登場したモンシロチョウが含まれるシロチョウ科では、最大の種類です。林の縁の高い所を、跳ねるように力強く飛びます。幼虫はギョボクという植物を食べて育ちます。翅や幼虫の体液に、イモガイ(毒針を刺して魚等を捕らえる肉食の巻き貝。人間が刺されて死亡した種類もいる)に近い猛毒の成分が、オーストラリアの研究チームによって発見されました。天敵からの防衛に毒を利用しているようです。チョウの仲間としては珍しく、ほぼ1年中見る事が出来ます。ハイビスカスやブッソウゲ、ブーゲンビリアの蜜を吸っています。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:チョウ目シロチョウ科
前翅長:40~55mm
成虫が見られる時期:北限近くの生息場所では3~11月
分布:日本では九州(南部)、南西諸島。国外では東洋区に見られる。
ヒミツ情報:「幸せを呼ぶチョウ」ともいわれ、沖縄県那覇市の国際通り沖縄山形屋という百貨店に、大きなツマベニチョウの飾りがあり、長らくシンボル的に愛されてきたが、閉店等もあって、現在は撤去された。また、沖縄が本土に復帰するまでは、日本の昆虫屋の憧れのチョウであり、佐多岬には多くの虫屋が集まり、手に手に捕虫網を振り回していたという。

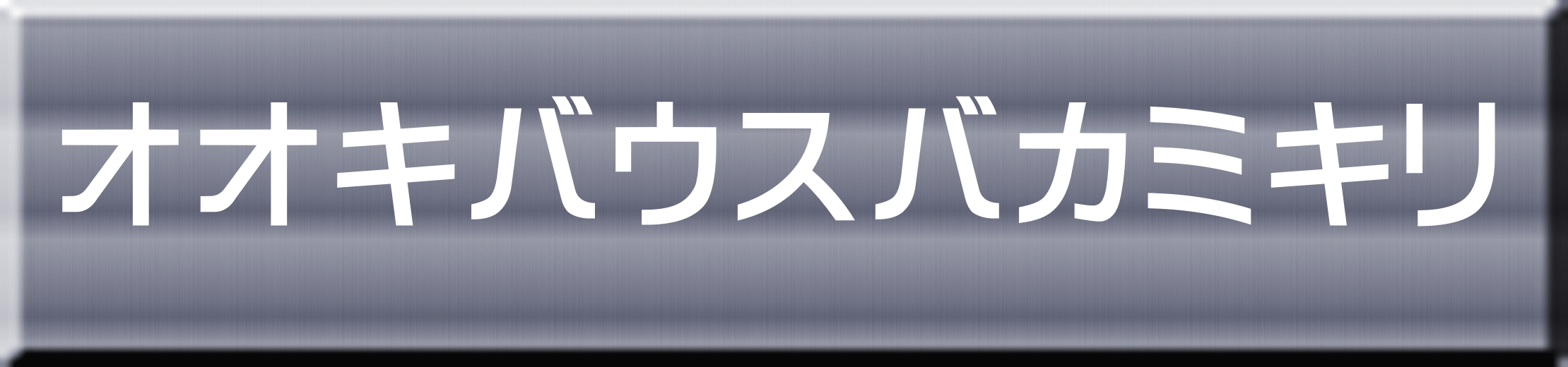
まるでクワガタのような大顎を持つ、強面のカミキリムシ。翅に不思議な模様を持っています。この大顎をどう使うのかは知りませんが、顎の力は枯れ枝が切れ落ちる程強力です。また、メスの大顎も相当に強力で、直径2cmの木の枝を噛み切り、そこに卵を産むらしいです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目カミキリムシ科
体長:150mm
分布:アマゾン
ヒミツ情報:初期の飛行機の設計家は、このカミキリムシの構造をヒントに設計したといわれる。

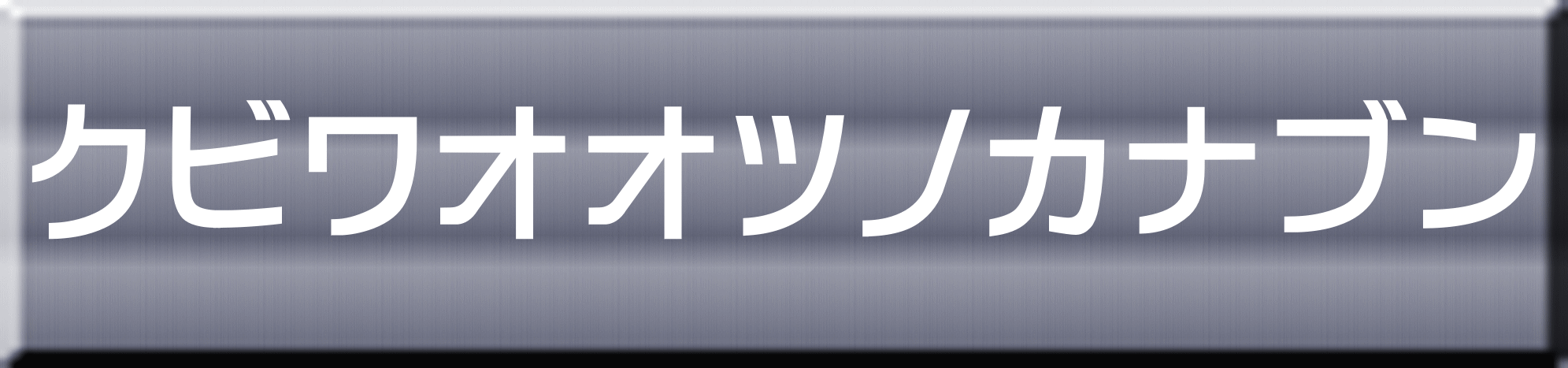
アフリカではカブトムシに代わって、ハナムグリの仲間が繁栄しています。ゴライアスオオツノハナムグリやクビワオオツノカナブンの他にも、アフリカには大型のハナムグリが沢山見られます。本種は現在4亜種に分類され、なお、生態の情報についてはあまり知られていません。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:♂54~89mm、♀45~61mm
分布:熱帯アフリカ東部~西部

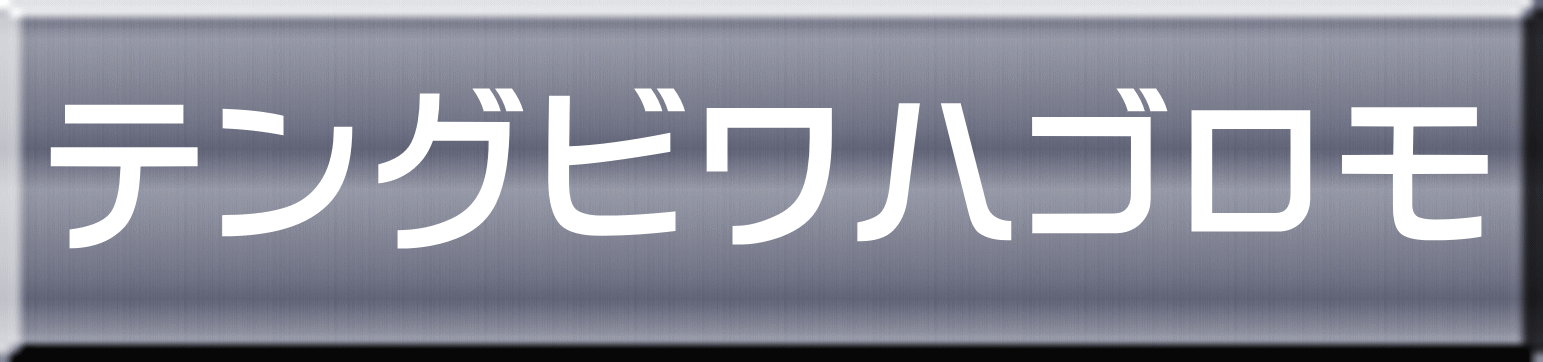
名前の通り天狗の鼻のように長く伸びた頭部が目立ちます。セミに近い仲間の昆虫で、ユカタンビワハゴロモ、アカバナビワハゴロモ等も、不思議な頭を持っています。翅を開く形状と閉じた形状、2つの完成形がありますので、お好みで作って下さい。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:カメムシ目ビワハゴロモ科
分布:東南アジア

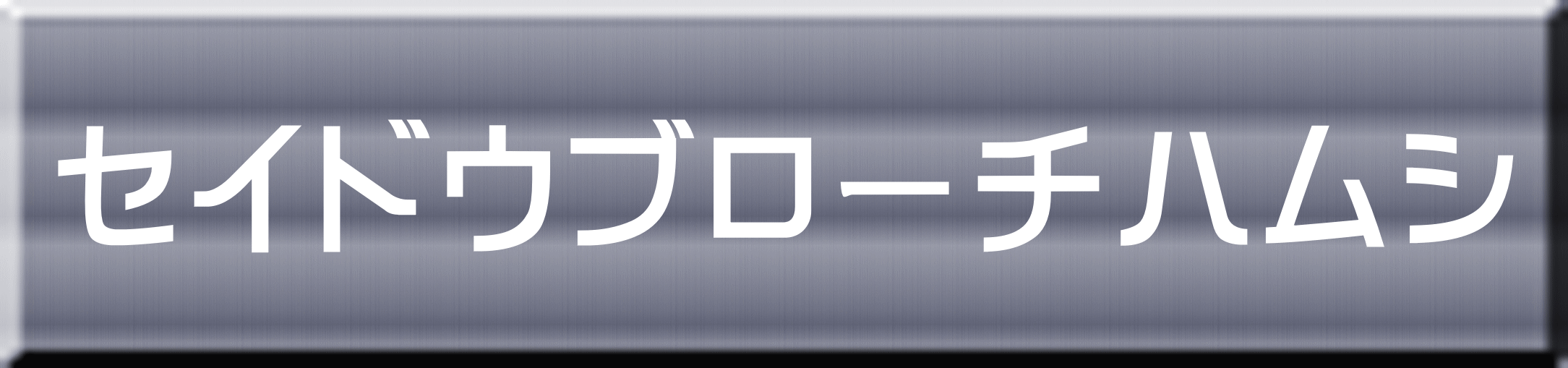
日本のハムシ(葉虫)の仲間には小さくても美しい色彩やユニークな形状をしたものが沢山いますが、それが海外ともなると不思議な虫だらけ。図鑑の写真からでは正確な種名が分からない種類ばかりです。本種は日本にもいる「ジンガサハムシ」という種類の仲間ですが、まるでブローチみたいな美しい体をしています。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目ハムシ科
分布:中南米
ヒミツ情報:翅があるから「羽虫」なのではなく、葉っぱを食べるから「葉虫」。

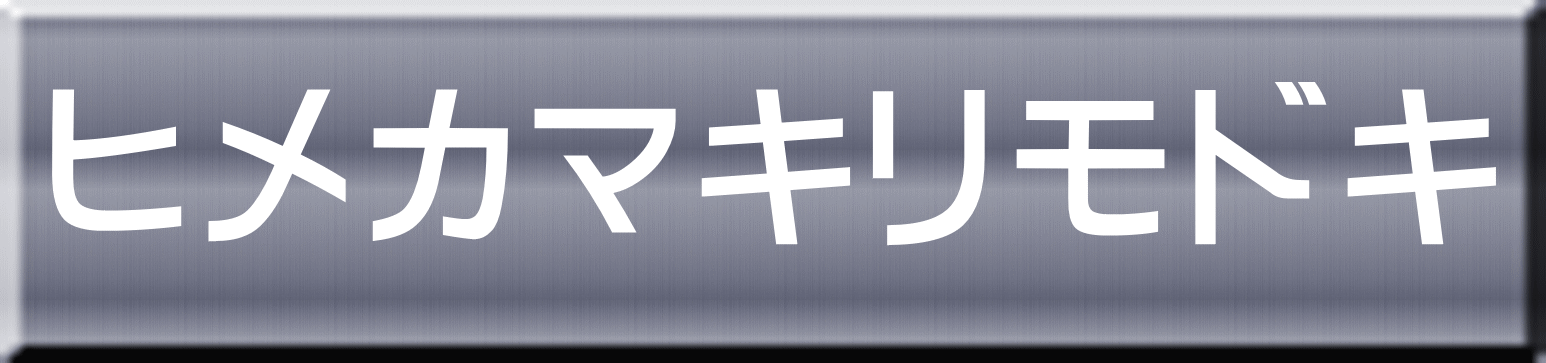
まるでカマキリのような見た目をしているカマキリモドキですが、実はカマキリモドキはウスバカゲロウ(アリジゴクの成虫)の仲間。カマキリと同じように、前肢のカマで小昆虫を捕まえ、食べています。カマキリは蛹にならない「不完全変態」の昆虫ですが、カマキリモドキは蛹の時期がある「完全変態」。しかもその育ち方が不思議で、孵化した幼虫は歩き回ってクモの腹部にしがみつき、その後はクモの卵嚢に寄生し、卵の汁を吸って成長します。やがてその卵嚢の中で繭を作り、蛹になってから、成虫が出てきます。こんな風に、幼虫が形を次々に変えながら成長する育ち方を、完全変態以上の育ち方という意味で、「過変態」と呼びます。過変態をする昆虫には、ツチハンミョウやゲンセイの仲間(甲虫の仲間。体液にカンタリジンという毒)が知られています。英名は「カマキリバエ」で、ハエのように素早く飛び回ります。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:アミメカゲロウ目カマキリモドキ科
前翅長:7~20mm
成虫が見られる時期:6~8月
分布:北海道~九州
ヒミツ情報:カマキリモドキの仲間には、下半身がスズメバチに似た種類も報告されている。恐らく、スズメバチに変装する事で、鳥等に襲われにくくしているのだろう。