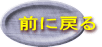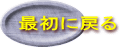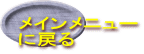名前に「エゾ」とついていますが、北海道だけでなく本州等でも見る事が出来ます。北海道や東北地方では平地でも見られますが、本州中部以西では標高500~1000mの山地に多く見られます。アカマツやスギ、ヒノキ等の樹木に、頭を逆さまにしてとまります。長野県北部では普通に見られる種類のようです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:カメムシ目セミ科
全長:55~65mm
成虫が見られる時期:7~8月
分布:北海道~九州
鳴き声:ギー・・・・・
ヒミツ情報:仙台市では稀であるが、中心部でも声が聞かれた事も。


翅が黒い大型のアゲハチョウで、市街地から山地まで幅広く見られます。アゲハチョウ(ナミアゲハ)よりも暗い場所を好みます。夏は日なたを長時間飛ぶ事は少なく、日陰のある場所をぬうように飛んでいます。幼虫はカラタチ等のミカン科植物を食べます。昔はクロアゲハのような黒い大型のチョウは、死者の魂とされたそうですよ。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:チョウ目アゲハチョウ科
前翅長:45~72mm
成虫が見られる時期:本州の暖地では4~9月
分布:本州、四国、九州、南西諸島


日本特産のオサムシの仲間で、成虫も幼虫もカタツムリが大好物。カタツムリを食べるから又はカタツムリを食べる姿がかぶっているように見える事から「マイマイカブリ」と名前がつけられました。実際にはカタツムリ以外にも、ミミズや小さなトカゲを襲って食べる事もあるようです。2枚の上翅はくっついていて飛ぶ事が出来ません。地上を歩き回って獲物を探します。海外のオサムシ収集家の憧れの的で、地域によって変異があります。この作品は東北地方北部の「キタマイマイカブリ」という亜種で、他にも北海道にエゾマイマイカブリ、東北地方南部にはコアオマイマイカブリ、新潟県(粟島)に固有のアオマイマイカブリ、伊豆大島を含む関東地方と中部地方にはヒメマイマイカブリ、トキで知られる新潟県の佐渡島にはサドマイマイカブリ、島根県隠岐諸島にはオキマイマイカブリがいます。なお、近畿地方以西の西日本に生息するものは基亜種です。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目オサムシ科
体長:32~69.5mm
成虫が見られる時期:初夏~秋
分布:北海道~九州
ヒミツ情報:北海道にいるオオルリオサムシや長崎県対馬のツシマカブリモドキは、マイマイカブリの近縁種で、カタツムリを主な獲物とする。


ジガバチとはミカドジガバチやサトジガバチ等、アナバチ科のうちジガバチ族の狩りバチの総称です。成虫自身は花の蜜を吸っていますが、幼虫はガの幼虫を食べて育ちます。ガの幼虫を捕まえたら、毒針を刺しますが、これは殺すのでは無く、麻酔しているのです。刺されたイモムシは、動けないまま生きていて、幼虫のエサとなるのです。巣穴を掘る時と塞ぐ時、「ジガジガ」という音を立てますが、漢字で書くと「自我」で、昔の人はこれをイモムシから自分に似たハチが地中から出てきますようにと祈っているのだと聞きなし、このハチに「ジガバチ」と名付けたそうです。なお、ファーブルが研究したジガバチはアラメジガバチという種類ですが、ファーブルは息子のジュールの死をいたんで、「昆虫記」第1巻の巻末に下記の通りを記しています。
「愛する子よ、おさないころから、あんなにも花と昆虫にむちゅうになっていた子よ。おまえはわたしに協力してくれた。おまえのするどい目はなにものをも見のがさなかった。わたしはおまえのためにこの本を書くはずだったし、おまえはこの文章をよろこんで読んでくれるはずだった。そうしていつかは、おまえ自身がこの仕事をつづけていくことになっていたのだ。しかし、ああ、なんということだろう。おまえはこの本のはじめのほうしか知らないうちに、天国に旅立ってしまった。せめておまえの名が、あんなにおまえの愛していた、巧妙なはたらきをする美しいハチのなかまにつけられ、いつまでもこの書物の中にあることを、わたしはのぞんでいる。〈「ファーブル昆虫記2 狩りをするハチ(奥本大三郎訳・解説/集英社)」より引用〉
そうして、「ユリウスツチスガリ(ジュールはラテン語では『ユリウス』となります)」等、3種類のハチに新種として、ジュールの名前をつけましたが、それらは新種では無く、無効の名前となっています。注意点は、触角が細い事でしょうか。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:ハチ目アナバチ科
(以下サトジガバチのデータ)
体長:10~23mm
成虫が見られる時期:5~11月
分布:北海道~九州、大隅諸島
ヒミツ情報:葉っぱにそっくりなイモムシを見つけ出すのは大変そうだが、ジガバチは糞を手掛かりに見つけ出す。


草原に棲み、緑色から褐色型まで色々と変異があります。イソップ物語や日本でも昔から親しまれている秋の虫。幼虫は植物の花粉等を食べて成長し、大きくなるにつれて肉食もするようになります。古典に出てくる「きりぎりす」は、キリギリスの事では無くコオロギの意味を含んでいます。暑い盛りに、日当たりの良い草地で鳴いています。鳴いている間は草の上に出ているので観察は容易ですが、一旦見逃すと地上に下りて草の間を移動するので、見つけ出すのは難しくなります。北海道のハネナガキリギリス、沖縄のオキナワキリギリス以外は、20世紀末までキリギリス1種だとされてきました。肢のトゲや触角は、綺麗に抜き取って下さい。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:バッタ目キリギリス科
全長:40mm
成虫が見られる時期:6~9月
分布:本州~九州
鳴き声:ギー・チョン
ヒミツ情報:最近になって「ヒガシキリギリス」と「ニシキリギリス」の2タイプに分けられたが、更に細かく分けられる事がある。

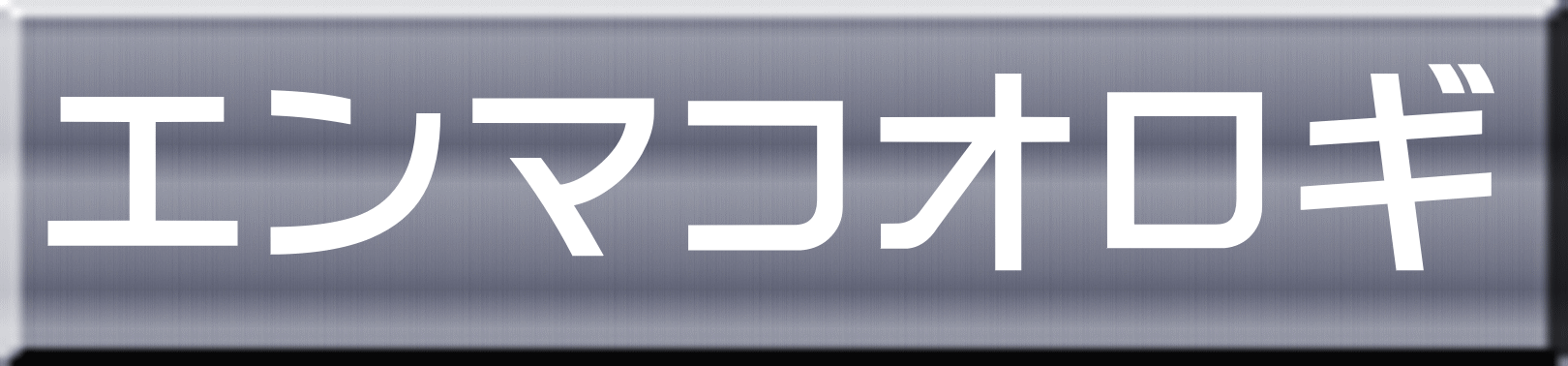
日本で一番大型、そして名前もよく知られているコオロギです。顔が閻魔大王にそっくりなので、「エンマコオロギ」と名付けられました。よく似た仲間に、エゾエンマコオロギやタイワンエンマコオロギがいます。コオロギやキリギリスの鳴き声には、「誘い鳴き(オスがメスに求愛する時の鳴き声)」、「さえずり(縄張り宣言であると同時にメスに居場所をアピールする)」、「ケンカ鳴き(オス同士のケンカで使われる鋭い鳴き声)」の3つがあります。エンマコオロギの鳴き声はメスの距離によってトーンが違い、メスが近くに来ると鳴き声の調子が、長く優しく変わります。耳は前肢にあり、これで鳴き声を聞いています。江戸時代、キリギリスやスズムシ、マツムシ、コオロギ等の鳴く虫が、美しい鳴き声を楽しむ為に、竹製のカゴに入れられて販売されていました。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:バッタ目コオロギ科
全長:20~25mm
成虫が見られる時期:8~11月
分布:北海道~九州
鳴き声:コロコロリー
ヒミツ情報:羽化直後は長い後ろ翅があるが、直ぐに抜き取ってしまう。

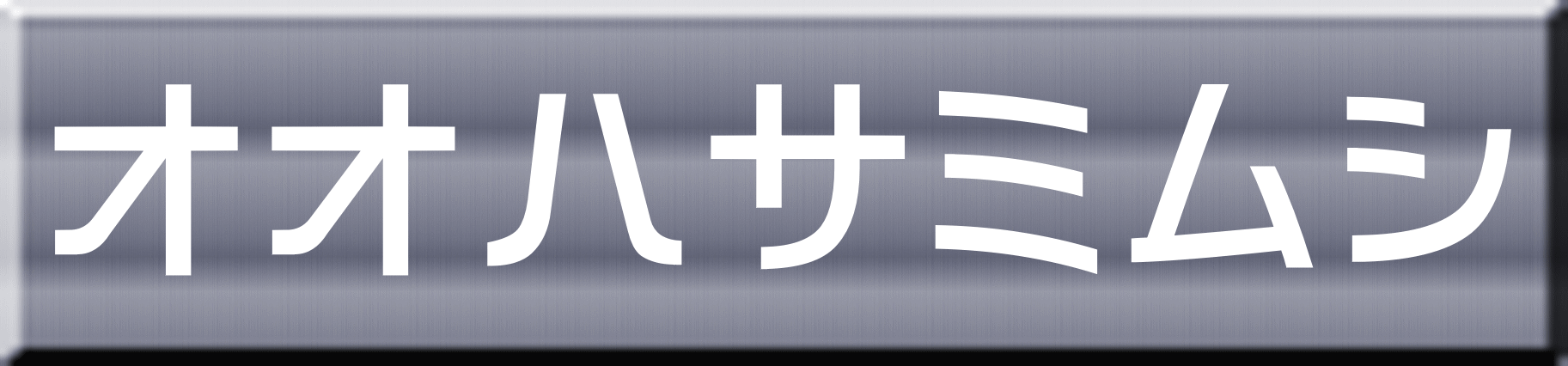
ハサミムシの仲間は、尾の先にハサミを持っていて、これを使って敵と戦ったり、獲物を捕まえたりします。オオハサミムシは、主に海岸や河原、畑の石やゴミの下に見られ、主に動物の死骸や腐った植物、小さな虫を食べています。多くの種類は翅がありませんが、飛ぶ事が出来る種類もいます。メスが卵を守り、幼虫が孵ると自分の体を食料として幼虫に与えるハサミムシもいます。ハサミは見た目は強そうですが、人間が挟まれてもちょっと痛いだけ。毒等はありません。最大種のハサミムシ、セントヘレナハサミムシは、ハサミの先端まで含めて84mmにもなりましたが、外来種による捕食により、2014年に絶滅したとされています。肢が細いので、切れないよう慎重に抜き取りましょう。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:ハサミムシ目オオハサミムシ科
全長:18~30mm
分布:本州、四国、九州
ヒミツ情報:ハサミムシは英語で「earwig」というが、これは「寝ている人の耳の中に入り込み食い入る」という伝承からきている為。(無論そんな真似はしない)また、日本では古い和式便所近くで見られた為か、「ちんぽきり」「ちんぽばさみ」と呼ばれた。

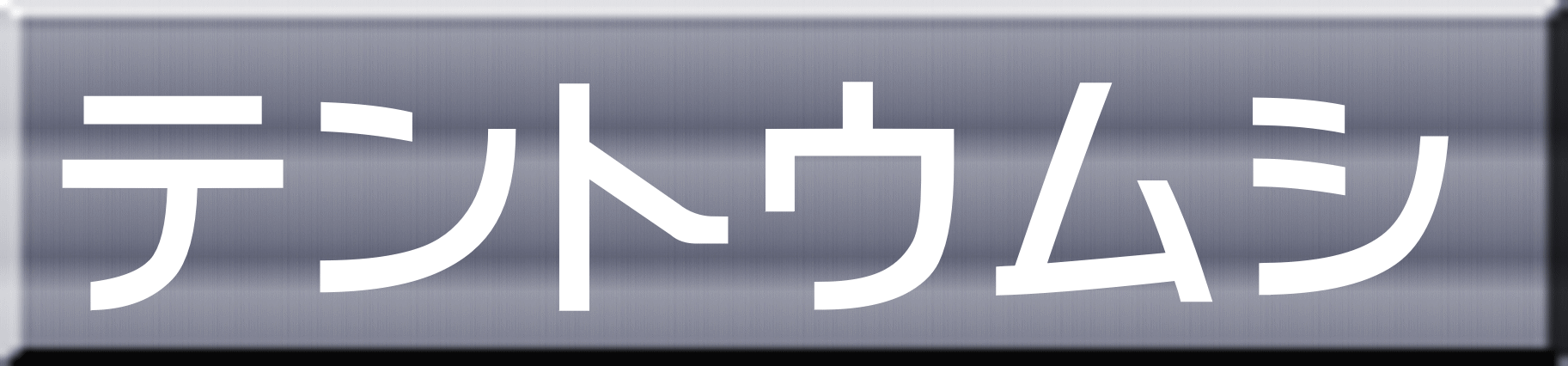
「ナミテントウ」とも呼ばれる、ナナホシテントウと並ぶ身近なテントウムシの1つ。ナナホシテントウ同様に、主にアブラムシを食べています。模様に色々と型があり、図鑑をみても違う種類が混ざっているとしか思えません。この作品は2紋型と呼ばれるタイプです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目テントウムシ科
体長:4.7~8.2mm
成虫が見られる時期:4月~
分布:北海道~九州
ヒミツ情報:西日本に行く程2紋型の割合は高くなり、九州では80%以上が2紋型。