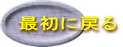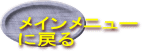「フェモラリスツヤクワガタ」という別名でも知られている東南アジアのクワガタムシ。ツヤクワガタの名の通り、体にツヤがあり、前翅は黄色をしています。本種は肢と腹部の一部が赤っぽいので、このような名前がつきました。灯火に飛来する事もあります。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:50~95mm
分布:マレー半島、ボルネオ、フィリピンのパラワン島
ヒミツ情報:短歯型のツヤクワガタの場合、戦わせた相手の肢を噛み切ってしまう事もある。


春の始まった頃から活動を開始している、身近なチョウの1つです。幼虫はキャベツ等のアブラナ科植物を食べて育ちます。抜き取って折るだけなので、簡単に、しかも本物らしく出来ますよ。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:チョウ目シロチョウ科
前翅長:20~30mm
成虫が見られる時期:本州では3~11月
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:人間の目ではオスもメスも同じ色に見えるが、メスは紫外線を反射している為、モンシロチョウの目で見るとメスは黒く見えるのだ。


サソリは昆虫では無く、クモに近い節足動物です。チャグロサソリの毒性は、ヨーロッパや中東等にいるデスストーカー等と比べて弱い方ですが、刺されると痛いです。東南アジア諸国では、標本が土産物として売られている事があります。タイやインドには本種に近い種類が多いですが、一般には見分けがつきません。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:クモ綱サソリ目コガネサソリ科
体長:7~9cm
分布:東南アジア
ヒミツ情報:サソリの祖先は陸棲節足動物の中でも最も古く、4億年以上大昔の「シルル紀」という時代から発見されている。

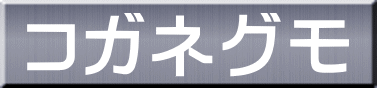
チャグロサソリ同様、クモも昆虫では無く節足動物。このコガネグモも、チャグロサソリも、「鋏角類」というグループに含まれています。鋏角類の特徴は、頭部にハサミ状の鋏角又は鋏肢を持ち、触角が無い事です。コガネグモは背の高い草の生えた所に棲み、「クモの巣」を張ってかかった昆虫を捕まえて食べます。クモの食事は「体外消化」といい、牙から毒を流し込んで中身を溶かし、獲物の中身を吸い取る方式です。写真のクモの巣は、切り紙で作ったもの。「切り紙昆虫館 ハサミで作ろう!」収録作品で、「平井智明切り紙博物館」にて紹介しているクモの巣と同じものです。ビニールテープを細く裂いたものを獲物にクルクルと巻きつけて巣に置いてみると、クモ糸みたいに感じました。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:クモ綱クモ目コガネグモ科
体長:♂5~7mm、♀20~30mm
成体(クモの場合成虫では無く成体、幼虫では無く幼体と呼ぶ)が見られる時期:6~8月
分布:本州、四国、九州、南西諸島
ヒミツ情報:クモの糸は同じ太さの鋼鉄の5倍以上も頑丈。太さ1cmのクモ糸でクモの巣を作れば、飛行機を捕まえられると言われている。


文字通り花に隠れて獲物を待ち伏せるカマキリです。別名を「ランカマキリ」といい、鎌を繰り出す速さは20分の1秒というスピード。体色はピンク色から白っぽい色まで変化があります。1齢幼虫の頃はカメムシの一種とそっくりな赤と黒の体ですが、脱皮を重ねるにつれて花っぽい姿になってきます。但し、成虫はあまり花そっくりでは無いようです。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:カマキリ目ハナカマキリ科
全長:♂35mm、♀70mm
分布:インド、タイ、マレーシア、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島
ヒミツ情報:幼虫の時だけだが、口からミツバチが仲間を呼ぶ時に出す匂いを出し、ミツバチをおびき寄せる事がある。



オオムラサキは日本の国蝶。主に平地から低山地にかけて棲み、樹液や動物の糞の汁を吸っています。オスは美しい紫色の翅をしていますが、メスは翅が地味な灰色です。滑空するように速く飛びます。気性が荒く、スズメを追い回した事もあるそうです。タテハチョウ科のチョウは前肢が退化して4本肢に見える為、最初は僕も不審に思いました。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:チョウ目タテハチョウ科
前翅長:43~68mm
成虫が見られる時期:6~8月
分布:北海道~九州
ヒミツ情報:世界最大のタテハチョウの1つ。

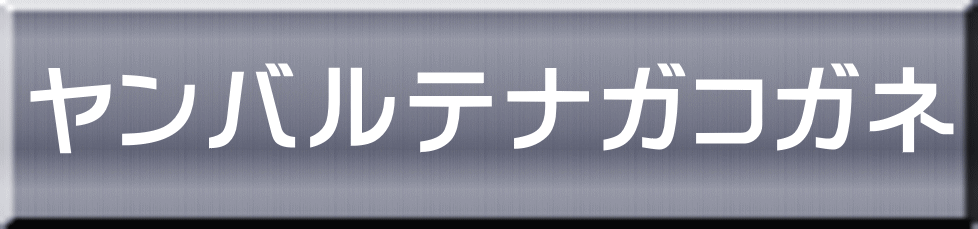
沖縄島に棲む大型のコガネムシで、名前の通りオスは前肢が長くなります。カシ類の洞の中に暮らしています。日本最大の甲虫で、国指定の天然記念物。長い前肢を何に使うかは分かりませんが、果実を抱え込んだりするのには便利そうです。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:42~63mm
成虫が見られる時期:8~10月
分布:沖縄島(北部)

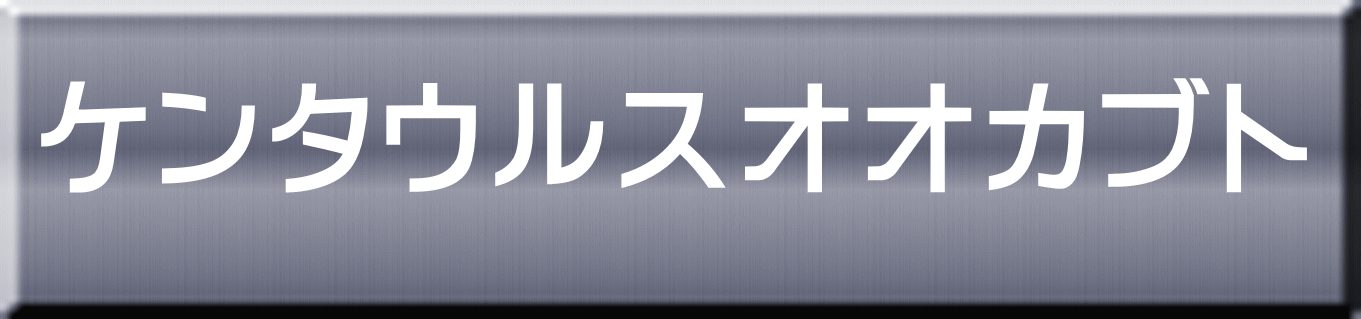
ケンタウルスオオカブトはアフリカ最大のカブトムシ。アフリカではカブトムシに替わってハナムグリの仲間が繁栄していて、アフリカの大型カブトムシは2種類程度。胸角には2つの突起を備えていて、先がしっかりしている頭角は、フックみたいになっています。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:40~90mm
分布:アフリカ中部の熱帯地域


日本で一番大きなカミキリムシ。クリ等の木を食い荒らしてしまう害虫ですが、カブトムシやクワガタが集まっている樹液は、シロスジカミキリやボクトウガの幼虫が木の内部を食べた時の傷口からしみ出したものです。捕まえると、首の後ろにあるヤスリのような部分をこすり合わせ、ギーギー鳴きます。大型カミキリムシ類の幼虫は、世界の色々な地域で食用とされ、重要な蛋白源にもなっています。日本でも、燃焼中の薪の中にいる幼虫は焼き上がると破裂音を立てるらしく、その音がすると火箸等で取り出して食したりするようです。カミキリムシの幼虫を「テッポウムシ」と言うのは、破裂音を銃声に例えたとも、食害により銃弾が打ち込まれたかのような穴が木に開くからともいわれています。長い触角の向きに気を付けて下さい。「りったい昆虫館パート3」収録作品。
分類:甲虫目カミキリムシ科
体長:40~55mm
成虫が見られる時期:5~8月
分布:本州、四国、九州、奄美大島
ヒミツ情報:背中の筋はやや黄色みを帯びているが、死ぬと白くなる。