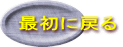クロオオアリは開けた場所の地中に大きな巣を作る、日本最大のアリの一つです。ミツバチやスズメバチと同じように、1匹の女王アリと沢山の働きアリ、そしてオスアリで集団生活を送っています。働きアリの中で大型のアリが兵アリとなります。肢が細いので抜き取る時に切れないように注意しましょう。なお、オオスズメバチにも共通の作り方として、腹部の胸部と糊付けする箇所は平べったく、つまり腹部を三角錐みたいな形にする事がコツです。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:ハチ目アリ科
体長:♀(働きアリ)7~12mm
成虫が見られる時期:4~11月
分布:北海道~九州、屋久島、トカラ列島(中之島)
ヒミツ情報:クロシジミというチョウの幼虫を巣穴で育てる。アリがエサを与えると、クロシジミは甘い汁を出す。


カブトムシの幼虫は土の中で、腐葉土に含まれる落ち葉や、朽木を食べて成長します。サナギになると土の中に作った部屋(蛹室といいます)の中で動かなくなり、体が成長するのをじっと待ちます。そして、翌年の夏に、成虫となって地上に出てきます。成虫の体の大きさはサナギの段階で決まってしまい、小さな成虫は一生小さいままです。「りったい昆虫館」収録作品。

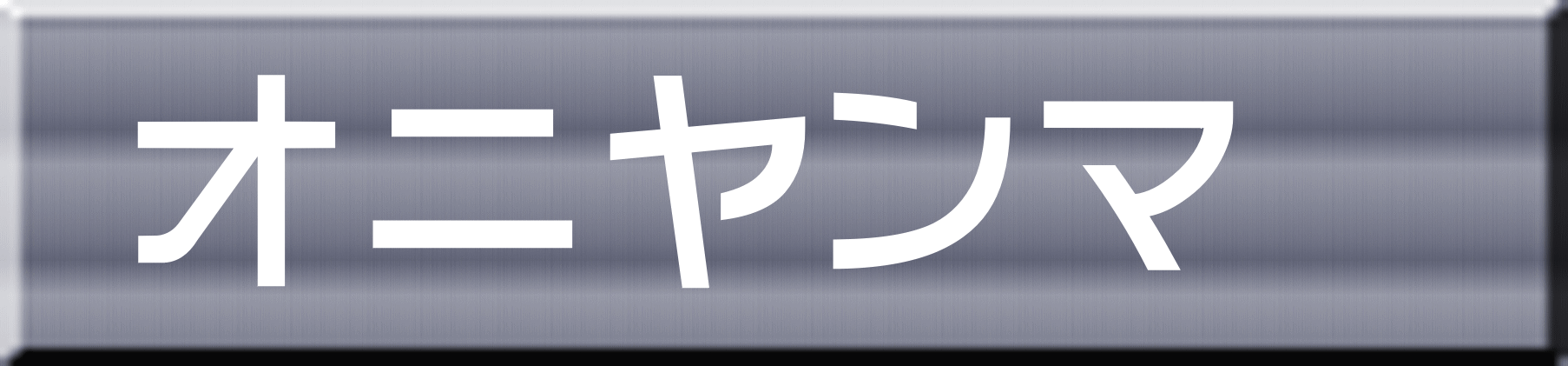
日本最大のトンボ、オニヤンマ。川や水辺の近くを飛んでいる事が多く、幼虫は平地から山地の小川や渓流に見られます。発達した大顎で飛んでいる昆虫を捕らえ、嚙み砕いて食べます。人間が指を噛まれでもしようものなら、血が出るはずでしょう。4枚の翅はしっかりと接着しましょう。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:トンボ目オニヤンマ科
体長:100mm前後
成虫が見られる時期:6~10月
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:開け放した家の中に入って来る事がある為、「ドロボーヤンマ」とも言われる。


夏の風物詩としても親しまれる昆虫、ホタル。光で異姓に求愛したり、敵を威嚇したりしています。「ホタルは光る虫」というイメージですが、実は成虫が発光するホタルは意外と珍しいんだそうです。少し小さいと思いますし、肢も細いので慎重に抜き取りましょう。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目ホタル科
体長:10~16mm
成虫が見られる時期:5~7月
分布:本州、四国、九州
ヒミツ情報:アメリカの「フォツリス・ベルシコロル」というホタルは他のホタルの発光パターンで他種のオスを誘い寄せ、捕まえて食べてしまう。


市街地から高山まで、幅広く見られます。同じ仲間のアゲハチョウ(ナミアゲハ)と、翅の模様で見分けられます。(キアゲハは前翅の付け根が黒っぽい)幼虫はセリやニンジン、ハナウドの葉を食べて育ちます。山の頂上に集まって縄張りを作る習性があります。翅の上に胴体を糊付けします。取れやすいのでしっかり付けて下さい。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:チョウ目アゲハチョウ科
前翅長:36~70mm
成虫が見られる時期:暖地では3~11月
分布:北海道~南西諸島(屋久島以北)
ヒミツ情報:中学校の国語の教科書に出ている「少年の日の思い出」に登場するチョウの1つ。


川原の草地や、山道沿いの藪を棲みかとしています。日本のカマキリではお馴染みの種類です。鎌のような前肢で昆虫を捕まえて食べますが、カエルやトカゲも捕食します。稀に小鳥を襲う事例も記録されており、NHKの番組「ダーウィンが来た!」でも、絶海の孤島・石川県の舳倉島でカマキリが鳥を捕まえる映像が公開されましたね。メスは枯れ草等に100~300個もの卵が入った卵嚢を産みつけます。カマキリの種類ごとに卵嚢の形状や見られる場所は異なります。多くのカマキリはオスよりメスの方が大きい為、交尾中にメスがオスを食べてしまう事も知られています。カマキリは獲物を待ち伏せる姿が祈っているように見える為、英語では「プレイング・マンティス」と言いますし、日本でも「祈り虫」等と言います。よく似たチョウセンカマキリ(カマキリ)とは、お腹側から見て鎌の間がクリーム色である事、後ろ翅の色が濃い紫色である事で区別出来ます。(チョウセンカマキリは鎌の間が朱色で、後ろ翅の色は薄く透明に近い)「りったい昆虫館」収録作品。
分類:カマキリ目カマキリ科
体長:♂68~90mm、♀75~95mm
成虫が見られる時期:8~11月
分布:北海道~九州、屋久島
ヒミツ情報:フランスではカマキリの卵を「ティニョ」といい、しもやけに効く薬としていたという。


威風堂々としたバッタの王様。川原等のイネ科植物が生える所に見られます。跳ぶ力もとても強く、昆虫サイズでも50m位跳びますし、もしトノサマバッタが人間サイズになれば、ビルの9階までジャンプ出来ると言われています。よく似たクルマバッタと違い、翅に黒い帯はありません。接着が剥がれやすい所が幾つかあります。しっかりと糊付けしましょう。触角も細いので気を付けて下さい。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:バッタ目バッタ科
全長:♂40~50mm、♀50~60mm
成虫が見られる時期:7~11月
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:周りに仲間が多くなり、エサの植物が減ると、「群生相」と呼ばれるバッタが誕生する。群生相は翅も長くなり、長距離移動に適した体つきになる。2007年には、関西空港でもトノサマバッタが大発生している。

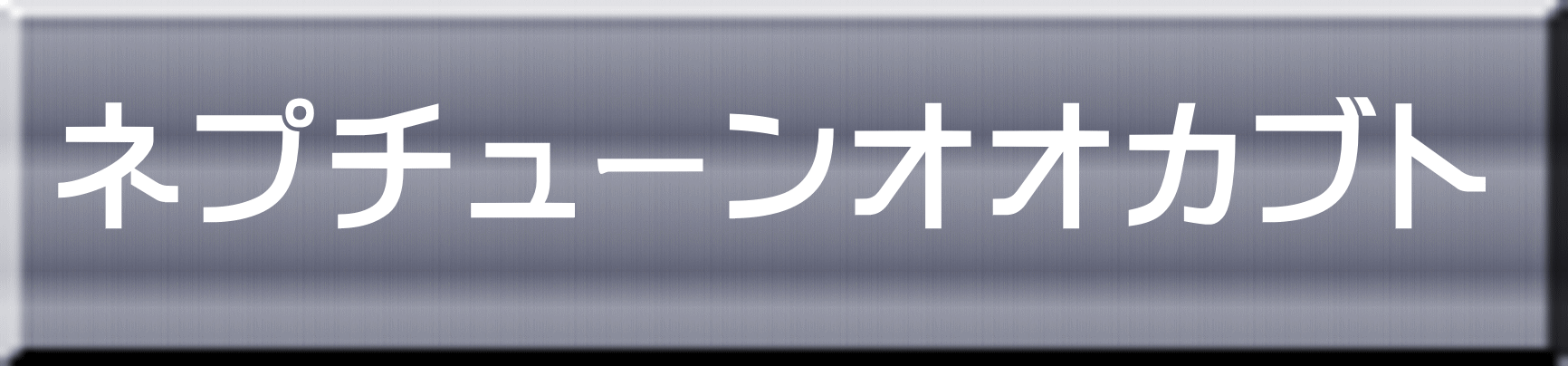
長く湾曲した頭角がカッコいい、大人気の大型カブトムシです。ネプチューンというのは、ローマ神話の海神の事で、ギリシャ神話ではポセイドンというそうです。「サウロポセイドン」という、30m級の大型植物食恐竜もいましたね。とても早起きで、朝の3時位から活動を開始しているそうです。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
全長:55~160mm
分布:ベネズエラ、コロンビア、ペルー、エクアドル等の南米の国々
ヒミツ情報:前肢の形状から、ボリビアのサタンオオカブトと近い種類だと考える人もいる。


これも日本の夏のセミの代表選手。平地から低山地まで、普通に見られます。僕の近所で多く見られるセミはニイニイゼミ、クマゼミ、そしてこのアブラゼミで、ミンミンゼミはあまり見かけません(高等部の伊吹山登山合宿で、ミンミンゼミは声だけ確認出来た)。南西諸島(奄美諸島~沖縄島周辺)には、リュウキュウアブラゼミという種類がいて、こちらは薄暗い林や低山地等に見られます。ミンミンゼミ同様、翅はしっかりとずれないように接着して下さい。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:カメムシ目セミ科
全長:55~63mm
成虫が見られる時期:7~9月
分布:北海道~九州、屋久島
鳴き声:ジージリジリジリ・・・・・・・・・
ヒミツ情報:イソップ物語の「アリとキリギリス」の物語は、元々は「アリとセミ」というお話だった。北ヨーロッパ等では、セミはあまり知られていない。

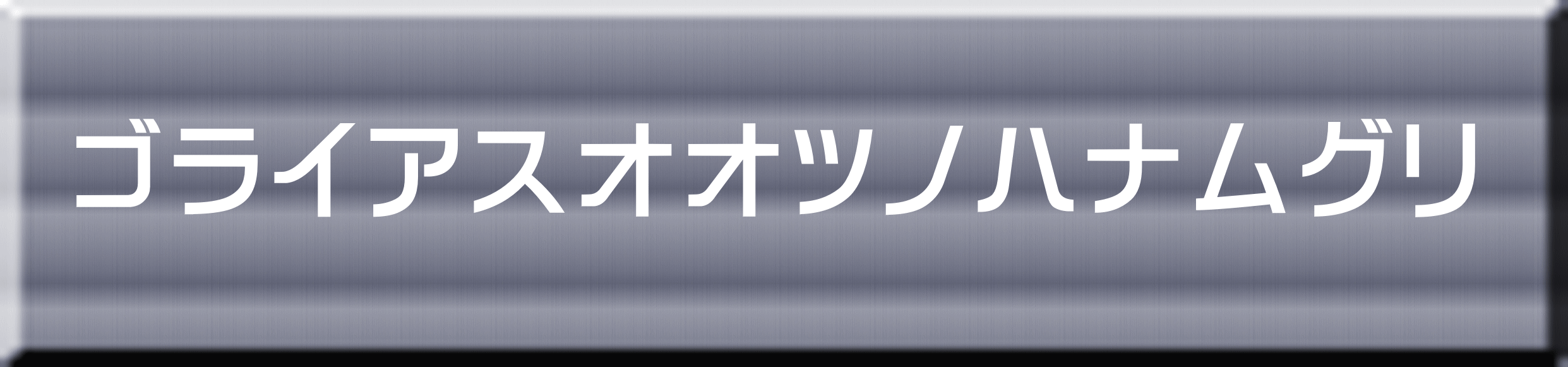
世界最大のハナムグリで、熱帯雨林で花粉や樹液、熟した果実を食べて暮らしています。前翅の模様には、幾つか変異があり、日本のカナブン同様に、前翅は浮かせ、後ろ翅だけで飛びます。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:♂55~110mm
分布:ナイジェリアからケニアまでの地域
ヒミツ情報:あまりに大きい為、銃で撃って捕まえた探検家もいたとか。


夏の雑木林で、樹液に集まっているメタリックな甲虫は、カナブンやこのアオカナブン。シロテンハナムグリ等も樹液に集まっていますね。1つ前のゴライアスオオツノハナムグリの所でも紹介しましたが、カナブンやハナムグリの類は、前翅を浮かせて後ろ翅だけで飛ぶので、とても速く飛ぶ事が出来ます。少ないパーツで作れるので、是非挑戦してみて下さい。「新りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:26~29.8mm
成虫が見られる時期:6~9月
分布:北海道~九州