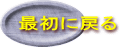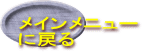動物の糞をボール状にして転がす、フンコロガシの1種です。古代エジプトではフンコロガシが「スカラベ」と呼ばれ、太陽を運ぶ虫として崇められてきました。糞の球は地中に埋めて食料にします。一生、動物の糞を食べて暮らすコガネムシ科の甲虫は「糞虫」と呼ばれます。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:42mm
分布:アフリカ
ヒミツ情報:「ファーブル昆虫記」に登場するスカラベは実はスカラベ・サクレではなくスカラベ・ティフォン。


山道を歩いていると、足元から小さな虫がパーッと飛んでいく事がありますね。近づくとまた飛んでいき、こちらが近づけばまた飛んでいき・・・・・・・という具合です。この昆虫の名はハンミョウといいますが、前述のような修正から「ミチオシエ」とか「ミチシルベ」とか言われてきました。宝石みたいに美しい体の持ち主ですが、凶暴な肉食昆虫。素早く地面を動き回って、ハエや地面にいる昆虫、ミミズを襲って食べています。幼虫は地面に掘った巣穴に住んでいて、待ち伏せて獲物を捕らえます。細長い草の葉を巣穴に差し込んで幼虫を釣り上げる昔の子供の遊びから、ハンミョウの幼虫は「ニラ虫」と呼ばれています。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目ハンミョウ科
体長:18~20mm
分布:本州、四国、九州、沖縄島
ヒミツ情報:昆虫は普通幼虫期にエサ不足があると死ぬ事が多いが、ハンミョウの場合はエサが少ないと幼虫期間を少し伸ばす。


水生昆虫の王者は、やっぱりタガメ。太く発達した前肢に、鋭いツメが生えています。この前肢で、魚やカエル、他の水生昆虫等を捕らえて体液を吸います。お尻の先に生えているのは、息をするのに使う呼吸管。これで空気中の酸素を取り込みます。水田のイネや植物の茎に卵を産み、オスはその卵を守ります。メスは、他のメスの産んだ卵を破壊。卵を守っていたオスと交尾し、新たな卵を産みます。口吻で刺されるととても痛いので気を付けて下さい。中国や台湾にも生息し、中国では漢方薬にもなっています。東南アジアでは香りが好まれ、食用にもしているそうですよ。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:カメムシ目コオイムシ科
体長:48~65mm
分布:日本、中国、台湾等(日本では本州、四国、九州、南西諸島)
ヒミツ情報:猛毒を持ったマムシまでも襲った記録がある。


田んぼ等に見られ、死んだ魚やカエル、オタマジャクシ等を食べる肉食昆虫です。後ろ肢に細かい毛が生えていて、これをボートのオールみたいに使い、巧みに泳ぎます。幼虫は細長い姿で、「田んぼのムカデ」とも呼ばれています。発達したアゴに猛毒を持ち、水中の生き物を襲います。人を噛む事もあり、その毒は人間の細胞を壊死させる事が出来る程の威力です。また、腹部の先を水面に突き出し、翅の下に空気を溜めておく事で、長時間水中に潜る事が出来ます。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目ゲンゴロウ科
体長:36~39mm(幼虫60~80mm)
分布:日本、中国、シベリア等
ヒミツ情報:成虫を捕まえると、白くて臭いのする液体を背中から出す。


夏になると大きな声で鳴くセミ。オスのセミは、ほとんど空っぽに見えるお腹の奥に膜があり、「腹弁」と呼ばれます。この腹弁を振動させる事により、大きな音を出すのです。なお、メスのセミは鳴きません。ミンミンゼミはお馴染みのセミの1つ。平地から低山地にかけて普通に見られる種類です。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:カメムシ目セミ科
全長:57~64mm
成虫が見られる時期:7~9月
分布:北海道~九州、対馬
鳴き声:ミーンミンミンミンミー・・・・・・・
ヒミツ情報:背中の黒い模様が無く、全体的に緑色や空色のミンミンゼミは、「ミカド型」と呼ばれ、決まった地域にのみ見られる。

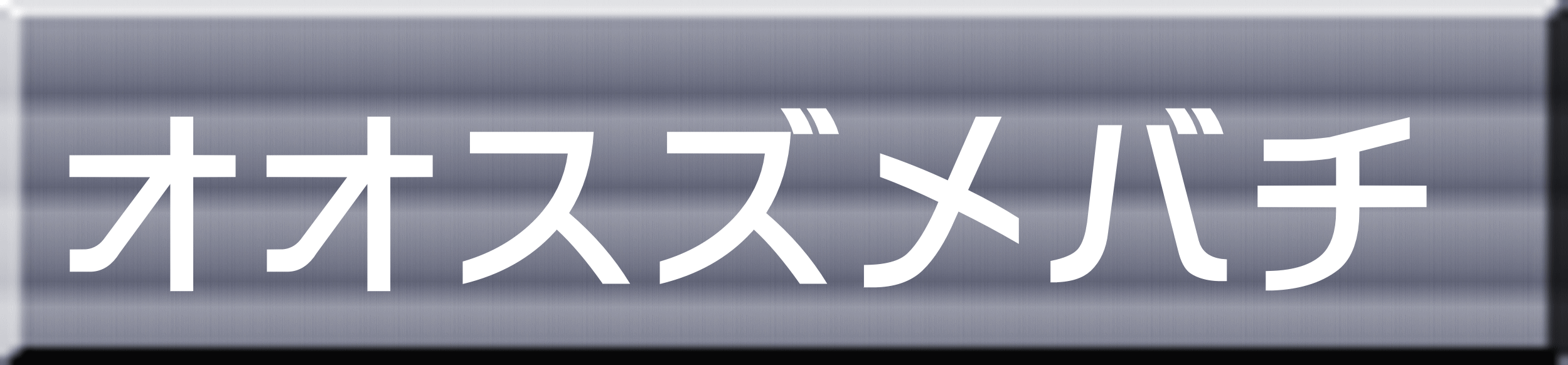
世界最大にして最強(最凶?)のスズメバチが、オオスズメバチ。大きいと身の丈5cm位になる、ならず者軍団です。地中のネズミやモグラ等が掘った穴に、巨大な巣を作ります。刺されるとかなり危険で、2度目に刺されるとアナフィラキシーショックで死亡する事も。キイロスズメバチやモンスズメバチの巣や、ミツバチの巣箱を襲い、全滅させる事もあります。小型昆虫を捕らえ、丈夫なアゴで嚙み砕き、肉団子状にして幼虫に与えます。樹液に集まっている事もあるので、夏休みの昆虫採集は特に注意が必要ですよ。翅は取れやすいので、しっかりと糊付けしましょう。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:ハチ目スズメバチ科
体長:♂30~39mm、♀(女王)40~45mm♀(働きバチ)27~40mm
成虫が見られる時期:5~10月
分布:アジアの広い地域。日本では北海道~九州、大隅諸島。
ヒミツ情報:成虫のエサは樹液だけでなく、幼虫が獲物を食べる度に唾液腺から出す栄養液。

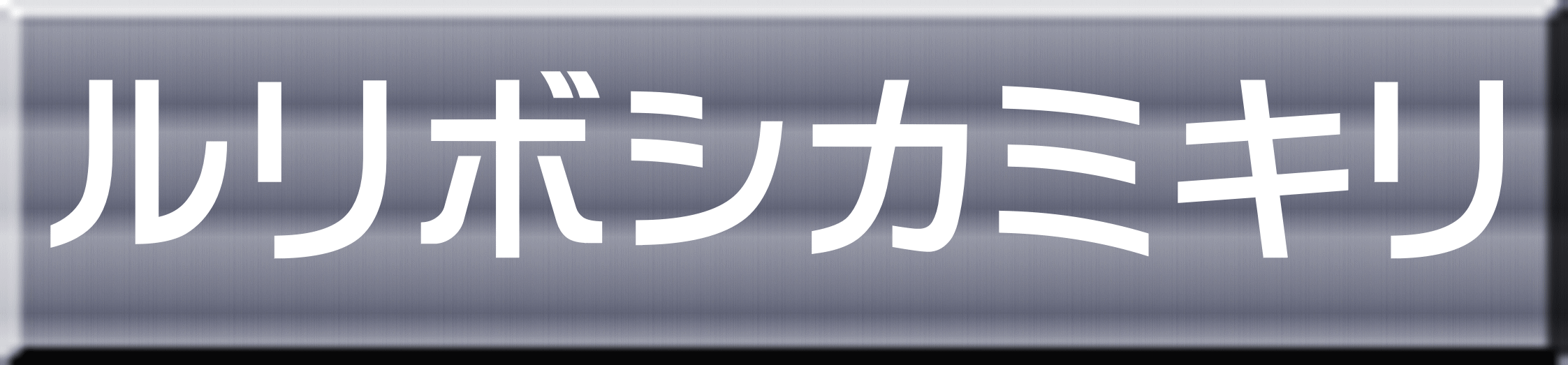
目の覚めるような水色に、黒い模様の綺麗なカミキリムシ。伐採した広葉樹に集まります。普通に見られる種類ですが、日本が世界に誇る、日本特産のカミキリムシです。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目カミキリムシ科
体長:18~29mm
成虫が見られる時期:6~9月
分布:北海道~九州


ゾウムシの仲間の自慢は、体の硬さ。八重山諸島にいるクロカタゾウムシという種類には、「標本にする為にステンレス製の針を刺そうとしても、硬過ぎて針が刺さらなかった」とか、「あまりにも硬過ぎて、鳥に食べられても消化されずに出てきた」等々、その頑丈さを示すエピソードがごまんとあります。オオゾウムシの硬さも、本州では五本の指に入るでしょう。クヌギやヌルデ等の樹液に集まります。本物のオオゾウムシを捕まえたなら、観察してごらんなさい。肢に鋭いトゲが生えているの、分かりますよね?これで木にしがみついているので、簡単には引きはがせませんよ。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目オサゾウムシ科
体長:12~29mm
成虫が見られる時期:6~10月
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:ビールもお好みらしいという事を書いた本も僕は見てみたが、僕が実際にオオゾウムシがビールを好むかを実験する事は無かった。

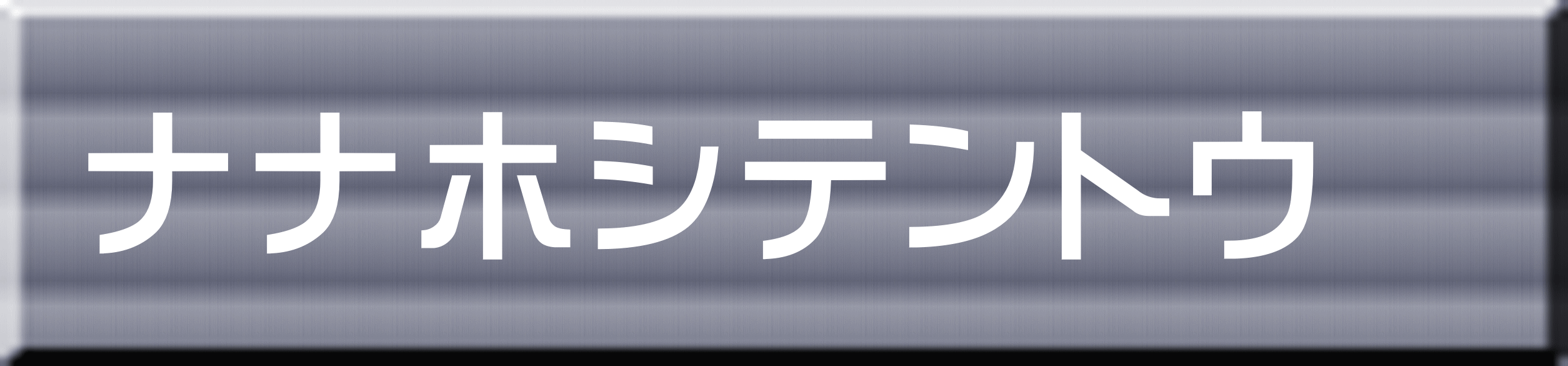
学校の校庭でも見かける可愛らしいテントウムシ。中でもナナホシテントウは、その代表選手です。成虫も幼虫も、アブラムシを食べて育ちます。刺激を与えると死んだふり、更に肢の間から黄色い液体を出すそうですが、これは鳥が吐き出す程苦いんだそうです。テントウムシは高い所から飛び立つ習性があり、指に止まらせて垂直に立て、飛ばして遊んだ方もいるでしょう。小さいですが、綺麗で面白い奴です。肢は細いので、途中で切れてしまわないよう気を付けて下さい。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目テントウムシ科
体長:5~8.6mm
成虫が見られる時期:春~秋
分布:北海道~南西諸島
ヒミツ情報:仰向けにされて、起き上がれないと前翅を使い起き上がる。もし捕まえたらその大道芸をじっくり観察しよう。