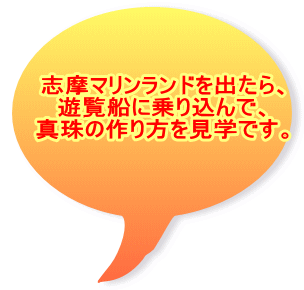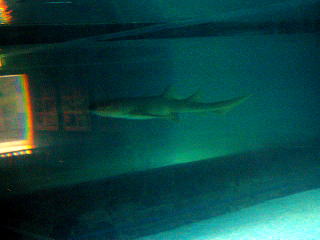 えっ、あれは、サメ!?
えっ、あれは、サメ!?
 アマゾン川に棲む、世界最大の淡水魚・ピラルク。全長4.5mに達する古代魚です。その恐竜のような鱗は頑丈で、嚙みついたピラニアの歯が折れてしまう事さえある位です。
アマゾン川に棲む、世界最大の淡水魚・ピラルク。全長4.5mに達する古代魚です。その恐竜のような鱗は頑丈で、嚙みついたピラニアの歯が折れてしまう事さえある位です。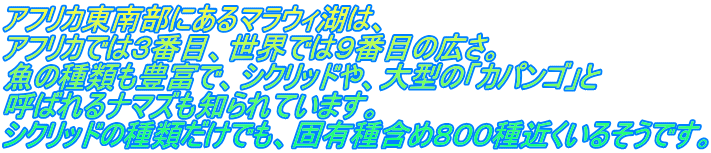
 マラウィ湖の魚達
マラウィ湖の魚達 見た目はタチウオやリュウグウノツカイに似ていますが、この魚の名前はサケガシラ(標本)。小魚やイカが主な主食なようで、2013年には胃袋からイカのクチバシ(カラストンビ)が多数見つかりました。大きなものは2mに達し、北海道から沖縄までの、日本近海の太平洋、日本海全域に分布。沖合中層域200~500m(海底から離れている)に生息しています。
見た目はタチウオやリュウグウノツカイに似ていますが、この魚の名前はサケガシラ(標本)。小魚やイカが主な主食なようで、2013年には胃袋からイカのクチバシ(カラストンビ)が多数見つかりました。大きなものは2mに達し、北海道から沖縄までの、日本近海の太平洋、日本海全域に分布。沖合中層域200~500m(海底から離れている)に生息しています。






サクラダイ
 伊勢志摩の海をパチリと一枚、カメラに収めました。
伊勢志摩の海をパチリと一枚、カメラに収めました。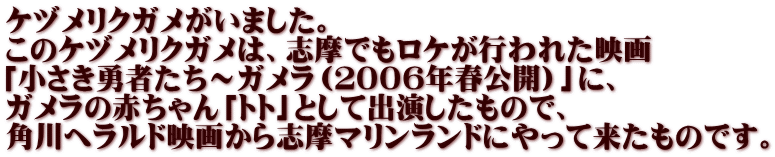



 餌の葛の葉を与えると、バリバリ音を立てて嚙み砕いて食べました。赤ちゃんガメラ、恐るべし。
餌の葛の葉を与えると、バリバリ音を立てて嚙み砕いて食べました。赤ちゃんガメラ、恐るべし。
 海賊船のような見た目の遊覧船に乗って、真珠工房のある島へと航海に乗り出しましょう。
海賊船のような見た目の遊覧船に乗って、真珠工房のある島へと航海に乗り出しましょう。
 アコヤガイ養殖の筏は、見えるかな?
アコヤガイ養殖の筏は、見えるかな?真珠の作り方
真珠が作られる貝として知られるのは、先程登場したアコヤガイ。アコヤガイは、体の中に入ったものを核として真珠層を巻く性質があり、真珠の養殖に利用されています。日本の養殖真珠の発明は、「球体に削った核を、アコヤガイの体内に外套膜と一緒に挿入し、真珠層を形成させる」というもの。因みに養殖では、別の貝の貝殻を真円状に加工したものを核としています。3年程で、真ん丸な真珠が出来上がり。日本の真珠は、愛媛県の宇和海、長崎県の大村湾、そして三重県の英虞湾で養殖されています。真珠には、本真珠や養殖真珠の他に、シロチョウガイから産する南洋真珠、クロチョウガイから産する黒蝶真珠、マベガイから産するマベ真珠、イケチョウガイやカラスガイから産する淡水パール、西インド諸島のカリブ海に生息する「ピンク貝」と呼ばれる巻貝から産するコンクパール、ハルカゼヤシガイから稀に産するメロパール等があります。日本の真珠の美しさはヨーロッパにまで伝わり、コロンブスも憧れたとか。

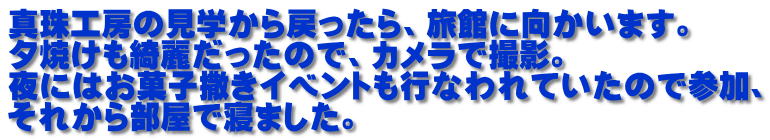


 僕達が泊まっていた旅館の部屋です。
僕達が泊まっていた旅館の部屋です。