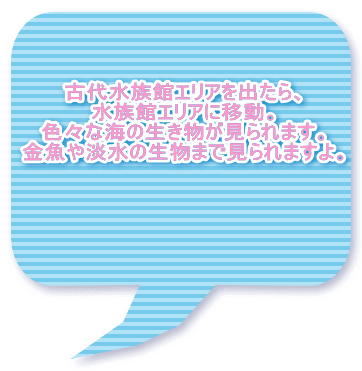
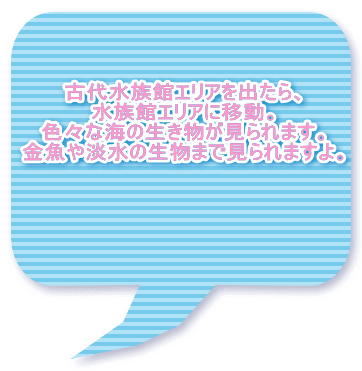




 これは、サメかな?サメだったら、何ていう種類かな?
これは、サメかな?サメだったら、何ていう種類かな?

 モンガラカワハギは、名前に「カワハギ」と付いていますが、カワハギがフグ目カワハギ科なのに対し、モンガラカワハギはフグ目モンガラカワハギ科なので、全くの別物です。
モンガラカワハギは、名前に「カワハギ」と付いていますが、カワハギがフグ目カワハギ科なのに対し、モンガラカワハギはフグ目モンガラカワハギ科なので、全くの別物です。

ツノダシ

 うわ~、魚がいっぱい!
うわ~、魚がいっぱい!

 この魚、前から見たら、こんなに薄っぺら~い。
この魚、前から見たら、こんなに薄っぺら~い。
 ナポレオンフィッシュことメガネモチノウオ。風格充分!
ナポレオンフィッシュことメガネモチノウオ。風格充分!






ウツボの水槽には、ウツボやウミヘビ(魚類の方ね)の仲間達。ウツボの口の中には、もう一つの「顎」があり、獲物をしっかりとくわえ込みます。

 コバンイタダキことコバンザメは、頭に吸盤が付いていて、それで大きな魚やカメ、イルカにくっついて泳ぐちゃっかり者。吸盤は背ビレが変化して出来たもので、くっついて身を守るだけで無く、くっついている相手からおこぼれを頂く事も。成長すると、自分で泳ぐ事もありますが、体が小さいうちは、他の生き物にくっついて暮らします。
コバンイタダキことコバンザメは、頭に吸盤が付いていて、それで大きな魚やカメ、イルカにくっついて泳ぐちゃっかり者。吸盤は背ビレが変化して出来たもので、くっついて身を守るだけで無く、くっついている相手からおこぼれを頂く事も。成長すると、自分で泳ぐ事もありますが、体が小さいうちは、他の生き物にくっついて暮らします。




「魚のお医者さん」ホンソメワケベラが、大きな魚をクリーニング。魚に付いた寄生虫を主に食べていますが、チャンスがあれば魚にかじりついて粘液を食べる事も。

ニセクロスジギンポ
ホンソメワケベラによく似ている魚が、たまにホンソメワケベラのそばにいる事があります。その魚は、ホンソメワケベラとほぼ同じ大きさで、模様までそっくりですが、積極的にクリーニングをしません。そして、何故か隙をついて、魚のヒレや鱗をかじり取って、食べてしまうのです。これは、ホンソメワケベラに似ているニセクロスジギンポ(スズキ目イソギンポ科)という魚です。この魚はホンソメワケベラになりすまし、魚をクリーニングすると見せかけて、だまされてしまった魚のヒレや皮膚等を食べてしまう「海の詐欺師」なのです。よく似ている2種類の魚ですが、見分けるコツがあるのです。口の付き方に注目してごらんなさい。ホンソメワケベラの口は頭部の正面、ニセクロスジギンポの口は頭部の下側に付いています。
 水槽を群れで泳ぐキンメモドキ。群れている事によって身を守っています。群れでいると逆に天敵に存在をアピールしているようで危険すぎるかもしれませんが、小魚には、隣の魚と同じ方向を向く習性があります。1匹が動き出せば、群れ全体も動き出すので、敵を翻弄出来るという訳。イワシやニシンも、こんな大きな群れを作ります。
水槽を群れで泳ぐキンメモドキ。群れている事によって身を守っています。群れでいると逆に天敵に存在をアピールしているようで危険すぎるかもしれませんが、小魚には、隣の魚と同じ方向を向く習性があります。1匹が動き出せば、群れ全体も動き出すので、敵を翻弄出来るという訳。イワシやニシンも、こんな大きな群れを作ります。

 ツバクロエイ(左)とシマウシノシタ(右)
ツバクロエイ(左)とシマウシノシタ(右)
 イヌの「チン(狆)」に似た顔から名付けられたチンアナゴ。砂地から上半身を出して、プランクトンを食べています。
イヌの「チン(狆)」に似た顔から名付けられたチンアナゴ。砂地から上半身を出して、プランクトンを食べています。
 綺麗な姿と、大きな胸ビレが目立つミノカサゴ。ただ、ヒレのトゲに毒針を持っているので、見かけても決して触らないように!
綺麗な姿と、大きな胸ビレが目立つミノカサゴ。ただ、ヒレのトゲに毒針を持っているので、見かけても決して触らないように!
 トラギスは、砂地をピョコピョコ、這うように泳ぎます。
トラギスは、砂地をピョコピョコ、這うように泳ぎます。
 ハコフグの仲間は、体が頑丈な板状の骨(骨板)で覆われています。箱型は種類ごとに違っています。
ハコフグの仲間は、体が頑丈な板状の骨(骨板)で覆われています。箱型は種類ごとに違っています。



