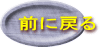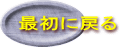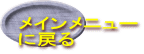JR東日本の主力形式で、2000番代以外は車体の幅を広げて座席数を増やす等、より多くの人が乗れるような工夫を凝らしています。まずは0番代が2006年に中央線快速系統で運転を開始、その翌年の2007年には1000番代が、京浜東北・根岸線での運転を開始しました。2009年には東京メトロ千代田線への乗り入れに対応した2000番代、2010年京葉線の5000番代、2013年埼京線7000番代、2014年横浜線6000番代と南武線8000番代が、それぞれデビューしました。また、2008年からは近郊タイプも登場しています。2016年での時点で、在籍両数は3197両となっており、在籍両数はE231系を上回っています。いずれもWebページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:中央線、青梅線、京浜東北・根岸線、常磐緩行線、京葉線、埼京線、横浜線、南武線、東北本線(宇都宮線)、高崎線、上野東京ライン、湘南新宿ライン
ヒミツ情報:青梅線の一部の区間には中央線快速電車も乗り入れるためか、青梅線の電車は中央線と同じオレンジ色のライン。

中央線、青梅線を走っている0番代。ラインはオレンジです。色の違いで一目で分かるって、便利ですね。

京浜東北・根岸線を走る1000番代。根岸線は京浜東北線の一部分でもあるため、2つまとめて「京浜東北・根岸線」とも呼ばれます。

埼京線で走っている7000番代。ラインの色は、山手線のよりも濃い緑色になっていますね。埼京線は、東京臨海高速鉄道りんかい線や、相鉄本線とも相互直通運転を行っています。川越線にも乗り入れて走っています。

横浜線で走っているE233系。6000番代で、ラインの色は緑色ですが、よく見ると、緑色の上に黄緑色のラインがあるのが分かりますね。

近郊タイプのE233系。東海道線や高崎線、宇都宮線、湘南新宿ラインや上野東京ライン、上越線、両毛線と、色々な路線で活躍しています。

南武線で走っているE233系。2014年から8000番代が、2017年から8500番代が運用に入っています。
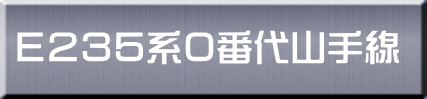
2015年に山手線に投入された車両で、車体はE233系と同様、軽量ステンレス製となっています。総合車両製作所が開発した次世代ステンレス車両「sustina」を採用しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:山手線
ヒミツ情報:後部先頭車両には、月替わりでイラストが表示される。


2020年には、横須賀・総武快速線にもE235系が走り始めました。山手線のE235系は0番代ですが、こちらは1000番代となっています。編成はこの後紹介するE217系と同様、基本編成11両と付属編成4両となり、基本編成のうち2両は2階建てグリーン車になっています。塗装は山手線の車両とは異なり、ホームドアの未整備駅が多くある路線を走る為分かりやすさを考え、従来車のE217系と大きくカラーリングは変更せず横帯としています。横須賀線は海の近くを走るので、ラインは海をイメージした青色、そして砂浜をイメージしたクリーム色となっています。横須賀・総武快速線と成田線をつないで、成田空港へも乗り入れていますよ。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:横須賀・総武快速線、成田線、外房線、内房線、総武本線、鹿島線
ヒミツ情報:常に車両の搭載機器や架線・路線の状態監視を行うモニタリング技術を初めて採用。実は山手線のE235系にも、お客さんを乗せながら線路の検査を行える「線路設備モニタリング装置」が4号車に搭載されている編成があるのだ。


横須賀・総武快速線で運用されていた113系の置き換え用として、1994年にデビューした近郊型電車です。国鉄・JRでは初の4扉構造を採用しました。車内の座席配置は混雑緩和を最優先とし、通勤型となるロングシート構造を基本としつつ、基本編成11両中3両は遠距離旅客や観光客にも配慮して、クロスシートを設けたセミクロスシートとなっています。先に紹介したE235系が横須賀・総武快速線で走り始めてからは、順次置き換えも進んでいるようです。前面を仕上げるコツは「私鉄特急」エリアのミュースカイや特別車特急、先に紹介したキハ110系陸羽西線「奥の細道」と同じで、ちょっと曲げくせをつけておくといいでしょう。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:横須賀・総武快速線、総武本線、成田線、鹿島線、内房線、外房線
ヒミツ情報:東海道線でもE217系は走っていたが、2015年のダイヤ改正により営業運転を終了してしまっている。


常磐線を走っている通勤型電車。415系に替わる中距離電車として、2005年にデビューし、その翌年に2階建てのグリーン車を組み込みました。2015年度には、準耐寒耐雪仕様の3000番代を導入し、415系の置き換えを完了しました。常磐線は日暮里と岩沼を結ぶ、343.7kmに及ぶ長い路線で、その中でも東京に近い部分は通勤路線となっています。初心者向けの簡単な作品です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:常磐線
ヒミツ情報:E231系に改良を加えて誕生し、JR東日本の通勤列車では初めて、最高時速130kmでの運転を開始した。


オレンジと緑のツートンカラーが特徴の113系です。最近この色は見かけませんが、113系自体は今でも現役で走っています。細かい部品が多いので、粘り強く作っていって下さい。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
現在走っている路線:草津線、湖西線、山陽本線、呉線等


113系と同じく、国鉄世代の近郊型電車です。この作品は湘南色の電車ですが、現在では主に岡山・広島地区の山陽本線で活躍しています。「Vayashi’s11」収録作品。
現在走っている路線:両毛線、山陽本線等
ヒミツ情報:先頭車化改造により、異端な面構えの車両もある。


東海道線の東京~熱海間を走る「快速アクティー」「湘南ライナー」の2つの快速列車に使われる2階建て車両です。4、5号車はグリーン車で、普通車はボックス席となっています。最終運用は「湘南ライナー」「おはようライナー新宿」、「ホームライナー小田原」でしたが、2021年3月にそれらが廃止されると運転を終了しました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:東海道本線(東京~熱海)
ヒミツ情報:両先頭車両の1階は機器室。


1985年から1994年にかけて、1461両が製造された通勤型電車で、山手線や埼京線などでも見られました。インドネシアに譲渡されて活躍している車両もあります。全てWebページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:仙石線、奈良線。かつては山手線、埼京線、京浜東北線、南武線、武蔵野線等でも見られた
 南武線で2016年まで走っていた205系。
南武線で2016年まで走っていた205系。 武蔵野線で走っていた205系。2020年まで走り続け、後にインドネシアへ譲渡されました。
武蔵野線で走っていた205系。2020年まで走り続け、後にインドネシアへ譲渡されました。 八高川越線のうち、電化されている八王子~高麗川間を走っていた205系です。
八高川越線のうち、電化されている八王子~高麗川間を走っていた205系です。 相模線で走っていた205系。500番代と呼ばれるもので、新造編成としては最後の205系になります。
相模線で走っていた205系。500番代と呼ばれるもので、新造編成としては最後の205系になります。
東海道線の普通用電車です。国鉄世代の1986年度に、セミクロスシート車の0番代が登場、JR発足後の1988~1990年度に3両、4両編成の5000番代とIM方式で2両編成の6000番代が、いずれもロングシートで投入されました。軽量ステンレス製で、省エネ性能に優れた車両です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:東海道本線(熱海~米原)、中央本線、両毛線等


JR東海では飯田線と中央本線のうち茅野~辰野間、JR西日本では山陽本線の吉永~三原間や伯備線の倉敷~新見間、赤穂線の東岡山~播州赤穂、本四備讃線(瀬戸大橋線)の茶屋町~児島間、宇野線で普通列車として走っています。JR西日本のものは0番台で、かつては瀬戸大橋を渡って岡山から高松を結ぶ「マリンライナー」にも使われていました。JR東海のものは5000番台です。国鉄形の車両ですが、5000番台の落成は国鉄が民営化されてJRになってからでした。211系によく似ていますが、ドアは片側2つです。いずれもWebページ「ぺパるネット」収録作品。
走っている路線:飯田線、中央本線(茅野~辰野)、山陽本線(吉永~三原)、伯備線(倉敷~新見)、赤穂線(東岡山~播州赤穂)、本四備讃線(茶屋町~児島)、宇野線
 JR東海が所有する5000番台
JR東海が所有する5000番台 JR西日本の0番台
JR西日本の0番台 高松側の先頭車両がパノラマグリーン車となっている、213系の快速「マリンライナー」。
高松側の先頭車両がパノラマグリーン車となっている、213系の快速「マリンライナー」。
東海道本線(熱海~米原)の新快速用に登場した車両で、1989年に営業運転を開始しました。最高時速120kmでの運転を行うために、ブレーキ力を強化し、台車にヨーダンパを取り付けました。座席は転換式クロスシートです。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:東海道本線(熱海~米原)


313系はJR東海の主力電車。1999年に登場したVVVFインバータ制御車で、最初の登場は転換式クロスシートの4両編成0番代と3両編成1500番代です。東海道本線(熱海~米原)や篠ノ井線、武豊線と、幹線からローカル線まで幅広い分野で活躍しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:東海道本線(熱海~米原)、篠ノ井線、武豊線、飯田線等
ヒミツ情報:JR東海の新快速と、JR西日本の新快速では、英語の言い方が違う。


色は違いますが、先ほどと同じ313系です。中央本線の座席定員制列車「セントラルライナー」用の3両編成となっています。中央本線の快速や普通でも運用されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:中央本線
ヒミツ情報:313系で唯一最高時速130km運転を、2007年より実施している。


2021年から製造が開始され、2022年より中央本線で営業運転を開始した、JR東海の最新型車両です。313系や211系、311系は近郊型でしたが、この315系は通勤型の電車。省エネ化が進み、バリアフリー設備も充実しています。2024年から、東海道本線名古屋地区と武豊線でも走り始めました。この電車は2025年度までに製造される予定で、これによって211系等の国鉄形車両を置き換える予定です。4両編成の315系もあり、こちらは2023年6月1日から、関西本線の名古屋~亀山間で営業運転を開始しました。万が一停電が起きても蓄電池の力で一番近くの駅まで走行出来るようになっています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:中央本線、東海道本線(熱海~米原)、関西本線、武豊線


飯田線で313系や213系が走り始める前、飯田線で活躍していた電車で、1982年に登場しました。中国地方の電化ローカル線の旧型国電置き換え用として先んじて登場していた105系をベースとした設計になっており、105系の特徴である高速性能よりも加速性能を重視した走行特性と、短い編成を組むのに適した機器構成を保ちつつも、連続急勾配を登る為の設備を付け加え、車内設備も長時間の乗車に適したものとしました。特殊な性格を持つ飯田線運用での最適化を図ったもので、特定のローカル線での運用を主眼として開発されており、その点では国鉄世代の電車の中でも、極めて特異な存在であるといえます。また製造コストの低減の為、全体に簡素な構造を採用しており、走行機器や内装部品等の一部には廃車発生部品を再利用しています。2012年の3月に引退していますが、引退の日には登場時の塗装の編成を使用した臨時列車も運転されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っていた路線:飯田線
ヒミツ情報:一部が福井県のえちぜん鉄道に譲渡され、MC7000形として走っている。
 左側の青いほうが登場時の塗装を復元した編成。
左側の青いほうが登場時の塗装を復元した編成。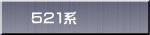
JR西日本として初めて新造した近郊型電車です。北陸本線の長浜~敦賀間、湖西線永原~近江今津間が、関西方面との直通運転強化のため、交流から直流に変更された事を受けて登場しました。2006年より、北陸本線の米原~福井間、湖西線の近江今津~近江塩津間で営業運転に入っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:北陸本線(米原~福井)、湖西線(近江今津~近江塩津)

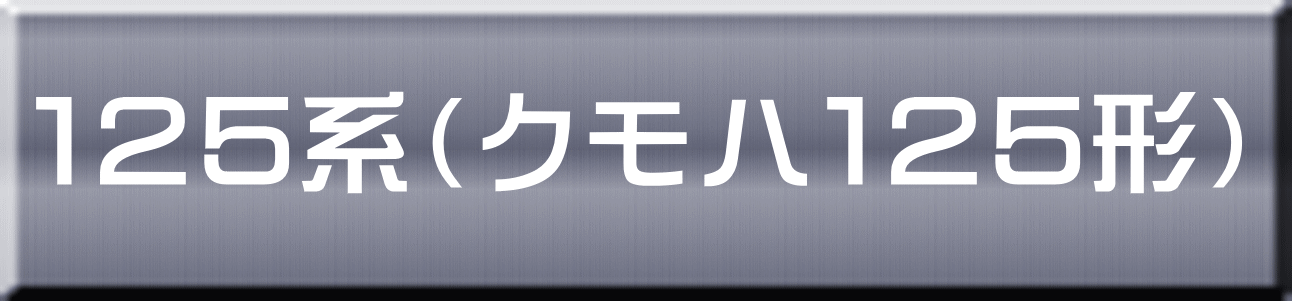
1両での単行運転が可能可能な両運転台付きの電車で、2003年の小浜線直流電化開業に合わせてデビューしました。VVVFインバータ制御装置は、補助電源と一体化した2レベル電圧形PWM方式で、主電動機を2基搭載しています。組み立てた後、パンタグラフの部分の裏側をボンドとかで留めておくと形が保てます。細かい部品が多いので落ち着いて作りましょう。Webページ「JR西日本:人気列車ペーパークラフトコーナー」収録作品。
走っている路線:小浜線、加古川線