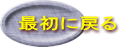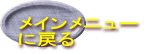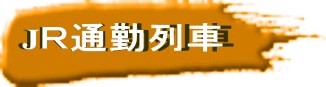
大きな町と町を結ぶ幹線から、地方の町を走るローカル線まで、JRには色々な種類の通勤列車が走っています。沢山覚えて列車博士になりましょう。

「快速エアポート」は、新千歳空港と小樽、札幌等、北海道の大きな町を結んでいる空港連絡快速列車。733系はJR北海道が2012年に導入した通勤型電車で、731系の設計コンセプトを基本に、その後の新技術導入、ユニバーサルデザイン・バリアフリー対応の要求を満たすべく、仕様の変更も行われています。見た目は基本番代・3000番代共に見た感じ違いが見受けられませんが、基本番代は3両編成で、札幌近郊の普通列車に使用されています。3000番代は6両編成で、「uシート」となる付随車のサハ733(3200番代)も組み込まれています。Webページ「Vayashi‘s11」収録作品。
走っている路線:函館本線・千歳線
ヒミツ情報:「快速エアポート」は種別上は快速となるのだが、2020年3月14日のダイヤ改正より、混雑緩和を目的として朝夕に特別快速の列車も設定された。

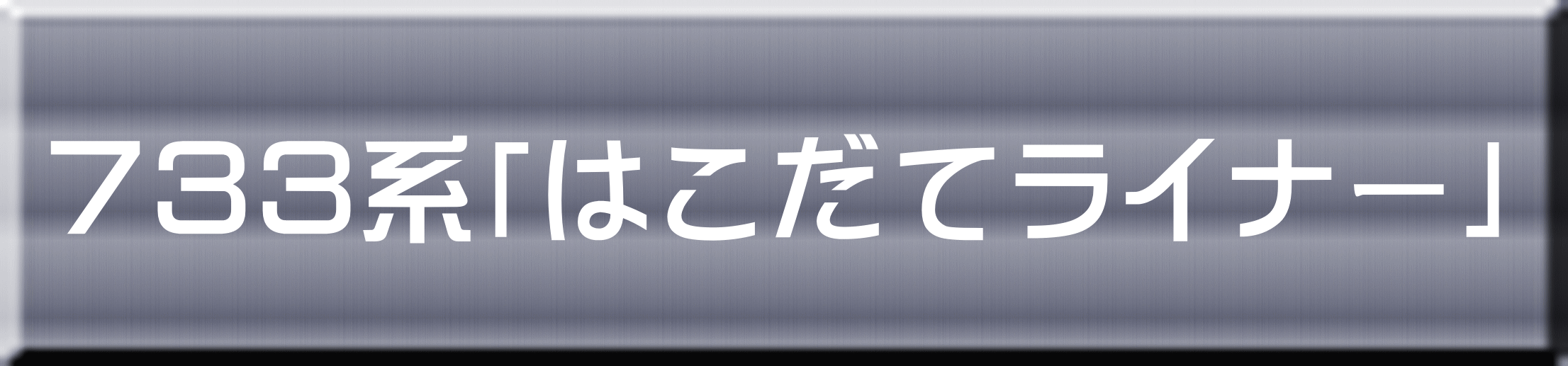
「はこだてライナー」は、函館本線の函館駅~新函館北斗駅間で運転している快速列車で、733系のうち1000番代が使用されています。先程の「快速エアポート」用3000番代の帯は緑色なのですが、こちらは紫色の帯となっています。2016年の北海道新幹線開業に合わせてデビューした列車で、新幹線接続も行います(但し朝の上り始発列車と深夜の下り最終列車は除く)。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:函館本線


1996年より営業運転を開始しました。JR北海道の通勤型電車で、函館本線や千歳線等で走っています。客用扉は721系と同じく片側3ヶ所ですが、オールロングシートを採用しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。なお、この写真は「ゴー!ゴー!キッチン戦隊クックルン」公式サイトに投稿するおたよりと同封する車両図鑑の為に撮影したもので、同じく僕が撮影したクックルンジオラマ写真に使用した車両の1つでもあります。
走っている路線:函館本線・千歳線、室蘭本線等
ヒミツ情報:キハ201形との併結運転をする事があるが、電車と気動車がつながって走るのは小樽~札幌のみ。

 731系を使って僕が撮影したクックルンジオラマ写真。改めてここで紹介させて頂きます。本棚の下の部分を空けて配置して撮影したら、地下鉄みたいになりました。この写真には、もう一つ別の列車が写っているのですが、分かりますか?(答えはこのページの下)
731系を使って僕が撮影したクックルンジオラマ写真。改めてここで紹介させて頂きます。本棚の下の部分を空けて配置して撮影したら、地下鉄みたいになりました。この写真には、もう一つ別の列車が写っているのですが、分かりますか?(答えはこのページの下)
こちらもJR北海道の通勤型電車。3両編成ですが、6両編成が走る事もあります。6両編成の電車には「uシート」があり、快速「エアポート」に充当されています。3両編成の電車は、小樽~滝川間、千歳線を中心に運転されています。135両が在籍しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:函館本線・千歳線等


1967年に製造が開始された、日本初の量産交流近郊型電車。初の北海道向け国鉄電車でもあり、内外共に耐寒耐雪への装備も徹底しています。以降に登場した721系や731系といったJR北海道を走る電車の基礎となった電車で、函館本線や千歳線、室蘭本線の普通列車や快速列車で運転されました。「北海道の赤い電車」として長きにわたり親しまれてきましたが、2015年に運用終了となってしまいました。写真を見て分かるように、冷房車の空調設備は他の711系と異なります。3作品ともWebページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っていた路線:函館本線、千歳線、室蘭本線
 一番左は旧塗装の車両、真ん中は冷房車。
一番左は旧塗装の車両、真ん中は冷房車。
札幌都市圏の通勤・通学輸送用に投入された気動車で、1997年に営業運転を開始しました。車体も731系に準拠した軽量ステンレス製になっています。小樽~札幌間では、731系とつながって走る事もあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:函館本線等
ヒミツ情報:データイムには、ほしみ~江別間でも走っている。


国鉄が開発した気動車です。全国の非電化区間に導入され、北海道には気象条件を踏まえた、極耐寒耐雪の100番代が150両配置されました。また、JR北海道発足後には、ワンマン運転機器を搭載して700番代、エンジンを換装したものは1700番代となりました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:室蘭本線、釧網本線、日高本線、石勝線等


キハ54形は1986年に製造された一般形気動車で、JR北海道のキハ54形とJR四国のキハ54形では窓や座席のタイプが異なります。これはJR北海道のキハ54形で、500番台と呼ばれるタイプです。JR北海道のキハ54形は座席がセミクロスシートで、また、随所耐雪、凍結対策も実施されています。エゾシカのような野生動物とぶつかるのを防ぐ為、警笛は在来車同様のタイフォンから「鹿笛」と呼ばれる甲高い音色のものに交換されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:宗谷本線、留萌本線、函館本線(旭川~滝川)、石北本線、釧網本線、根室本線(釧路~根室)

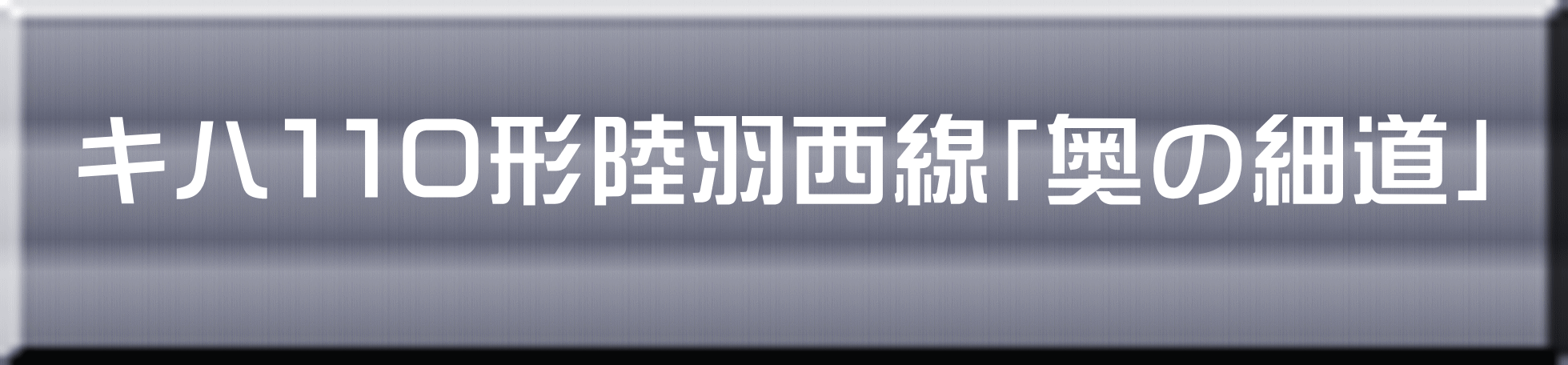
山形新幹線の終点・新庄から日本海側の町を結ぶローカル線・陸羽西線。景色が綺麗な路線として有名で、俳人・松尾芭蕉が最上川を旅した時の様子を「奥の細道」という随筆に書いている事から、最上川沿いを走る陸羽西線は、「奥の細道最上川ライン」と呼ばれます。走っている車両は、このキハ110形です。先端部の仕上げは、「私鉄特急」エリアに登場している「ミュースカイ」「特別車特急2種」と同じ感じでしょう。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:陸羽西線、陸羽東線等
ヒミツ情報:運が良ければ列車の窓から川下りが見られるかも!?


205系は、1985年に登場した通勤型電車です。かつては山手線や埼京線、京浜東北・根岸線等でもその姿が見られました。ここで紹介するのは、2002年~2004年にかけて103系を置き換える為に導入された205系です。4両編成17本が配置されており、あおば通~石巻間の普通電車として走っている車両で、予めトイレの設置改造等が行われた上で投入されました。車体のラインカラーは、オールロングシート車両では青系の2色なのに対し、クロスシートとロングシートの切り替えが可能な「2WAYシート組み込み車」は各車両ごとにラインカラーが異なる他、沿線の観光地をイメージしたロゴマークが貼られています。Webページ「Vayashi‘s11」収録作品。
走っている路線:仙石線
ヒミツ情報:仙石東北ラインの開業に伴い仙石線の快速列車が廃止となった為、2WAYシートは2015年以降ロングシートに固定されており、連結面寄りは車椅子スペースとトイレを設置した為座席は無くなった。

 2WAYシート車
2WAYシート車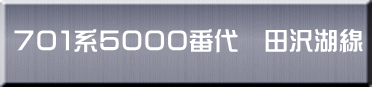
東北地方の普通列車に使用されていた50系・12系客車の置き換え用として、1993年に登場しました。車体はステンレス製で、客用扉は片側3ヶ所、座席もロングシートとなっています。5000番代は、秋田新幹線の開業に伴い標準軌化された田沢湖線の普通列車用として1997年に投入されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:田沢湖線
ヒミツ情報:5000番代はロングシートとボックスシートを点対称に配置したセミクロスシート車。


JR東日本の交流型近郊電車です。基本は2両編成ですが、それを組み合わせて4両、6両、8両といった編成で走る事が出来ます。かつては仙山線や磐越西線、東北本線でも見る事が出来ましたが、E721系等後継車の登場、ダイヤ改正等で運用を終了しています。現在は奥羽本線でのみ走っていますが、それが山形新幹線の運転開始に伴いデビューした標準軌用の5000番台です。奥羽本線のうち山形線と呼ばれる福島~新庄間の普通列車として走っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
走っている路線:奥羽本線(山形線)


首都圏の多数の路線に投入された、JR東日本の代表的な通勤列車です。0番代は2000年に中央・総武緩行線、2002年に常磐線快速に投入され、その1ケ月後には山手線にも500番代が投入されましたが、1999年より中央・総武緩行線各駅停車用として試作車の209系950番代が元祖となっています。2003年に東京メトロ東西線に乗り入れを行う800番代が、中央・総武緩行線の各駅停車となっています。ここまでのは通勤タイプで、2000年から近郊タイプが東北本線で運転を開始。2001年、湘南新宿ラインが開通すると、東海道本線や横須賀線にも進出しました。2004年に2階建てのグリーン車を連結しての本運転を開始、最長15両編成での運転を行っています。
走っている路線:中央・総武緩行線、常磐線、成田線、東海道本線、高崎線、宇都宮線、八高・川越線

山手線の500番代。山手線は環状線に思われがちですが、正確な区間は品川~田端間です。山手線のE231系は、2020年に営業運転を終了しました。Webページ「ぺパるネット」収録作品。

中央・総武緩行線のE231系。山手線は黄緑色のラインですが、中央・総武緩行線の電車は黄色いライン。このように、ラインの色が違うと、乗り間違える事も無いし、一目で分かりますね。左の線路にいるのは元山手線の500番代、右側が0番代です。2作品ともWebページ「Vayashi’s11」収録作品。

常磐線快速として走っている0番台です。Webページ「ぺパるネット」収録作品。

近郊タイプのE231系は、2階建てのグリーン車を連結していますが、ラッシュ時には15両編成も満員になります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

地下鉄に乗り入れる800番台には、非常脱出用貫通扉が装備されています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

八高線は、八王子と倉賀野を結ぶ路線ですが、高麗川を境に電車の走る「電化区間」と、ディーゼル列車が走る「非電化区間」に分かれています。これは電化区間を走っている3000番代で、中央・総武緩行線で走っていた車両です。川越線でも走っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

日本国有鉄道(国鉄)から大量に引き継ぎ老朽化が進んだ103系の置き換えの為に投入された通勤型電車です。1993年に京浜東北線・根岸線、南武線に本格投入されました。設計段階より廃車後のリサイクルが計画される等、環境問題にも配慮した電車で、JR東日本の通勤型電車の基礎となった、優秀な車両です。0番代は京浜東北線用に導入され、後に南武線へと転用されましたが、京浜東北線・南武線共に営業運転は終了しています。八高川越線では3500番代、3100番代が走っており、3000番代は2019年に運転を終了しました。中央・総武線系統、京葉線系統、武蔵野線系統、中央線快速と幅広く活躍するのは500番代。2000番代や2100番代は、内房線や外房線、東金線、成田線、鹿島線で走っています。いずれもWebページ「Vayashi‘s11」収録作品。
走っている路線:八高川越線、中央・総武線系統、京葉線、武蔵野線、中央線快速、内房線、外房線、東金線、成田線、鹿島線
ヒミツ情報:2200番代の1編成が、ジョイフルトレイン「BOSO BICYCLE BESE」となって走っているぞ。何と、「電車そのものを『サイクリングの基地』にしよう」というコンセプトになっているのだ!
 房総色の車両
房総色の車両 かつて八高川越線を走っていた3000番代
かつて八高川越線を走っていた3000番代 武蔵野線で走っている車両
武蔵野線で走っている車両(731系クックルンジオラマの答え)
001系「Laview」→「私鉄特急」参照