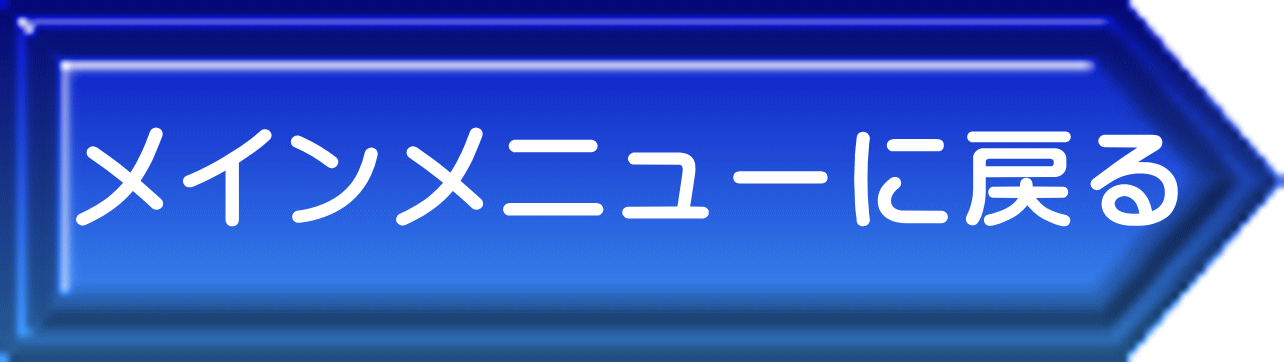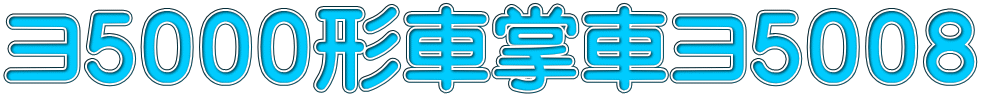
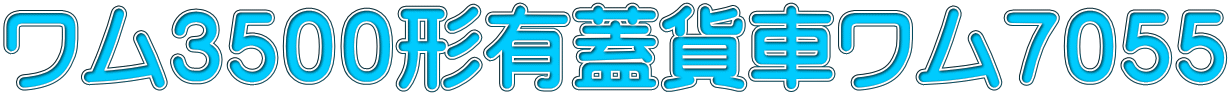

 ヨ5000形車掌車ヨ5008
ヨ5000形車掌車ヨ5008
 ワム3500形有蓋貨車ワム7055
ワム3500形有蓋貨車ワム7055ヨ5000形は、戦後、標準型車掌車として大量生産されたヨ3500形の走り装置を1段リンク式から2段リンク式に改良し、最高速度を時速75kmから時速85kmに向上させた車両です。ヨ3500の改良型車両と、最初から2段リンク式で新製した車両とがあります。当初、コンテナ特急「たから」用に登場した為、車体色は当時の国鉄コンテナと同じ黄緑色でしたが、1962(昭和37)年新製分からは貨車標準の黒色となりました。現在の貨物列車では、原則として車掌は乗務しませんが、かつての貨物列車においては、車掌車または緩急車(車掌室を備えた貨車)に車掌が乗務し、貨車の監視や必要に応じて非常ブレーキ操作、列車防護作業等、列車運転に必要な業務を行っていました。ヨ5008号は1959年に登場し、引退後はJR貨物が保管していましたが、京都鉄道博物館開業にあたり、記念コンテナ等と共に譲り受けました。汐留貨物駅(東京都)と梅田貨物駅(大阪市)を結ぶ日本初のコンテナ列車「たから号」使用当時の黄緑色に復元されています。なお、記念コンテナは、JR貨物が1999(平成11)年に鉄道コンテナ50周年を記念して50個限定で製作した、黄緑色の19Dコンテナと同等の新製コンテナです。展示用に製作されたものですが、営業用と同等に「19D-28901」という番号が付けられています。
ワム3500形は1917(大正6)~1925年に製造された木製の15t積み有蓋貨車です。新製時の形式はワム32000でしたが、1928(昭和3)年の称号規則改定によりワム3500形となりました。汎用の有蓋貨車として全国で使用され、1万1873両が製造されました。現在のJRでは、一部を除き貨物はコンテナ輸送となっていますが、以前は運ぶ貨物の種類によって、屋根のある「有蓋貨車」、屋根の無い「無蓋貨車」、液体を運ぶタンクを台枠に固定した「タンク貨車」、粉や粒状の物資を積載し取り卸し用の落とし口(ホッパ)を備えたホッパ車等があります。中でも汎用の有蓋貨車は、様々な種類の貨物を運ぶ事が出来る為重宝され、国鉄貨車の代表格でした。本形式は、1915(大正4)年に日本初の15t積み有蓋貨車として登場したワム23000形(後のワム1形)の車軸を長軸に変更した車両で、鋼製台枠の上に溝形鋼による鋼製柱で車体骨格を形成し、木製側板と鋼製側扉という車体構造は引き継ぎました。長軸とした事で軌間を広げる事が容易になり、当時検討されていた1067mmから欧米並の1435mmに改軌する事になった場合の準備でした。この構造を活かし、陸軍要請により中国向けに製造された車両もあります。ワム7055は製造初年の1917(大正6)年製。木製貨車が営業に使われなくなった後も、吹田市にあった関西鉄道学園の教材となった為、貴重な大正生まれの貨車が生き残りました。