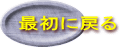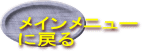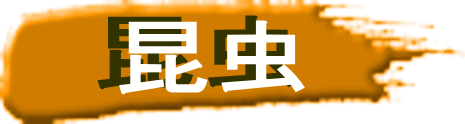
折り紙の「昆虫」エリアでは折り紙で折った昆虫を紹介していますが、ここで紹介しているのはペーパークラフトの昆虫です。ハサミが要らず、抜き取って作れる作品が多いですが、細い部分とかは切れやすいので、慎重に抜き取りましょう。なお、カブトムシやクワガタムシはオスの体長を示しています。(カブトムシ[メス]を除く)
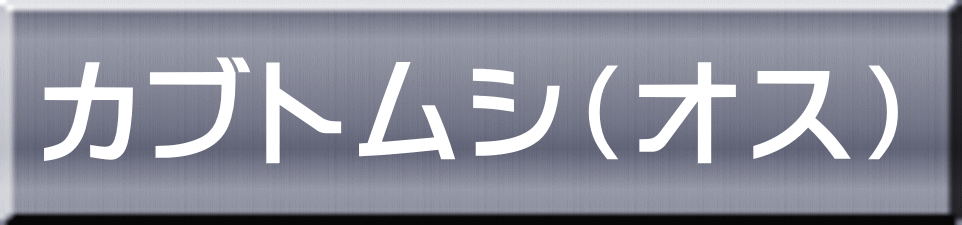
カブトムシはコガネムシ科の甲虫で、クヌギやコナラの樹液や熟した果実に集まります。オスの角を入れた全長は、最大で85mmにもなります。樹液に集まる虫の中でも力が強いので、一番いい場所を独占出来ます。沖縄のカブトムシは、角が小さく、オキナワカブトという亜種になります。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:27~55.6mm
成虫が見られる時期:6~9月
分布:アジアの国々(日本では北海道から九州、屋久島、奄美大島、沖縄)
ヒミツ情報:北海道には元々いなかったが、人の手によって入ってきたらしい。

「りったい昆虫館」収録作品。角とお尻は糊付けします。

「新りったい昆虫館」収録作品。角やお尻も差し込んで留めるのが、上のカブトムシとの違いです。

日本にいるクワガタムシの中でも大型の種類です。樹液に集まり、昼間は木の隙間等に隠れています。大変臆病な性格の持ち主です。中国にはホペイオオクワガタがいます。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:27~77mm
成虫が見られる時期:5~9月
分布:日本、中国、朝鮮半島
ヒミツ情報:飼育下では8cmを超える個体も羽化している。

「りったい昆虫館」収録作品。オオクワガタにしては立体的で、アゴの形状で僕には同じオオクワガタの仲間で、インドやタイ、マレーシア等にいるアンタエウスオオクワガタに見えてきました。

「新りったい昆虫館」収録作品。さっきのよりオオクワガタらしく感じたのは、僕の気のせいでしょうか?
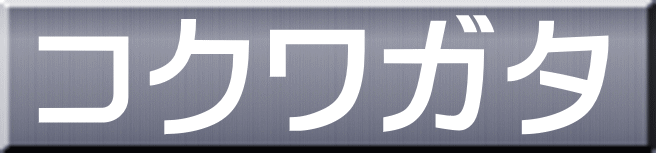
僕がよく見かけるクワガタムシで、北海道から九州までは最も普通に見られるクワガタムシです。真っ直ぐ伸びた大アゴの真ん中に内歯が1対生えていますが、小さいと内歯も目立ちません。僕の近所では、多いと大きな個体が数匹は取れます。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:17.8~54.4mm
成虫が見られる時期:5~9月
分布:北海道~南西諸島(トカラ列島以北)

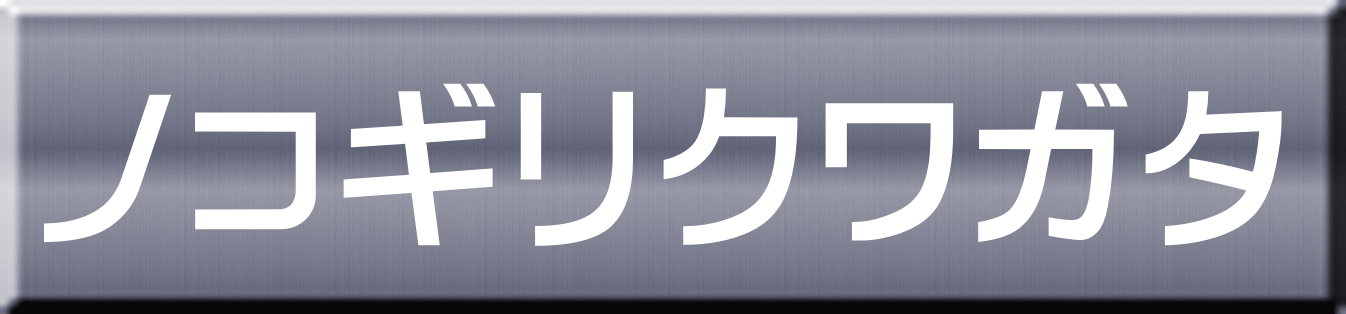
水牛の角のように立派に湾曲した大アゴが魅力の、日本産のクワガタムシです。クヌギやコナラ、ヤナギ等の樹液や、熟した桃にも集まります。幼虫は地中の朽木を食べて成長します。日本産のノコギリクワガタの仲間には、アマミノコギリクワガタ、ヤエヤマノコギリクワガタ、ハチジョウノコギリクワガタ、クロシマノコギリクワガタがいます。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:25.8~74.7mm
成虫が見られる時期:6~9月
分布:北海道~九州、種子島、屋久島
ヒミツ情報:小型のオスは大顎の内歯も目立たず真っ直ぐ。

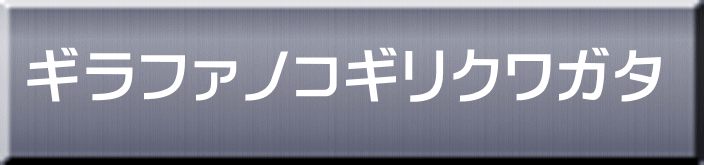
ギラファノコギリクワガタは世界最大・最長のクワガタムシ。ギラファとはキリンの事で、長い大顎をキリンの首に見立てて付けられたのでしょう。地域によって大アゴの形に差があり、フローレス島のフローレスギラファノコギリクワガタが最大で、120mmにまで成長するそうです。一見強そうですが、アゴが長いので、見た目程挟む力は強くありません。昔の図鑑では「キバナガノコギリクワガタ」とか表記されていました。アゴは左右に動かす事が可能だと思います。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:45~118mm
分布:インドからマレー半島、インドネシア、フィリピン
ヒミツ情報:「ワニノコギリクワガタ」とも呼ばれている。

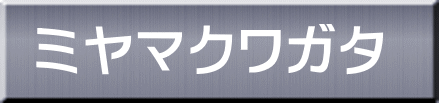
大型のオスは頭部の両側が張り出し、兜のように見えます。ミヤマは漢字で「深山」と書く為、山深くに行かないと見られないと思われがちですが、実際には雑木林があればどこでも見られます。怒ると体を反り返らせて威嚇のポーズを取ります。幼虫は地中で朽木を食べて成長します。根元の内歯が大きいものは「富士型」、内歯が小さいものは「蝦夷型」と呼ばれます。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:31.5~78.6mm
分布:北海道~九州、シベリアの一部も含むユーラシア大陸
ヒミツ情報:ミヤマクワガタがいる所ではノコギリクワガタが少ない事が多い。


中南米の竹林に暮らすカブトムシです。前肢が異様に長く、持て余してしまうのかと思ったら大間違い。竹は足場が悪い為、オス同士戦う時は前肢を振り回します。但し、それでも勝負がつかないと角まで使います。「ゴロファ・ポルテリ」とか「ポルテリィタテヅノカブト」と呼ばれる事もあります。竹の樹液を吸っています。角の付け位置に気をつけて下さい。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:40~84mm
分布:グアテマラ、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル


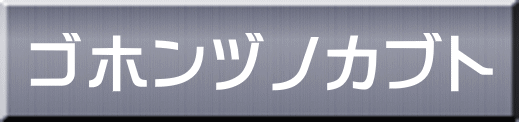
これも竹の樹液を吸うカブトムシですが、インドや東南アジア、中国に生息します。生きている時の前翅は美しいクリーム色です。角が5本もありいかにも強そうに見えますが、実際には大人しく、あまり好戦的では無いようです。明かりにも集まります。本体(肢)はこの後登場するモーレンカンプオオカブトの本体(肢)と一緒に載っていますので、間違えないで下さい。「りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:45~86mm
分布:インドから中国にかけて分布


言わずと知れた世界最大のカブトムシ。大きいものは18cmにも達します。真っ直ぐ伸びた2本の角が、一番の特徴。標高1000m位の森に棲み、幼虫は朽ちた木や腐葉土を食べて育ちます。また、甲虫は1ケ月の短命が多い中、ヘラクレスは1年近く生きるそうです。胸角には毛が生えているのもポイントです。本種のヘラクレスの他にもヘラクレス・リッキーやヘラクレス・オキシデンタリス、ヘラクレス・エクアトリアヌス、ヘラクレス・モリシマイ、ヘラクレス・レイディ等、色々な亜種がいます。
分類:甲虫目コガネムシ科
体長:46~178mm
分布:中央アメリカ~南アメリカ中部
ヒミツ情報:前翅は乾燥している時は黄色い色だが、湿り気があると黒っぽくなる。

「りったい昆虫館」収録作品。これはヘラクレス・ヘラクレスだと思います。

「新りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。カッコよく飛んでいる姿にもチャレンジしてみて下さい。細かい箇所があるので、慎重に作って下さいね。