
アフリカに暮らしているクワガタムシで、オスは頭楯に相当する辺りが大きく衝立状に出っ張っています。この衝立上の出っ張りは、オス同士が戦う際に防具の役割を果たします。体色も黄褐色で、太陽光線に含まれる熱線を吸収する為の進化の結果ともいわれています。幼虫は蛹になる際に蛹室は作らず、土繭を作りその中で蛹化します。メンガタクワガタの仲間には他にグラディアトールメンガタクワガタというのもいます。衝立上の出っ張りは糊付けして組み立てます。最後は完成写真や図鑑を見て仕上げてください。「新りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:26~55mm
分布:アフリカ中部~西部

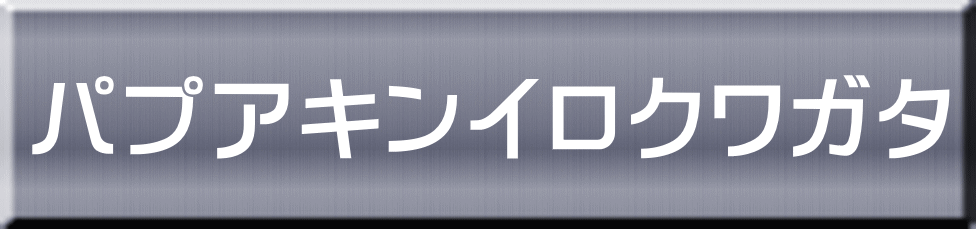
ニューギニア島に暮らしているクワガタムシで、体色は緑だったり青だったり、見る角度によって違って見える他、個体により様々な色で着飾っています。オス、メス共に金属光沢があるのも特徴です。主に昼間活動し、ベニバナボロギクという植物の汁を吸って暮らしています。オスの前肢には扇形の突起があり、これを鋸のように使って茎を切り取り、そこからしみ出てくる汁を吸います。因みにメスにはその鋸が無い為、オスから草の汁を分けてもらっているようです。大顎は上向きに反り返っていて、ケンカの時だけでなく、前肢の鋸でベニバナボロギクの茎を切断する際、この大顎を使いますが、驚くべき事に茎を0.37mmもの薄さにスライス出来るんだそう。これは草の汁を、余すところ無く吸えるからなんですね。「新りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:24~50mm
分布:ニューギニア島
ヒミツ情報:原産地ではおやつとして、肢と翅を取り除き腹部を食用にされる。

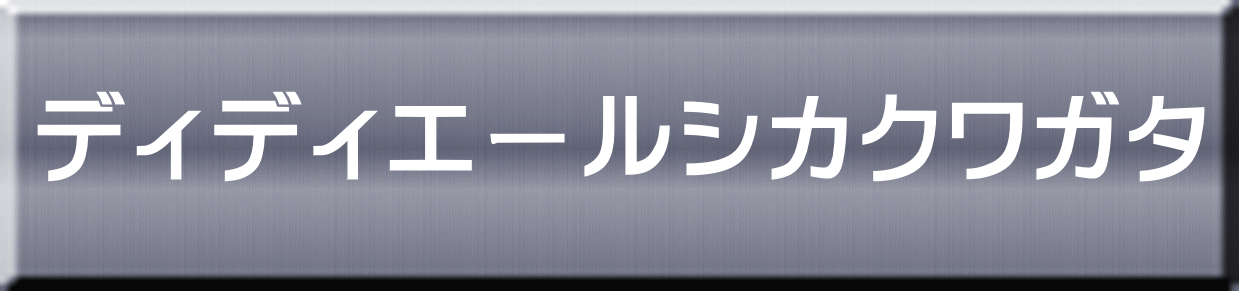
シカクワガタの仲間で、名前の通り大きくシカの角のように湾曲し発達した大顎が特徴です。シカクワガタの仲間(シカクワガタ属)では最大の種類で、和名で「アカミトゲシカクワガタ」とも呼ばれます。野外産の流通は他の外国産クワガタに比べると少ないのですが、シカクワガタとしてはスぺキオススシカクワガタと並び多い部類に入ります。オスは気性が荒いものの長時間の戦いは苦手なようで、組み合ってすぐに決着がつかないと自ら逃げてしまう事もあるようです。その一方でメスに対しては凶暴な一面もあり、飼育下ではオスによるメス殺しに注意が必要となります。特徴的な大顎は図鑑等をよく見て、本物そっくりに仕上げてみてくださいね。「新りったいカブトムシ・クワガタムシ館」収録作品。
分類:甲虫目クワガタムシ科
体長:35~87mm
分布:マレー半島


日差しの強い日によく活動し、成虫はエノキ等の葉っぱを食べますが、幼虫はエノキやマキ、ナツメ、リンゴ等の木の内部を食べて育ちます。全体に緑色の金属光沢があり、背中に虹のような赤と緑の縦縞が特徴的。単に「タマムシ」と呼ばれますが、「ヤマトタマムシ」という事もあります。金属光沢はCDやシャボン玉と同じ「構造色」と呼ばれるもので、死後も色褪せる事が無い為、装身具や法隆寺の「玉虫厨子」にも使われたりしています。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:甲虫目タマムシ科
体長:25~40mm
成虫が見られる時期:7~8月
分布:本州、四国、九州、南西諸島(沖縄島以北)
ヒミツ情報:日本では「タマムシを箪笥に入れると着物が増える」という言い伝えがある。また、どのようにも解釈出来、はっきりとしない事の例えに「玉虫色」が使われる。

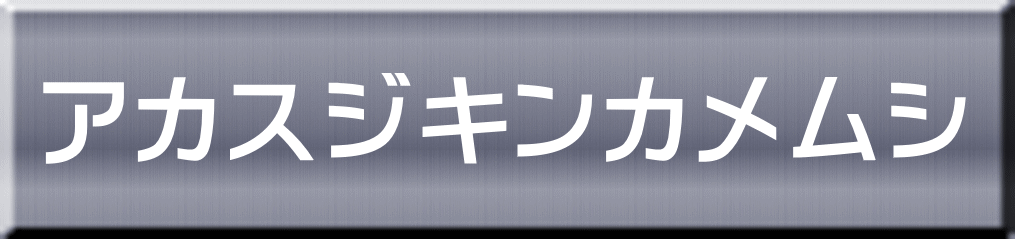
ミズキやキブシ等の実に集まり、汁を吸います。金属光沢のある緑色の美しい虫ですが、稀に黒っぽいものが出現する事もあります。体は楕円形で厚みがあり、キンカメムシの仲間の中でも丸みが際立っています。口吻は細いので、切れないようにゆっくりと抜き取りましょう。「りったい昆虫館」収録作品。
分類:カメムシ目キンカメムシ科
体長:16~20mm
成虫が見られる時期:5~8月
分布:本州、四国、九州


ラベルと標本箱の付いた昆虫のペーパークラフトです。ラベルには作った日と名前を書き込めます。全て「ペーパークラフト無料ダウンロード|ペーパーミュージアム」収録作品。
 アンタエウスオオクワガタ
アンタエウスオオクワガタ ヘラクレスオオカブト
ヘラクレスオオカブト オニヤンマ
オニヤンマ ギンヤンマ
ギンヤンマ
 アブラゼミ。翅を開いたバージョンも作りました。
アブラゼミ。翅を開いたバージョンも作りました。


