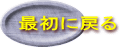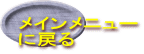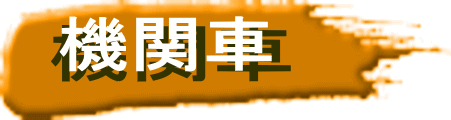
客車や貨車にはモーターが付いていない為、自力で走る事は出来ません。そんな客車や貨車を引っ張るのが、機関車の役目です。動力源によって、蒸気機関車(SL)、電気機関車(EL)、ディーゼル機関車(DL)の3種類に分けられます。工場で新製した車両を引っ張る事もあります。機関車を種類別に見ていきましょう。

蒸気機関車は、石炭を燃やして蒸気を発生させ、その力で動きます。現在は観光用に時々走っていますが、昔は定期的に旅客列車や貨物列車を引っ張っていました。
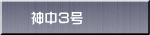
相模鉄道・相鉄線の全身である神中鉄道が厚木~二俣川間を開業した1926年に導入した蒸気機関車です。電化されてからは福島県の江名鉄道という私鉄で働いていました。1967年より、相模鉄道の車両センターに保存されています。前照灯は切れやすいので気をつけてください。また、煙突や蒸気ドームは、差し込んでから糊付けすると、ピッタリの大きさになりますよ。Webページ「そうてつキッズ」収録作品。
ヒミツ情報:正しい読み方を知るまで、僕は「神中」を「じんちゅう」ではなく「かみなか」と読んでいた。


大正時代に造られた旅客用蒸気機関車で、672両が製造されました。「ハチロク」という愛称でも親しまれた機関車です。基本は旅客用でしたが貨物でも運用する事が可能で、その為長く運用されました。写真の作品では京都鉄道博物館に展示されている8630号機をイメージし、除煙板の無いバージョンで組み立てました。2020年の大ヒット漫画「鬼滅の刃」及びアニメ映画「劇場版鬼滅の刃 無限列車編」に登場する無限列車は本形式に類似した機関車が牽引しており、京都鉄道博物館の8630号機は2020年12月26日から2021年3月14日まで、ナンバープレートを「無限」と無限列車と同じデザインにしていました。この写真にはもう一つ別の列車が写っていますが、何だと思いますか?答えはこのページの一番下に書いてあります。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


旅客用の大型蒸気機関車です。1919年に開発され、当初は18900型と名乗っていましたが、1928年にC51となりました。諸外国で高速機関車に好んで用いられる2C1の軸配置、いわゆる「パシフィック形軸配置」を国産設計の蒸気機関車として初めて採用しました。1930年~1934年の間には超特急「燕」の東京~名古屋間牽引機を務める等、幹線の主力機関車として1920~1930年代には大活躍していました。現在でも大宮の鉄道博物館や京都鉄道博物館でも、静態保存ではありますが現物を見る事が出来ます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

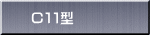
性能がいい事から、1932年~1947年までの間に、381両が製造されました。C10型を改良して造られた機関車で、今でもJR北海道・釧網本線の「SL冬の湿原号」(釧路~標茶、川湯温泉)、、東武鉄道の「SL大樹」(下今市~鬼怒川温泉)、大井川鉄道の「SL急行かわね路号」(新金谷~千頭)等で見る事が出来ます。なお、「SL大樹」として東武を走る前に325号機が使用された「SLもおか」については「楽しい列車」エリアに登場しています。難しくはありませんが、カッターナイフを使う箇所があります。カッターナイフを使う際は、安全に気をつけて使って下さい。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

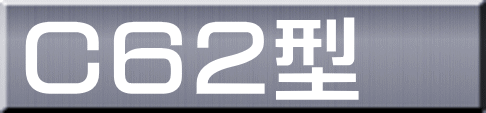
1948年から1949年までの間に49両が製造された、超大型旅客用蒸気機関車です。貨物用のD52型を旅客用に改造したもので、「つばめ」を始めとする様々な特急列車の牽引に主に使われました。写真の作品は除煙板にツバメのマークが付いている為、C62 2号機でしょうか。京都鉄道博物館では、2号機と合わせて、1号機、26号機と、3台が見られます。2号機は動態保存で、体験乗車用列車「SLスチーム号」として走っています。1号機は扇形車庫、26号機はプロムナードで、それぞれ静態保存となっています。パーツも多くて、かなり難易度が高い為、上級者向けの作品です。この写真にはもう一つ別の列車が写っています。何だと思いますか?Webページ「JR西日本:人気列車ペーパークラフトコーナー」収録作品。
ヒミツ情報:狭軌鉄道の世界最高記録、時速129kmを記録した。


貨物用の大型テンダ式蒸気機関車です。1936年から1945年までの間に1115両が製造されました。これは国鉄機関車では最大の両数で、電気機関車やディーゼル機関車を含めても、未だ破られていません。「デゴイチ」の愛称で知られていて、JR東日本の498号機は「SLみなかみ」「SL碓氷」で、2017年に復活運転を果たしたJR西日本の200号機は、C56型に代わって、C57型と共に「SLやまぐち号」で、それぞれ走っています。難易度はそこまで高くないです。組み立てる際、糊代が無い箇所は、ボンドを部品の空間に塗り、接着しましょう。強度が心配な方は、気になる部分を接着しましょう。紙切れを機関車の後ろに貼り、完成した炭水車と一緒に切り込みを入れて、ジョイントを差し込むのも僕イチオシの仕上げ方です。Webページ「JR西日本:人気列車ペーパークラフトコーナー」収録作品。
ヒミツ情報:煙突と蒸気ドームが一体化した「ナメクジ型」や、それが運転台まで届く「スーパーナメクジ型」もあった。


電気機関車は、その名の通り電車と同じ、電気を動力源とする機関車です。寝台特急等の旅客列車を引っ張るものもありましたが、現在は貨物列車に使われる事の方が多い気がします。
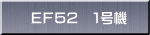
1928年に鉄道省と4つの民間会社の協力で誕生した、日本初の国産電気機関車です。主に東海道線の急行等に使われました。なお、7号機までは旅客用としては歯数比が大きく、加速性能は良いものの高速性能において劣っている為、急行よりも普通列車に充当されました。細かい部品がいっぱいあります。最初は難しく感じるかもしれませんが、落ち着いて仕上げましょう。Webページ「JR西日本:人気列車ペーパークラフトコーナー」収録作品。
ヒミツ情報:基本機関車は何号機かは製造された順番で決まるが、EF52 1号機は6番目の製造。


国鉄が開発した、日本初の2車体連結の8軸電気機関車。「マンモス」という愛称でも呼ばれていました。1954年に登場し、1957年までに64両が製造されました。この写真にはどんな列車が写っているか、分かるでしょうか?合わせて4つ、写っています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


1936年、国鉄の前身である鉄道省によって開発された電気機関車です。流線型の車体が特徴で、流線美を追求する為に電気溶接で組み立てられています。丸みをつける所はつけた方が、美しく仕上がります。「ムーミン」の愛称で親しまれましたが、2009年に引退しました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

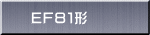
国鉄の交直流電気機関車の代表形式。交流50、60Hz及び直流区間が走行可能で、国鉄からJR東日本、JR西日本、JR九州、JR貨物へ継承されました。「北斗星」を始めとする寝台特急も牽引していましたが、旅客会社は夜行列車が減少した事、JR貨物は後継機が登場した事を受けて、数を減らしています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


国鉄世代の電気機関車では、最もパワーのあった形式です。主電動機は1基あたり650kW。1966年に試作機のEF90形が登場し、1968年より量産機の0番代が導入されました。JR貨物では、1989~1991年までの間に、100番代を33両製造しました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。貨車も同サイトに載っていたものです。
ヒミツ情報:寝台特急を引っ張っていた事もあった。
 一般色のEF66形。この写真、肝心の機関車がピンボケなので、出来たら作り直して取り直したいです。
一般色のEF66形。この写真、肝心の機関車がピンボケなので、出来たら作り直して取り直したいです。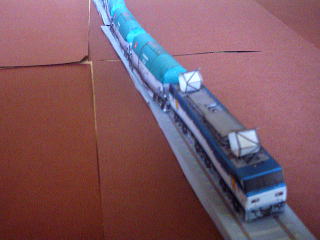 100番代。こっちはなかなか良く撮れました。
100番代。こっちはなかなか良く撮れました。<写真に写っている他の列車の答え>
(8620型「無限列車」)→21000系「アーバンライナー」(「私鉄特急」参照)
(C62型)→特急スーパーはくと号(「私鉄特急」参照)
(EH10形)→E001形「TRAIN SUITE 四季島」(「楽しい列車」参照)、E231系500番台山手線(「通勤列車(JR通勤列車)」参照)、京都市営地下鉄烏丸線10系1次車、あさかぜ(「楽しい列車」参照)