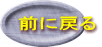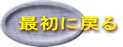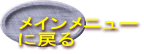碓氷峠専用の補助機関車で、その特殊な性質上、様々な特殊設備を備えています。最大66.7‰の勾配を、2両1組で運転していました。およそ100tの重量車体で、23400kgの牽引力を誇ります。これは1次車で、2次車や3次車はそれぞれ違いが見られます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


1990年に量産先行機が登場し、1992年~1993年に量産機も登場した、前例のない6000kWという定格出力を誇る強力な直流電気機関車です。VVVFインバータ制御が機関車では初めて採用されました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
ヒミツ情報:パワー全開で走行すると沿線の変電所の能力を超えてしまう事、またバブル崩壊により貨物の鉄道輸送の需要が伸び悩んだ事から、結局2019年の引退までパワーを十分に発揮できなかった。

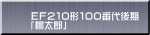
EF65形、EF66形に替わる直流電気機関車として、JR貨物が製作しました。「ECO-POWER 桃太郎」という愛称で親しまれます。VVVFインバータ制御を採用し、出力565kWの三相交流モーターを6基搭載、30分定格出力354kWのパワーが持ち味です。100番代は2000年にデビューした形式で、73両が在籍します。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。
ヒミツ情報:前期型のパンタグラフは下枠交差型だが、後期型はシングルアーム型。

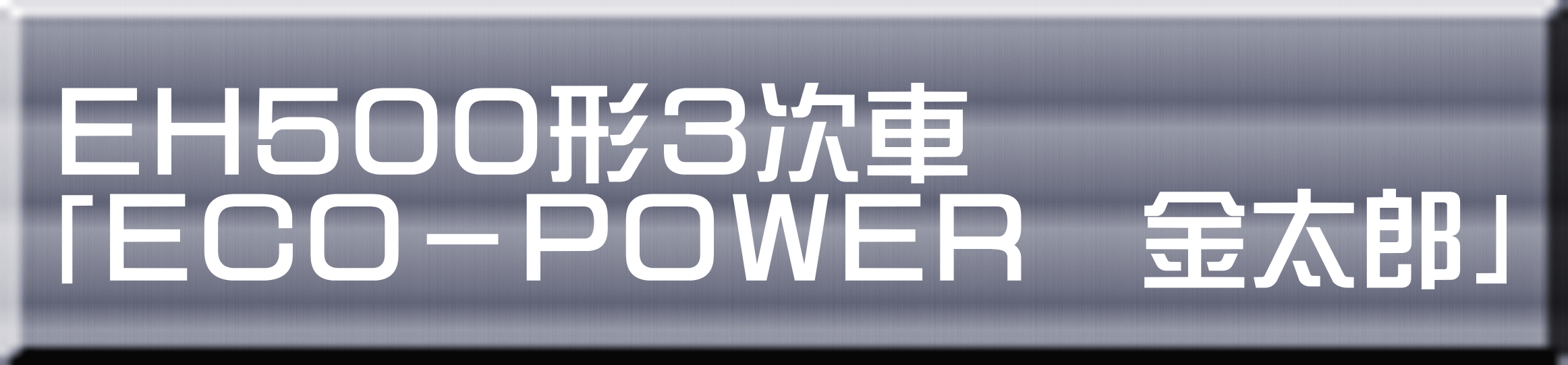
2車体連結の交直流電気機関車で、「ECO-POWER 金太郎」と呼ばれています。EH10形に続く大型機となり、運転整備重量は134.4tにもなります。3電源対応の機能を活かし、隅田川駅、新鶴見信号場から青森信号場までロングランしている他、幡生操車場から関門トンネルを抜け、福岡貨物ターミナルまでの1300t貨物列車牽引もしています。なお、青函トンネルを抜けて五稜郭までの運用がなくなった為、首都圏に現れる機関車は増えると思われます。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

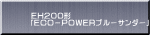
2車体連結の電気機関車で、量産先行機は2001年よりデビューしました。EF64形の後継機にあたる機関車で、主に高崎線、上越線、中央本線、篠ノ井線といった勾配線区に運用されています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

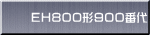
青函トンネル付近の北海道新幹線との共用区間に運転される電気機関車です。2016年に北海道新幹線の新青森~新函館北斗間開業に向けて投入されました。複電圧式の交流電気機関車で、新幹線開業後は、貨物列車のみならず、団体専用旅客列車も牽引しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


黒部峡谷鉄道は、宇奈月と欅平を結ぶ、全長20.1kmの観光鉄道です。EDR形は、全長6.9mの小型機関車。線路の幅が狭いので、小さな車両が活躍しています。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


ディーゼル機関車は軽油を動力源に動く機関車で、ディーゼル機関車には液体式ディーゼル機関車と電気式ディーゼル機関車があります。それぞれ仕組みは異なります。ハイブリッド機関車は、ディーゼルエンジンで起こしたバッテリーの電気で走行します。どちらも電気の通っていない路線でも活躍できる機関車です。

液体式の除雪用ディーゼル機関車で、冬季は車両の前部と後部にラッセルヘッドを装着し、線路上に積もった雪をはね飛ばします。冬季以外は入れ替え用やトロッコ列車の牽引も行います。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。