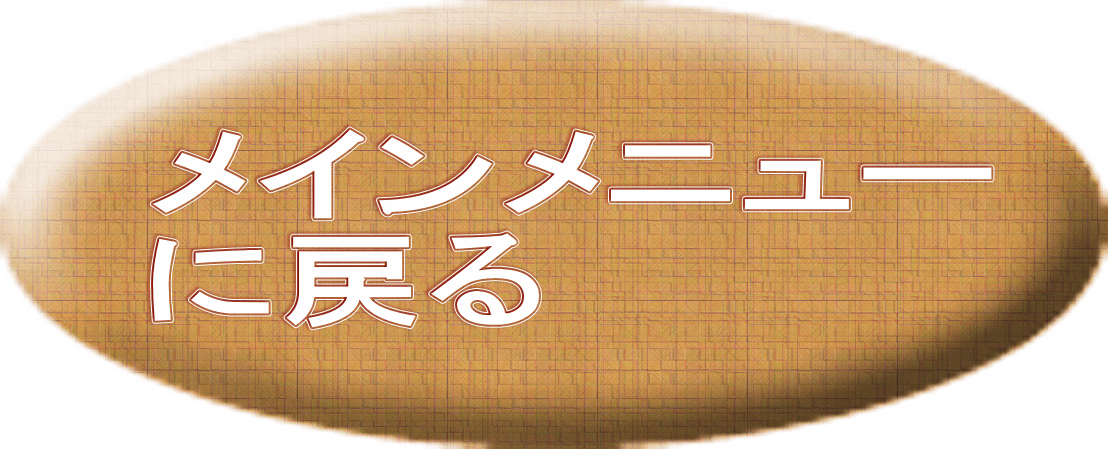学研プラスの空想図鑑シリーズ「最強王図鑑シリーズ」の中の1冊、「ドラゴン最強王図鑑」。その中には僕がイメージしていたようなファイヤー・ドレイクのようなドラゴンの他にも、色々な姿をしたドラゴンや龍が登場しています。僕もそれに創作意欲を刺激され、「ドラゴン最強王図鑑」トーナメント参加選手から選び抜いたドラゴンを折り紙で再現してみました。なお、ファイヤー・ドレイクやファーヴニルのような典型的なドラゴンの姿をしたドラゴンにつきましては、「恐竜」エリアをご覧下さい。なお、ドラゴンの「属性」については、属性相性含めて以下詳しく説明します。

世界は火、水、風、土の四大元素から成るという考えは、古代ギリシャから中世の錬金術まで広く信じられてきました。「ドラゴン最強王図鑑」では、ここに光と闇という2属性を加えて分類しています。
・火 炎、熱等を象徴する属性。風に対して有利で水に対しては不利となる。火を吐いたり火山に棲むようなドラゴンは火属性。一例としてベーオウルフ・ドラゴンやゴルィニシチェ。ファイヤー・ドレイクも火属性。
・風 台風や雷等、自然現象を象徴する属性。土に対して有利で火に対して不利。飛行が得意だったり、風を操るドラゴンが分類される。例としてケツァルコアトルやヴリトラが含まれる。
・土 大地と動植物を象徴する属性。水に有利で風に不利。山や地中にいるドラゴン、大地に関連の深いドラゴンが土属性に入る。ヴイーヴルが分類される。
・水 海や川を象徴する属性。火に有利で土に対して不利。水中や水辺にいるドラゴンや水を司るドラゴンは水属性となる。一例を挙げればレヴィアタンやレインボー・サーペント、タラスク。
・光 神聖な存在で神々のような扱いを受けていたり、神に助力しているドラゴンが含まれる。ムシュフシュや応龍が含まれる。なお、今まで紹介してきた4つの属性のドラゴンと光属性、闇属性のドラゴンは特に優劣は無しとなる。
・闇 神に敵対していたり、悪魔と関係が深いドラゴンは闇属性。一例として聖ゲオルギウス・ドラゴンやアジ・ダハーカが含まれる。闇と光は互いに有利でもあり、不利でもある。

イングランドの紋章や伝承で知られる、一対の大きな翼を生やした二脚の竜です。ドラゴンに比べると体はやや細身で、大きな翼で空を自在に飛び回る事が出来る事から、「飛竜」とも呼ばれます。人間に懐く事もあるらしく、イギリスのモーディフォード村には、少女がワイヴァーンを育てた逸話も残っています。何度か後ろ足と大きな翼の両方を目立たせられる折り方をあれこれ試していたところ、「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」のドラゴンと何か同じような折り方となってしまいましたが、首や翼、足を細く折った事、ワイヴァーンには尾の先端に鋭く尖った毒棘がある事から尻尾の折り方を変えて毒棘も折り出した事、そしてワイヴァーンらしく前足を折っていない事で、オリジナル性を出しています。
属性:風
伝承地域:イギリス
登場する物語:イギリス伝承


中東メソポタミア神話の怪物で、毒蛇のような頭とライオンのような前足、ワシのような後ろ足をしていて、尻尾はサソリのような形をしています。元々女神ティアマトが神々の軍勢と戦う為に作り出した合成獣のうちの1体でしたが、ティアマトが戦いに敗れると、神々のリーダーであるマルドゥクや太陽神アッシュールに仕える神獣になりました。後ろ足のワシの爪やサソリの毒針も上手く折り出せて、納得いく仕上がりにはなりましたが、前足辺りが厚ぼったくなり、胴体が開きやすくなってしまいました。
属性:光
伝承地域:中東
登場する物語:「エヌマ・エリシュ」等

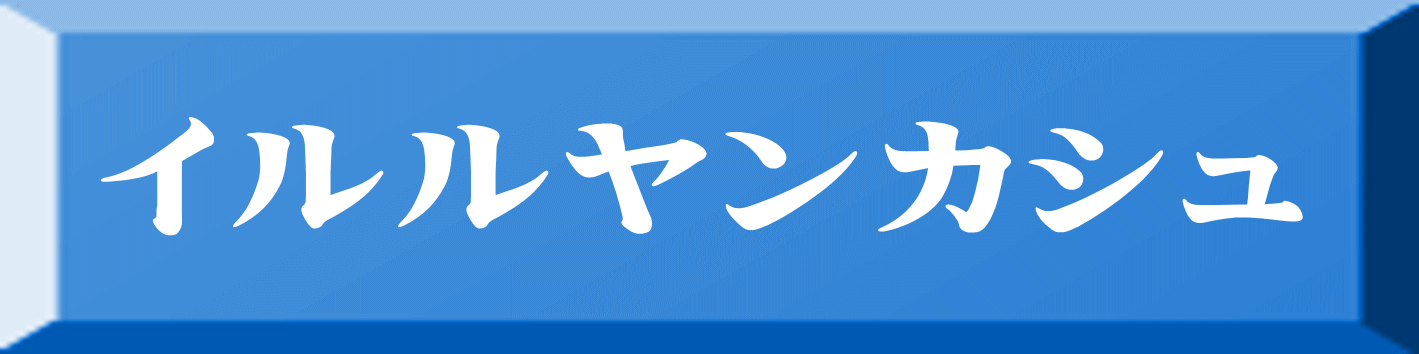
アジア大陸の最西部にあるアナトリア半島(現在でいうトルコ)に王国を築いた、ヒッタイト人に伝承する竜神で、紀元前1500年頃に作られたとされる石版には、大きなヘビとして描かれています。伝承では雷神プルリヤシュと覇権を争って一度は勝利していますが、最後は策にはまって敗れています。凧の基本形をベースに段折りを重ねていった結果、細長い体形だけでなく体に付いているヒレも何とか表現出来ました。後ろ半分のヒレは段折りで折り出しました。紙が重なってて分厚くなった為に中に折り込んだ箇所が段折り時に破けてしまいましたが、木工用ボンドで接着した事により事無きを得ました。頭にあるヒレは完成後に折った箇所です。
属性:闇
伝承地域:アナトリア半島(現在のトルコ)
登場する物語:トルコ(ハットゥシャ)出土のレリーフ


ギリシャ神話の中でも特に恐れられた巨大な蛇竜です。細長い胴体には9つの頭が生えており、それぞれが猛毒の息を吐きます。また、9つある頭のうち1つは不死身、後の8つは斬られたり潰されたりしても、またそこから新たな首が2本生えてくるそうです。猛毒の息は吸っただけで人が死ぬ程恐ろしく、また、ヒュドラーの寝た場所は猛毒が残っている為に、そこを通った者は更に苦しんで死ななければならなかったといいます。しかもその猛毒は解毒不可能だそうです。ヘラクレスが12の功業の1つとしてこの怪物を退治しましたが、従者の手を借りたとして無効とされ、本来10やるはずだった仕事を増やしてしまったうちの1つとされています(もう1つはアウゲイアースの家畜小屋掃除。これは罪滅ぼしであるにも関わらず報酬を要求した為とされる)。また、後にヘラクレスもヒュドラーの猛毒を矢に塗って使うようになったといいます。ヒュドラーといえば9つもある頭ですが、僕は蛙の基本形からパーツを作りました。1つのパーツにつき首が3本になるように足の折り出しも行い、合わせて9本になるようにしました。首は角度を違えて折るといいと思います。
属性:水
伝承地域:ギリシャ
登場する物語:「神統記」「ギリシャ神話」等

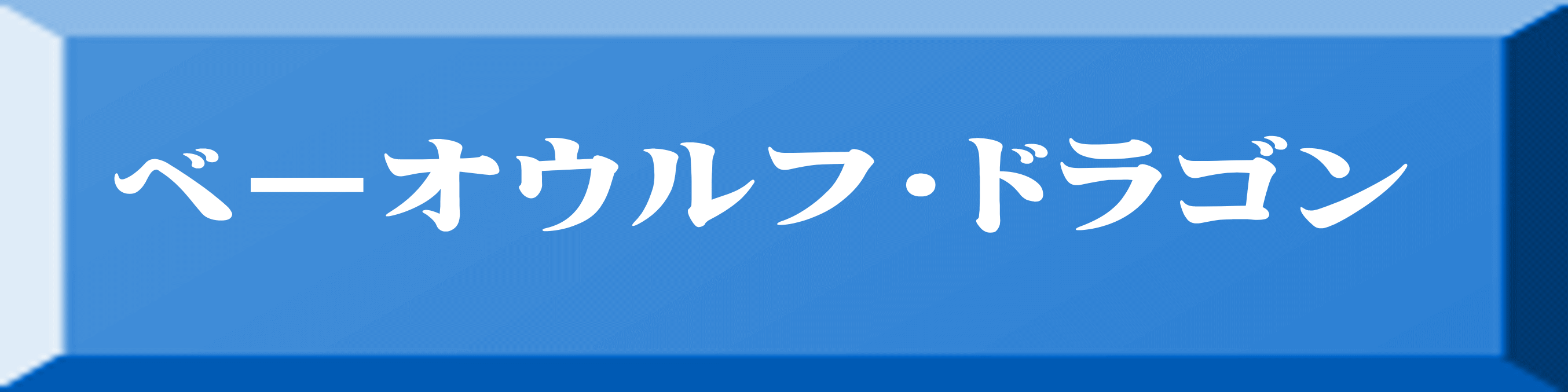
ゲーム等にはよく「財宝を守るドラゴン」というのが登場しますが、その原点といえるのが、イギリスの叙事詩「ベーオウルフ」に登場するドラゴンでしょう。口には毒牙が生えていますが、炎を吐く点はファイヤー・ドレイクと共通しているかもしれません。足が無い為、地上ではヘビのようにスルスルと這って移動するようです。翼を生やしたヘビのような姿で、全身は硬い鱗で覆われています。財宝を好む習性があり、とある王族が宝を隠していた塚に棲んでいましたが、それを盗まれた事で怒り、人間を襲い始めます。最後は老王ベーオウルフと戦って相討ちとなりました。この後紹介するヴイーヴルと、基本的な作り方は一緒です。黒と赤の紙の裏面をそれぞれ貼り合わせて両面折り紙にしていますが、写真のように下アングルから見るとそれが分かると思います。
属性:火
伝承地域:イギリスや南スウェーデン
登場する物語:「ベーオウルフ」

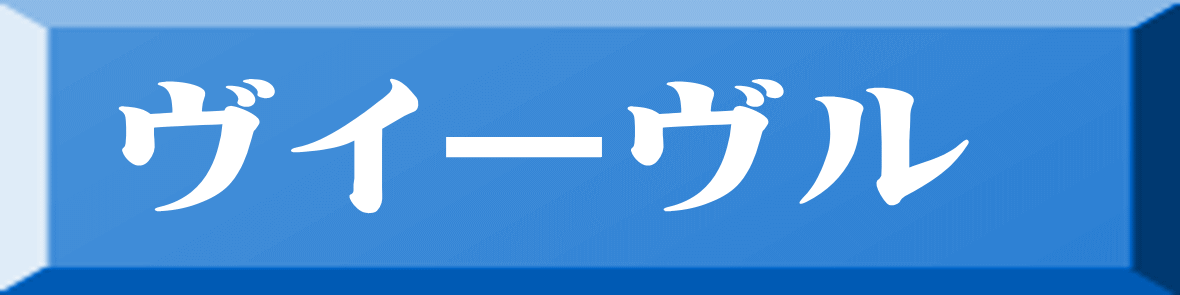
フランス伝承のヘビ型ドラゴンで、額に大きなダイヤモンドが付いています。このダイヤモンドは目として機能しており、川や泉で水を飲む際には外して水辺に置いたそうです。このダイヤを手に入れられると富と権力を得られるという事で、多くの人々がヴイーヴルを狙っていましたが、ダイヤを外したヴイーヴルを目にした者は誰一人としていなかったそうです。因みにヴイーヴルは、ダイヤを奪われると絶望のあまり死んでしまう為、奪われないように必死で守るんだそう。また、ブレス地方には、ダイヤを盗む為の方法も伝わっています。先程のベーオウルフ・ドラゴンと形状が似ていた為折り方は基本同じ感じですが、最大の特徴であるダイヤの表現に苦労しました。なお、頭のうちダイヤの辺りは紙の裏を出した三角形にしています。
属性:土
伝承地域:フランス(ブレス地方、フランシュ=コンテ地方等)
登場する物語:「フランスの民俗」等

 右の写真は上から見たところ。
右の写真は上から見たところ。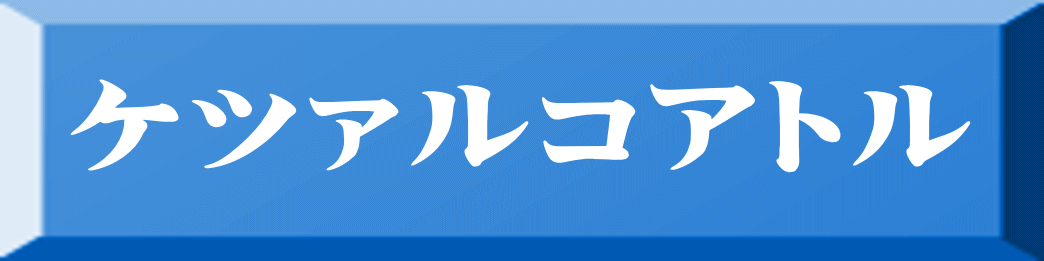
アステカ神話における文化神並びに農耕神。また、風の神とも考えられてきました。古くは水や農耕に関わる蛇神でしたが、後に文明一般を人類に授けた文化神と考えられるようになり、ギリシャ神話のプロメテウスのように、人類に火をもたらした紙とも考えられるようになりました。描かれている姿は様々で、上半身が人間で下半身はヘビだったり、名前の意味通り「羽毛のあるヘビ」として描かれる事もあります。人の姿でも、岩を叩いただけで手の跡が残り、また、山や森を平地にする力もあるそうです。「ドラゴン最強王図鑑」の挿絵では、翼は3対だったようですが、僕が勘違いをしていた為この作品では翼が2対となってしまいました。スタンドを使ってもなかなかバランスが難しく、撮影に難儀しました。
属性:風
伝承地域:メソアメリカ
登場する物語:アステカの金石文や諸文献


中国には様々な龍が伝えられていますが、いずれも成長途中の段階で、3000年もの年月を経て、最終段階まで成長したものがこの応龍という訳です。神通力を身につけた神のような存在で、天界と地上を行き来出来る神龍です。古代中国の王達に力を貸していて、例えば神話時代の8人の聖王・三皇五帝に名を連ねる黄帝に助力した際には巨人族とされる夸父や、敵の総大将であった蚩尤を討ち取る等、戦の中で大きな功績を挙げています。中国の龍の殆どには翼がありませんが、応龍には猛禽類かコウモリのような翼があり、諸龍の王とされています。本体は基本的には「折り鶴から折る おりがみ恐竜大国」の龍とあまり変わらないように思えますが、実は折り方を変えて、翼を付けられるように「背割れ」の龍になるようにしているのです。また、角や尻尾の形状も少し違っています。
属性:光
伝承地域:中国
登場する物語:「山海経」「本草綱目」「和漢三才図会」等
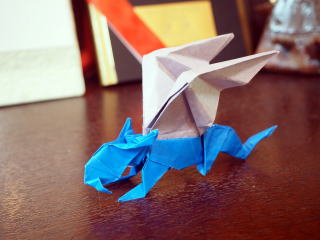

薬物についての知識をまとめた中国の書物「本草綱目」等に記述がある中国の龍です。それによると「蛟龍」とよばれる龍の一種で、ヘビのような姿をしており、腰から下の鱗は逆向きに生えているそうです。口から気を吐いて幻影、いわゆる「蜃気楼」を発生させます。その為「蜃樓」や「海市」とも呼ばれますが、これはいずれも「蜃気楼」の別名です。ヘビとカメの子供がキジと交わる事で生まれる等、出自にもいくつかの話があります。因みに蛟龍は成長しきっていない龍の事であり、それが成長しきったものが1つ前の応龍ともいわれています。細長い体形を強調して仕上げているので「ドラゴン最強王図鑑」の挿絵のようなヒレはあまり見られませんが、頭のヒレは小さいながら作ってありますし、肩辺りにあるヒレも強調しています。前足はあまり目立ちませんが、中割り折りを繰り返して小さな前足を作り出しました。一方の後ろ足も小さく、1本分しか折り出せなかった為バランスはかなり悪いようです。
属性:水
伝承地域:中国
登場する物語:「本草綱目」「三才図会」等

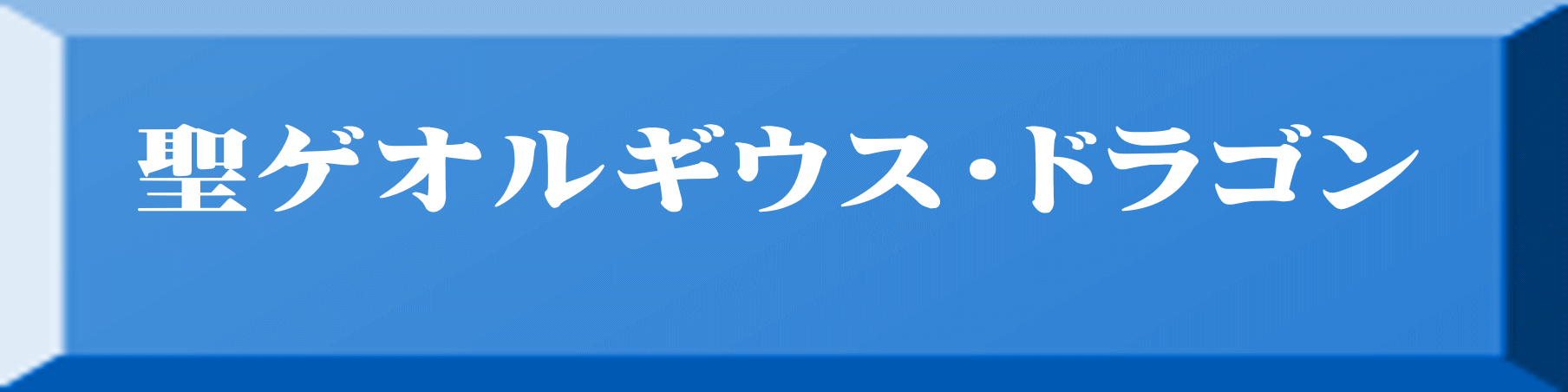
北アフリカのリビアという国にある小国・シレナに棲みついていたというドラゴンです。姿は伝承によって異なっていますが、絵画等では2本の足と大きな蛇の目の模様入りの翼を生やした黄緑色のトカゲとして描かれています。カッパドキア(13世紀の「黄金伝説」では舞台がリビアのシレナである)を訪れた際に伝染病を引き起こす毒の息を吐くドラゴンの話を聞いた、騎士であり、キリスト教の聖人でもある聖ゲオルギウスは、討伐を申し出ました。聖ゲオルギウスはドラゴンが口を開けたところに槍を突き刺して深手を与えると、生贄となる為に同行していた王女に帯を借り、ドラゴンの首にかけて街に連れ帰ります。街は大騒ぎになりましたが、聖ゲオルギウスは住人がキリスト教徒となり洗礼を受けるならばドラゴンを殺すと宣言し、シレナの王を含む1万5000人がキリスト教徒に改宗した後、ドラゴンを殺したといいます。絵画等では小さく描かれがちなのですが、その死体を運ぶのに8頭もの牛が必要だったといいますから、結構大きなドラゴンだったのかもしれませんね。ワイヴァーンを折った際の反省点を踏まえ、こちらは複合作品にしています。複合にすると翼、出来栄え共にシンプルになり、2色の色分けも出来ました。
属性:闇
伝承地域:リビア
登場する物語:「黄金伝説」