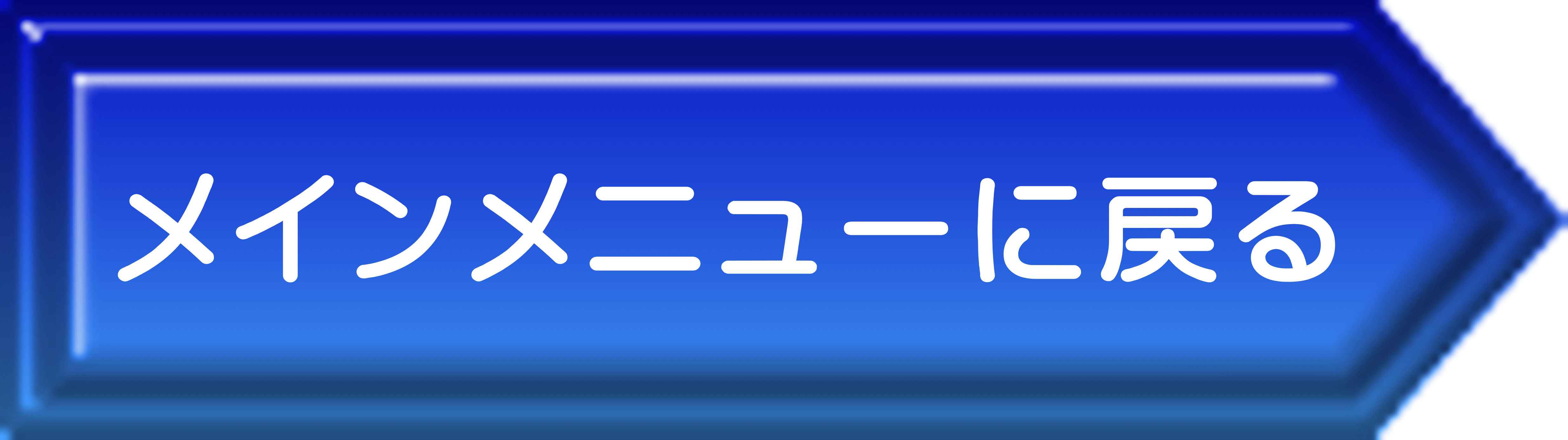EF52形は、1928年に新製された国産電気機関車初の幹線用大型電気機関車です。鉄道省と各メーカーによる共同設計で、輸入機の中で使用実績の優秀だったアメリカ・ウェスティングハウス社製のED53形、EF51形の影響を受けています。7両が芝浦製作所(現・東芝)、三菱電機、川崎車輌、日立製作所の4社へ同時に発注された関係で、番号順の竣工では無く、1号機は6番目の登場となりました。7号機までは、旅客用としては歯数比が大きく、加速性能は良いものの高速性能において劣る設計で、急行よりは普通列車に多く使われていました。1931年には、歯数比を旅客用で一般的なものに変更した8・9号機が川崎車輌で製造されましたが、翌年にEF54形へ変更されました。新製当初は、国府津機関区に配置され、東海道本線で旅客列車を中心に担当していましたが、戦後は歯数比が勾配線区向きである事から、一部が甲府機関区に転じて中央本線の旅客列車を牽引、更に1958年までに全機が阪和線に転じ、旅客列車と貨物列車の双方を担当していました。その後、1975年にさよなら運転を行い、全機廃車となりました。1号機は日立製作所で新製され国府津機関区に配置、1952年に2号機と共に鳳電車区に転属し、阪和線で走り始めました。1968年に同形機全機と共に竜華機関区に転属、1973年に廃車となった後は竜華区の扇形庫内で保管され、1977年10月から交通科学館(後の交通科学博物館)で保存されました。