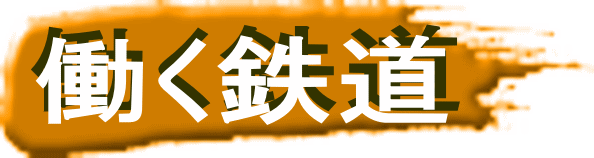
鉄道車両には、色々な種類があります。そしてその役割も、列車ごとに様々です。お客さんを乗せて町と町をつなぐ列車だけでなく、沢山の貨物を引っ張ったり、列車の走る線路の点検を行う保線用の車両もありますよ。ここでは、そんな普段滅多と見れない働き者達をご紹介します。
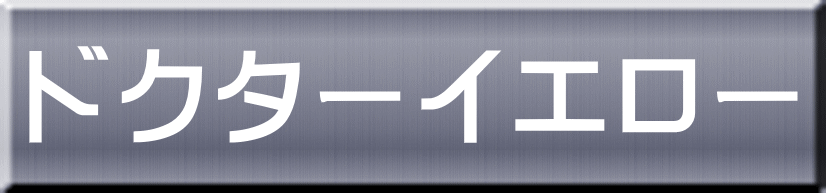
正確には「電気・軌道総合試験車」ともいい、線路の歪みや電気設備を検査する車両です。このドクターイエローは923形と呼ばれる形で、700系新幹線をベースに設計されました。電車は7両編成で、車内はそれぞれ1号車が電気検測室、2号車が電力・集電の測定(主にトロリ線の摩耗)を行う車両、3号車が屋根部分にパンタグラフ等をチェック出来る観測ドームを設けた電力チェックの車両(5号車にも観測ドームはあるが階段周辺の構造が若干異なり、休憩室が設置されている)、4号車はレーザーを使って線路の歪みを見つけ出す軌道検測車、そして6号車がミーティングを行うスペース、そして7号車は各種添乗、視察に適した添乗員室になっています。「見ると幸せになれる」という噂があり、「幸せの黄色い新幹線」と呼ばれてきたドクターイエローですが、2027年度には完全引退する予定であり、完全引退後はN700Sに搭載されている営業車検測機能で代替する方針です。作る際のコツは、「新幹線」エリアで紹介しているN700Aのぞみや700系ひかりレールスターと同じです。Webページ「JR西日本:人気列車ペーパークラフトコーナー」収録作品。
ヒミツ情報:4号車のみ熱による検測結果への影響を防ぐ為、屋根は白色になっている。

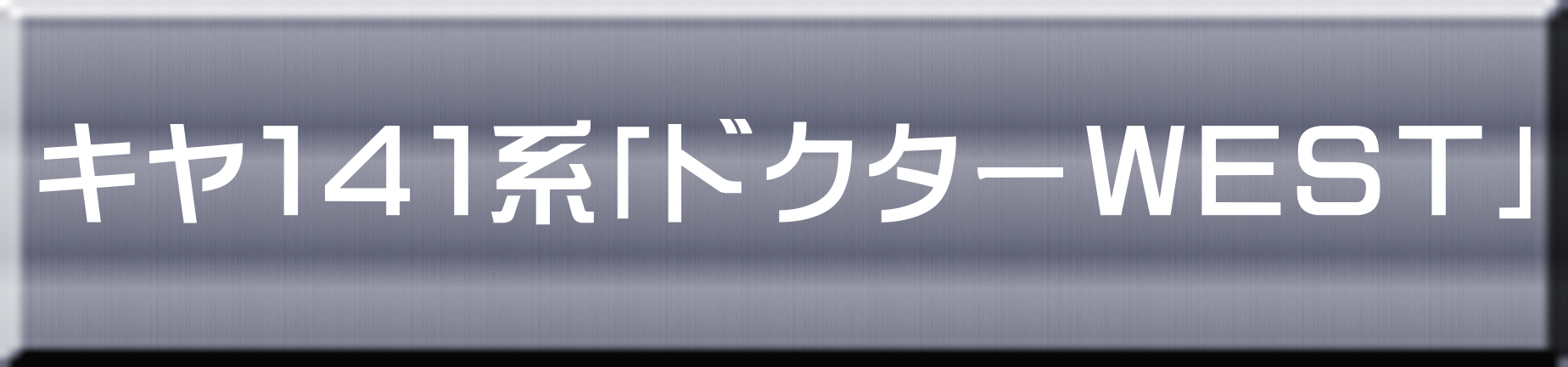
JR西日本の検測用車両ですが、ごくまれにJR四国やJR九州、他にも線路がつながっている一部の貨物線や第三セクター、私鉄でも走行します。基本的な走行システムは特急形気動車のキハ187系や一般形気動車のキハ126系に準じたものとなっています。「ドクターWEST」というのは鉄道ファンがつけた愛称です。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


東急電鉄の総合検測車です。動力車、軌道検測車、電気検測車の3両から構成されていて、屋根にある観測ドームから、架線がすり減っていたり飛来物が付着したりしていないか確認できます。また、ATSとATCの両方の走行システムを搭載している為、線路幅が異なる世田谷線以外の区間を全て走行する事が出来ます。基本的には軌道検測車を組み込んで3両編成で運転しますが、架線の確認のみ行う時は2両だけで走行します。この写真にはもう一つ、別の列車が写っていますが、何だと思いますか?Webページ「ぺパるネット」収録作品。


小田急電鉄の総合検測車で、ちょっと変わっているのは営業中の電車に連結されて、その状態で軌道や架線の検測を行える事。小田原方面の車内は測定室となっており、各種測定機器が搭載されている他、どの場所からもパソコンが接続できるよう10か所にコンセントを備えています。新宿方面の車内は中央に通路を配置した機器室です。運用する際は1000形に連結されて走行していましたが、後に8000形に連結されるようになりました。この写真にはもう一つ列車が写っています。分かりますか?Webページ「Vayashi’s11」収録作品。


近鉄の通勤車両・2410系を改造して造られた電気計測車両で、電車線の摩耗や高さ、ATS等の検査を行います。モワ24とクワ25の2両編成ですが、クワ25は台車を変えて、標準軌(1435mmの線路幅)だけでなく狭軌(1067mmの線路幅)の検査も可能です。なお狭軌の路線を検測する際には3両編成の6200系や養老線では2両編成の610系に連結して走ります。この写真にはもう一つ別の列車が写っていますが、何だと思いますか?Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

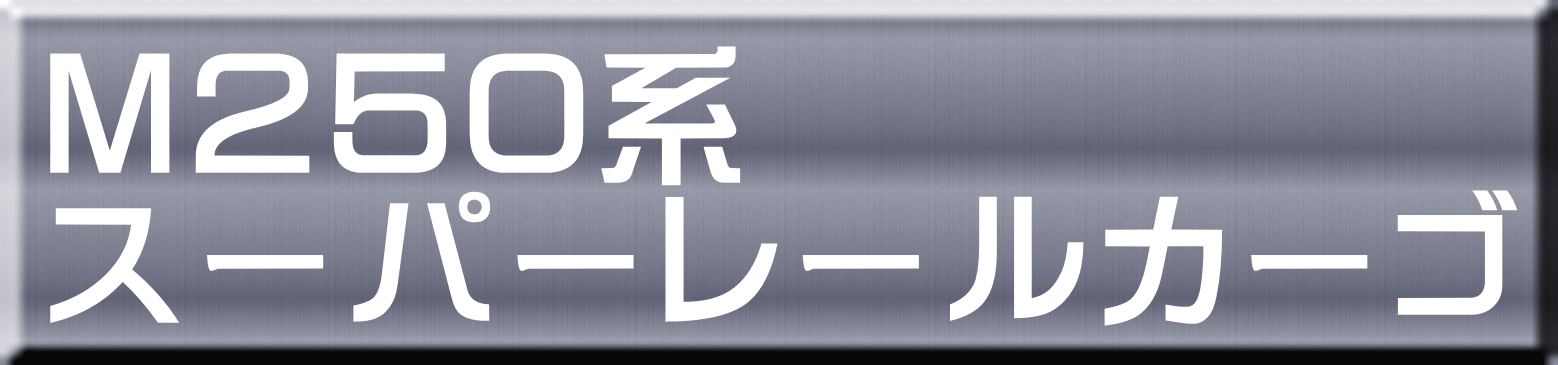
JR貨物が佐川急便と共同開発した貨物電車で、東京から大阪の安治川口という所までを、およそ6時間で走り抜けます。最高時速は130kmで、日本の貨物列車ではトップクラスのスピードを誇ります。特徴は列車に積んでいたコンテナを、そのままトラックに積みかえたり、またその反対に、トラックのコンテナを列車にそのまま積みかえたり出来る事。2005年には鉄道友の会より、貨物専用形式としては初となる「ブルーリボン賞」も受賞しました。Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

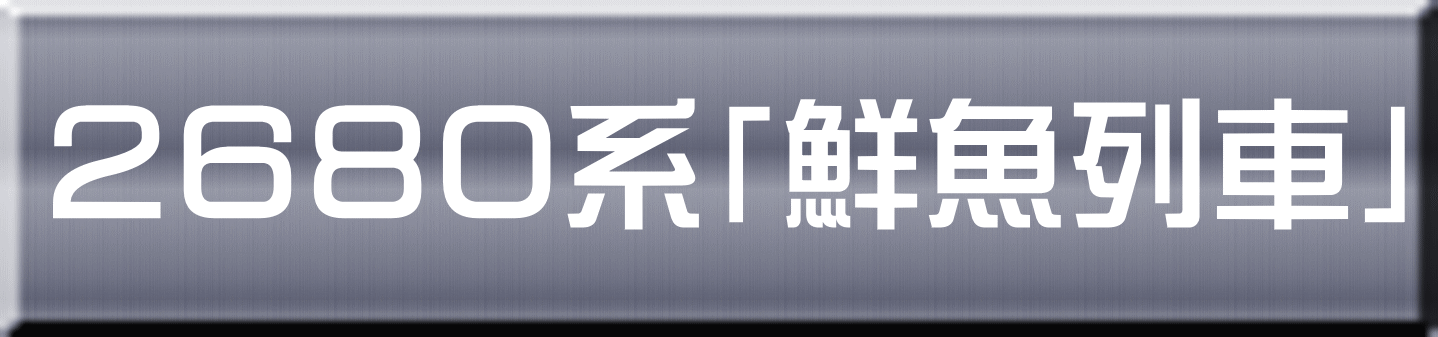
近畿日本鉄道が運用していた行商用の電車で、2020年まで走っていました。連合会の会員以外は乗る事が出来ず、また時刻表にも掲載されていない為「幻の電車」と呼ばれています。伊勢湾で獲れた海産物を都市に届ける役割をしていました。現在では後継として「伊勢志摩お魚図鑑」という車両が一部の通勤列車に組み込まれる形で運用しています。この写真にはもう一つ列車が写っています。さて、何でしょう?Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

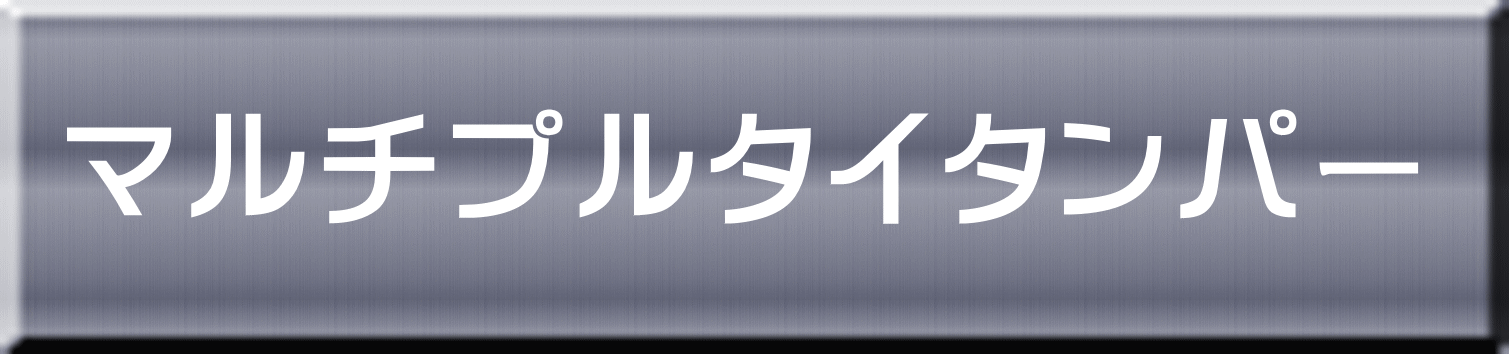
線路は毎日、沢山の電車が走っているので、放っておくと沈んだり歪んだりしてしまいます。その為定期的に線路のメンテナンスを行う必要があります。以前は人の手でメンテナンス作業をしていたのですが、このマルチプルタイタンパー、通称マルタイは、人の手でやるよりも何倍も速く、しかも正確に線路のメンテナンスを行う事が出来ます。この作品は京成電鉄のマルタイです。見た感じは鉄道車両のように思えますが、厳密には「保線機械」という扱いになります。この写真にはもう一つ列車が写っています。何だと思いますか?Webページ「Vayashi’s11」収録作品。

(写真に写っていた他の列車の答え)
(7500系「TOQi」)キハ183系「クリスタルエクスプレス」→「楽しい列車」参照
(クヤ31形検測電車「TECHNO-INSPECTOR」)115系中国地域色→「通勤列車(JR通勤列車)」参照
(モワ24系「はかるくん」)713系宮崎サンシャイン色→「通勤列車(JR通勤列車)」参照
(2680系鮮魚列車)1600系→「私鉄特急」参照
(マルチプルタイタンパー)E257系500番台→「JR特急」参照

